学習院大学名誉教授 戸松秀典

昨年(令和元年・2019年)の春秋に行われた今上天皇の即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、および饗宴の儀といった行事は、大きく報道されたので、それを目にした人は多いと思います。ここで焦点を当てたいのは、三権の長が揃って参列している様子のことです。安倍晋三内閣総理大臣、大島理森衆議院議長と山東昭子参議院議長、さらに大谷直人最高裁判所長官が儀式の場に並んで赴き着席している姿に、私は、強い印象をもちました。このように、天皇がご臨席の会場に三権の長が揃った光景は、特別なことだといってよいのではないでしょうか。
私の印象の中心には、日本国憲法第1条が浮かんでいます。すなわち、同条では、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、・・・」とうたわれています。上記の光景は、これを表しているといえるのではないでしょうか。上にあげた人物は、それぞれが行政権、立法権、司法権を担う機関を代表しており、主権者である国民を背景にして天皇の即位に伴う重要な式典に参列しているわけです。そして、特にここで注目したいのは、最高裁判所長官についてです。
前回(29回)「誰が憲法上の価値を決定するのか」で指摘したことですが、最高裁判所裁判官をはじめとする裁判官は、国民から選出されてその地位に就いているわけではありません。しかし、主権者である国民の意思と隔絶せず、むしろ結ばれていなければならないといえます。そこで、上記の場面で、参列している三権の長のうち、最高裁判所長官は、他の行政権や立法権の長とは異なり、国民との結びつきが選挙過程とは別の意味をもった存在だといえそうです。この前回の指摘にかかわることについて、今回は、少し立ち入って考えてみることにします。
最高裁判所は、その長たる裁判官と、裁判所法で定める14人の裁判官で構成されています(注1)。長たる裁判官は、最高裁判所長官と呼ばれ、内閣総理大臣と同様、内閣の指名に基づいて、天皇が任命することになっています(注2)。他の14人の裁判官は、判事と呼ばれ、内閣がその任命をすることになっています(注3)。
(注1)憲法79条1項と裁判所法5条1項・3項参照。
(注2)憲法6条1項、2項参照。衆議院と参議院の議長は、国民から選出された議員が選んでいるので、天皇の任命行為はありません。
(注3)裁判所法39条2項。なお、最高裁判所のホームページには、現在の最高裁裁判官の経歴や人物像が紹介され、さらに、歴代の裁判官の一覧表が掲載されています。
このような最高裁判所裁判官の任命手続きについて、国の統治機関の三権に浸透しているはずの国民主権原理が認められるか問う必要があります。この問いには、裁判所およびその担い手の裁判官が司法の独立や裁判の公正といった、立法権や行政権に対するのとは異なる価値原理が求められることを看過できません。このようなことはいうまでもないとたしなめられるかもしれませんが、私は、つねづねその基本的理解が社会に浸透していないと嘆いております。その浸透度合いが低いためだと受け止められる現象がよくみられます。
まず、社会での注目度合いについてです。最高裁判所長官や最高裁判事に対しては、司法部門における法秩序維持の最高の責任者として、注目するとともに、絶えず関心を抱いていなければなりません。その動向を無視したり放置したりしていると、国民のための法秩序でなくなるおそれがあります。しかしながら、最高裁判所長官や最高裁判事の任命と退任について、社会でも関心はかなり低いようです。それは、マスコミの取り上げ方に表れています。たとえば、最高裁判事の就任についてのニュースは、内閣の大臣の選任より小さく扱われています(注4)。
(注4)実は、芸能人の結婚や死去のニュースが新聞の紙面を大きく占めているのを目にして、苦々しく思っているのですが、それには価値観の異なる問題がかかわっていくので、ここでは立ち入りません。
本欄では、性差別の解消が進んでいないことを一度ならず取り上げました(注5)。そのときは言及しませんでしたが、女性裁判官についても、西欧の水準からみれば、法曹の中で数が少なく、問題としては変わらない状況だといえます。そして、ここでは特に女性の最高裁裁判官について、指摘しておきます。すなわち、女性の最高裁裁判官は、1994年に初めて就任し、今世紀に入ると、三つの小法廷に一人ずつ席を占めるようになったのに、現在ではそれが崩れております(注6)。それは、内閣の大臣もわずか二人が女性であることと同じような状態といえます。これにについて、社会で問題とされたり議論されたりしたことがないようですが、読者の皆さんの関心をうかがいたいものです。
(注5)本欄第5回「ランク付け――平等社会」や 第16回「平等社会――性差別解消を考える」を参照。
(注6)1994年就任の高橋久子裁判官をはじめ、横尾和子、櫻井龍子、岡部喜代子、鬼丸かおる、宮崎裕子、岡村和美裁判官で、現在は、最後の二人の裁判官です。なお、15人の最高裁裁判官は、5人の小法廷に帰属しており、このことにかかわる裁判事情については、別の機会にとりあげます。
さて、もう一つ関心を向けたいことは、どのような経緯を経て最高裁裁判官が人選され任命されるのかということですが、日本では、徹底した人事の秘密が貫かれ、おおよその推測しかできないのです。ただし、任命された裁判官がすぐれた法律家であり、人物であることは、歴代の裁判官から明らかです。それは、裁判所法が最高裁裁判官の任命資格として、「識見の高い、法律の素養のある年齢40歳以上の者の中から・・・任命」すること、さらに、そのうち少なくとも10人以上が一定年数法曹職にあった者であることを定めており(41条1項~4項)、この規定を反映させた任命がなされているからだといえます。しかし、前述したように、最高裁判所も、国民主権原理に基づいた存在ですから、裁判官の任命過程を公開したり、そこに国民の意思が反映されたりすることが望ましいといえます(注7)。この要請は、司法制度改革の課題として取り上げられたり、話題となったりしたことがないまま今日に至っております。
(注7)最高裁裁判官の国民審査の制度(憲法79条2項~4項)がありますが、これは、解職(リコール)の制度だとされているものの、その意義に疑問がもたれ、機能していません。
以上は、最高裁裁判官の任命にかかわることの一端にすぎませんが、それを念頭において、さらに、前回に少しふれた憲法81条の司法審査権の行使がいかに展開されてきているかについて興味がわいてくるはずです。それは、簡略に語ることができないので、今後おいおい触れることにします。ここでは、最高裁判所は、憲法秩序の形成にかかる役割を、かつては消極主義とか慎重すぎるとかの性格付けがなされました、今世紀に入るころから、次第に、ゆるやかですが積極的姿勢を示すようになっているとの指摘をするにとどめておきます。
この概略の指摘に関連して、場面を今回のはじめに注目したところに戻します。それは、最高裁判所長官が内閣総理大臣と国会の両院の議長と並んでいる場面です。前述したように、最高裁判所長官は、他の二権の長とは異なる性格であることを念頭におく必要があります。言い換えると、同長官は、司法分野の長であって、政治部門の長とは区別されるということです(注8)。
(注8)国の統治機関を権力分立とか三権分立と呼ぶ関係にあると、とりわけ高校以下の教科書で説明されていますが、三角形の図の三頂点に、国会、内閣、裁判所をおいての解説は、実態と異なり、誤解を招くものだと私は批判してきました。三権は、国会と内閣の政治部門と裁判所の司法部門とに分け、それぞれには図式的には説明できない相互関係が働いていると捉えるのが適切です、本コラムでは、これを基礎にした説明をします。
この認識を基盤にして、最高裁判所は、国民の期待に応えているかと問うてみる必要があります。その考察は、前述した、憲法秩序の形成において、ゆるやかな積極姿勢を示しているとの結論について、それがどのように展開されてそういえるのか、分析することです。前回の本欄で、最高裁判所は、立法裁量の法理によって合憲性の判断をすることが少なくないと指摘しましたが、それはどのような具合に、何が根拠となって適用されているのでしょうか。こうした関心は、次回以降でとりあげる課題です。
最後に指摘しておくべきことがあります。それは、本格的な政権の交代がないことです。もちろん、自民党が民主党に政権をゆずったり、連立政党に委ねたりした時期がありますが、それは、短期間であったため成果をみせる政治の展開がなく、いわゆる政権の交代による政治状況の大きな変化といえるものは生じていません。むしろ一党独裁と呼ばれそうな政治状況が続き、しかも改革志向の政治となっていない状態です。これが最高裁裁判官の人事はもとより、裁判、とりわけ憲法訴訟に対する裁判に反映されているのではないか、という問題点を生み出します。
今回は、考えるべき課題をいくつか指摘しました。
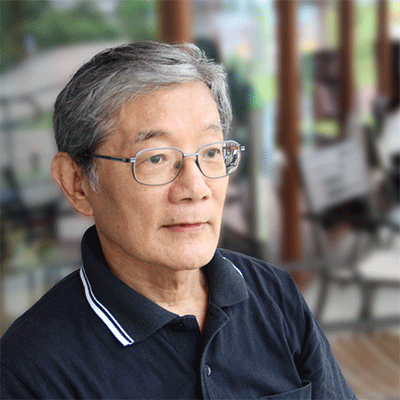 戸松 秀典 憲法学者。学習院大学名誉教授。
戸松 秀典 憲法学者。学習院大学名誉教授。
●著書等
『プレップ憲法(第4版)』(弘文堂、2016年)、『憲法』(弘文堂、2015年)、『論点体系 判例憲法1~3 ~裁判に憲法を活かすために~』(共編著、第一法規、2013年)、『憲法訴訟 第2版』(有斐閣、2008年)、『憲法判例(第8版)』(有斐閣、2018年)、など著書論文多数。
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?