学習院大学名誉教授 戸松秀典

本欄でよく述べていることですが、憲法の規定は、一般的で抽象的な内容となっており、ある規定から論理必然的に具体的内容が導き出され、それが法制度として確定するといったことはほとんどありません。このような憲法規定の性格ゆえに、時の経過とともに、憲法価値の具体的実現をしたはずの法律の規定に対して、見直しを迫られ、違憲であるとの主張がなされる場合があります。今回は、家族法の規定について、そうした事態が生じていることを取り上げることにします。そして、前2回(第29回、第30回)で注目した最高裁判所の役割についても合わせて考えることにします。
家族法は、民法の第4編の親族と第5編の相続に関する規定部分を指しますが、それは、日本国憲法の誕生に伴い全面的に改正されて登場しているので、その意味では、日本国憲法とともに新たな国法秩序が形成されたといってよいでしょう。ところが、憲法の70年余りの体験の過程で、憲法秩序の具体的実現をしたはずの規定の中には、憲法に合致しないから改正すべきとの見直しの論議がいくつか登場するようになっています。いうまでもなく、日本国憲法は、一度も、どの条文についても、改正がなされていないのですから、憲法に合致しないということの意味は、憲法秩序の具体的実現内容が時の経過とともに変化したため再検討の必要性が生じたということです。どの規定について、そのような状態となっているか、次に列挙します。
以上の他にも提起されている問題がなくはないのですが、このような代表的問題が立法府である国会をとおして順調に解決されているわけではありません。次にみるように、上述の①と②については、改正されたことの指摘をしているように、進展がみられたのですが、③と④については、日本の法秩序の在り方として大いに検討せねばならない問題を抱えております。
上記の四つの見直しと改正の対象規定は、それぞれ簡略に語ることが容易でない内容を含んでおりますが、ここでは、提起された訴訟の動向を、最高裁判所の判断に焦点を当ててみることにします。
まず、①については、最高裁判所が正面から民法900条4項ただし書きを、憲法14条1項の平等原則に違反するとの判断を下しました(注1)。最高裁判所は、平成7年以来、何度か裁判をしておりましたが、これに至って国内のみならず国際的な非嫡出子の法的処遇の仕方の変化に注目して、当該規定には正当化の合理的根拠がないと判断したのでした。
(注1)最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁。従来の紹介どおり、裁判内容を手っ取り早く読むためには、戸松=初宿・憲法判例8版のⅢ-3-14参照。
次に、②については、最高裁判所は、民法733条1項の定める再婚禁止期間6か月のうち100日超過部分は、父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止しており、憲法14条の平等原則と憲法24条の両性の本質的平等を侵害するとの判断を下しました(注2)。つまり、違憲だとして争われた民法733条1項の定めのうち一部が違憲であるとされたので、めずらしい判断手法だとして、注目され、学説上の論議をよびました。
(注2)最大判平成27年12月16日民集69巻8号2427頁。戸松=初宿(前掲)Ⅲ-3-7参照。
さて、③については、本欄ではすでに個別にとりあげましたので、思い出していただければ幸いですし、第13回のコラムを参照し直していただくようお願いします。最高裁判所は、要するに、民法750条が生じさせている不都合を解決するのは、立法府である国会の役割であり、裁判所ではないと、冷たい判断を下したのでした(注3)。
(注3)最大判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁。戸松=初宿(前掲)Ⅲ-3-16参照。
さらに、④については、最近、最高裁判所の判決が登場しましたが、裁判内容については、新聞報道によらざるを得なく、最高裁判所のホームページに搭載されていません。新聞記事によると、民法744条の合憲性を争った訴訟の下級審判断が維持され、最高裁判所の憲法に関する見解は全く示されていないということです(注4)。その下級審裁判所は、立法裁量論によっているので、最高裁判所は、それでよしとしたのでしょう。
(注4)日本経済新聞2020年2月8日朝刊。最高裁判所のホームページには、最近の判例が掲載されるようになっていますが、それは、限られたもので、本件のように新聞で報じられていても掲載されていないものがあります。これは、最高裁判所に充てられる予算が少ないためなのか原因は分からないが、裁判の公開の意味が薄れ、司法国家の地位が低くなっていることは確かです。なお、本欄は、一般の読者向けですが、下級審判決の所在を記しておきます。第一審は、神戸地判平成29年11月29日訟務月報65巻4号643頁、第二審は、大阪高判平成30年8月30日訟務月報65巻4号623頁。
以上の動向に照らすと、最高裁判所は、家族法における憲法上の見直し問題に対して、それほど積極的な姿勢でないことが明らかです。①や②の裁判結果をみると、前回(第30回)の本欄で指摘したように、ゆるやかな積極主義と呼ぶ程度だといえます。その原因は、最高裁判所の裁判官の憲法感覚にあるといった単純なことでなく、いろいろな観点からの分析が必要だと考えています。そして、重要な分析要素として、上記四つの問題点にかかわる事実があります。ここでは、それにふれるゆとりがないのですが、興味のある方は、上記の裁判例に示されている当事者にかかわる事実を見て下さい。次に述べる立法裁量論は、そこにも関係しております(注5)。
(注5)次の論述は、四つの問題に関して訴えを提起した者にかかわる事実や対象規定にかかわる社会での実態を基盤としております。
最高裁判所は、上記の四つの問題の解決にあたり、自ら判断を下すか、それとも立法府に判断を委ねるかの選択をしております。
上記の①の問題との関係では、その選択を決定づけたのは、嫡出子の相続分の半分しか得られない非嫡出子(原告)の実情です。原告が被相続人の生前に尽くした労苦に照らすと、相続分の配分があまりに不平等で不合理であるといわざるを得なく、そのような法秩序は、世界の諸国における非嫡出子への法的処遇の変化とかけ離れたもの言わざるを得なくなっているのです。最高裁判所は、こうした事実に注目して、民法900条4号ただし書きを違憲と判断したのでした。最高裁判所が自己の判例を変更して、その結論に至ったのは、立法府の裁量に委ねていては、法的正義が失われると判断したからだといってよいでしょう。
そこで、最高裁判所が立法裁量論による、すなわち、自らの価値判断を抑制し、法律の制定権限者である立法府に判断を委ねるという選択をすることの根拠はどこにあるのか問いたくなります。②の最高裁判所判決では、民法733条を定めた当時と比べ、今日では再婚をすることについての制約をできるだけ少なくすべきとの要請の高まりなどの社会的事情の変化や、諸外国の動向も参考にすると、100日を超過した期間の禁止部分については、国会に認められた合理的な立法裁量の範囲を超えたものだと説かれています。それでは、この立法裁量の範囲を超えていることを決定づける要因は、ルール化できるのでしょうか。
この関心をもって③の夫婦の氏の問題をみてみると、選択的夫婦別氏の採用を拒否することは、国会に認められた合理的な立法裁量の範囲を超えたものだといってもおかしくないように思えます。これに関わる考察は、すでに本欄の第13回で行っているので繰り返さないでおきます。ただ、テレビでの国会中継で、この問題に対する野党議員の質問に対して、安倍首相が、選択的夫婦別氏制度は、子どものためによろしくないと答えていたことには触れておきます。
子どものためという正当化の根拠は、実態をみつめているのか、そうであったら、④において問題とされている無戸籍の子どもを生じさせている法規定は、子どもを不幸にさせているので、矛盾しないのかという疑問が湧きます。どうも安倍首相は、夫婦や家族について、個人よりも、日本社会に浸透させたい理想像ないしイデオロギーを根底に置いているように思えます。
ここでは、そうした理想像・イデオロギーをめぐった論議の場とはしたくないのですが、最高裁判所が立法裁量の問題というときの立法府ないしその現実の行為については、少し説明をする必要があります。すなわち、上記の民法規定の改正内容を検討して、改正案を作成するのは、国会自体ではないという現実を知る必要があります。最終的には、国会が改正法を成立させるのですが、それに至る過程を見る必要があります。これについては、次回に取り上げることにします。
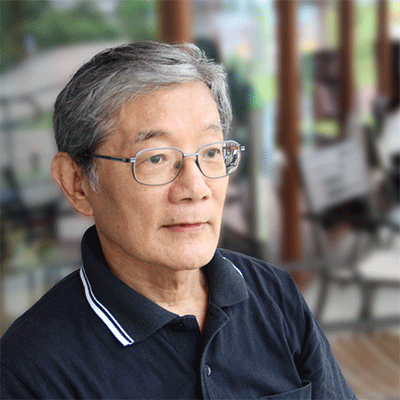 戸松 秀典 憲法学者。学習院大学名誉教授。
戸松 秀典 憲法学者。学習院大学名誉教授。
●著書等
『プレップ憲法(第4版)』(弘文堂、2016年)、『憲法』(弘文堂、2015年)、『論点体系 判例憲法1~3 ~裁判に憲法を活かすために~』(共編著、第一法規、2013年)、『憲法訴訟 第2版』(有斐閣、2008年)、『憲法判例(第8版)』(有斐閣、2018年)、など著書論文多数。
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?