2020年は日本からノーベル賞は出なかった。しかし、数学の超難問といわれる「ABC予想」を京都大学数理解析研究所の望月新一教授が証明したとされる論文が、ついに国際的な数学誌に掲載されることになった。京都大が20年4月3日発表した。
望月教授は12年8月にこの問題を解いたことを明らかにしていたが、論文を掲載する数学誌がなく、謎の証明となっていた。ノーベル賞に「数学部門」はないが、大手マスコミは、「ノーベル賞級」という専門家のコメントを報じていた。
BOOKウォッチでは、ABC予想を解説した加藤文元・東京工大教授の著書『宇宙と宇宙をつなぐ数学』(株式会社KADOKAWA)をすでに3月段階で紹介していた。「ABC予想」が長年、数学の学会掲載されなかったのは、「理論がとても難解で、論文掲載の事前審査が進まないから」ということのようだ。
さらにBOOKウォッチでは4月末、数学の未解決難問「リーマン予想」についても、『リーマン予想の今,そして解決への展望』(技術評論社)を取り上げた。難解な数式だらけの異例の書評となったが、今も根強いアクセスがある。
こうした超難問に挑むの「神童」と呼ばれた人たちだ。望月教授は米国育ち。プリンストン大学に16歳で入学し、19歳で卒業したという。日本の教育システムでは理解不能な経歴の人だ。
『神童は大人になってどうなったのか』(太田出版)は日本の伝説的な秀才たちのその後の人生をフォローしている。多数の神童が登場するが、その中でもずば抜けているのが、岡田康志さん。「神童ワールド」では知る人ぞ知る有名人らしい。1968年生まれ。灘中学3年のときには駿台予備校の東大実戦模試で最難関の理Ⅲ合格A判定。その後、同模試で高1のときに2番、高2で1番。現在は東大教授・理化学研究所生命システム研究センターのチームリーダーだという。
同書には戦前の日本の英才教育の話も出ていた。戦争末期の「特別科学組」だ。日本はアメリカに勝つために、新しい発明を期待できそうな少数の英才を集め、国内の5つの旧制中学などで特別な教育を施そうとした。1945年に一期生が入学した。京都府立京都第一中学にも特別科学組が設けられた。指導に関わっていたのが、若き湯川秀樹博士だ。
『湯川秀樹日記1945』(京都新聞出版センター)には、終戦目前の45年8月3日、「一中にて特別科学教育打ち合わせ」と、湯川がこの特別教育に関わっていたことを示す記述がある。加えて同書によれば、博士は「原爆研究」にも関係していた。いわゆる「F研究」だ。
2月3日の項に、「F研究相談」と記されている。6月23日にも「戦研 F研究 第一回打合せ会、物理学教室にて、荒勝、湯川、坂田、小林、木村、清水、堀場、佐々木、岡田、石黒、上田、萩原各研究員参集」と出席者の名前が列記されている。もちろん研究は進まなかった。そして戦争が終わり、9月15日には「米士官二名教室に来たので直ちに面会」と書き残されている。
なぜ、進駐直後の米軍が、京都在住の物理学者を訪ねたのか。実は米軍は早々と、戦争末期の日本の原爆研究を察知していた。その実情調査だった。10月4日と11月16日にも占領軍将校が来たことが記されている。湯川は取り調べだとは認識していなかったようだが、同書には「聴取」の詳細を記した米側の秘密報告も掲載されている。
戦前の湯川は、京都新聞に「科学者の使命/全ては戦力に/一擲せよ孤立主義」と寄稿していた。多くの日本の科学者たちと同じように、戦争推進に協力する立場だった。しかし、戦後は核廃絶・世界平和のために尽力した。
同書には極めてタイムリーな「解説」が付いている。その一つが、この9月まで京都大学総長を務めた山極壽一氏による「湯川日記が遺したもの」という一文だ。周知のように山極氏は日本学術会議の前会長でもある。
湯川の戦前の原爆研究への関与と、戦後の核兵器廃絶運動への積極的な活動を振り返りながら、山極氏は、「日本学術会議は発足当初から湯川と共に歩いてきた」と記す。たしかに1949年の学術会議創設の年に、湯川はノーベル賞を受賞している。さらに山極氏は学術会議が50年と67年には、戦争を目的とする科学の研究には絶対に従わない決意を表明し、昨年3月にもその表明を継承する提言をしたことも強調している。要するに学術会議は、湯川の戦前の悔悟と、戦後の平和への思いを継承しているということだろう。
本書は今年9月1日の刊行であり、菅義偉首相が、日本学術会議が推薦した会員候補のうち一部を任命しなかった問題はまだ起きていなかった。学術会議側が猛反発したのは周知の通り。本書では、「湯川秀樹」を通して、今日の学術会議の問題を考えるうえでの「原点」を再認識することができる。
学術会議の今回の問題では付随して、中国の「千人計画」の話なども一部で話題になった。中国が海外からハイレベルな研究者を招いている政策だ。すでに米国をはじめ世界各国から一流の研究者を招聘している。
BOOKウォッチでは昨年来、科学技術教育の分野における中国の「元気ぶり」と日本の立ち遅れについて多数の本を紹介してきた。
『科学立国の危機』(東洋経済新報社)は、日本がバブル経済崩壊のあと、大学、研究所の予算を絞り、研究者の数、研究費を事実上減らしてきたことが研究の停滞をもたらしていることを指摘していた。『大学改革の迷走』 (ちくま新書)は、日本で行われている様々な大学改革が成果を上げていないことを報告している。こうした日本の大学・大学院教育の現状に見切りをつけ、海外に活動の場を求める研究者も増えていることは、『海外で研究者になる――就活と仕事事情』(中公新書)からもうかがえる。同書は一時、東大生協書籍部のベストセラーになっていた。
かつてアジアのナンバーワン大学といえば東大だった。ところが最近、国際的な大学ランキング調査だと、中国やシンガポール、香港の大学が上にいる。今やアジアのトップ大学は、習近平の出身校、中国・清華大学などであり、東大は5、6位あたり、調査によっては韓国の大学にも抜かれて10位前後にまで落ちている。
米国の大学院に留学する日本人の数は中国の足元にも及ばず、『科学立国の危機』によれば、人口100万人当たりの論文数では、すでに韓国の半分以下に落ち込んでいる。『海外で研究者になる』によれば、中国最大の研究所、中国科学院は約6万人が所属しているが、会議は中国人同士でも基本的に英語だという。
『大学はもう死んでいる? トップユニバーシティーからの問題提起』(集英社新書)はオックスフォード大で教える日本人教授と東大の先生が徹底討論し、なぜ日本の大学改革は失敗するのか、問題の根幹に迫る、という内容だ。
中国が「千人計画」のみならず、「ウミガメ作戦」と称し、海外にいる中国人研究者の呼び戻しにも熱心なことはよく知られている。科学技術振興に対し、政府が明確な戦略を持ち、カネもかけているのが中国だ。
一方で、日本の科学技術教育、大学教育の現状を冷静に見つめると、「立ち遅れ」による影響が多方面に及んでいることがわかる。
『貧乏国ニッポン』(幻冬舎)によれば、日本はすでに「貧乏国」に転落している。これからもっと大変になるかもしれない、コロナ禍は序章に過ぎないと手厳しい内容だった。なにしろ、日本人の実質賃金は過去30年間、ほとんど上昇していない。日本以外の先進国は1.3倍から1.5倍になっている。例えばスウェーデンは賃金が2.7倍になって、物価は1.7倍。日本は賃金が横ばいで、物価は1.1倍。その理由は簡単だ。「日本は国力が大幅に低下し、国際的な競争力を失っており、その結果が賃金にも反映されている」と様々な統計をもとに断言していた。
著者の加谷珪一さんは経済評論家。同書の後継に当たる『日本は小国になるが、それは絶望ではない』(株式会社KADOKAWA)では今後、少子化によって日本の人口が急減すること、それはGNPの減少にも直結し、新たな国家像を構築する必要があることを強調していた。一言でいえば、日本と日本人は生産性を高めるしかないということであり、そのためには教育重視が不可欠というわけだ。
同書には、「高等教育機関への25歳以上の入学者比率」の一覧表が出ていた。日本はわずか2.5%だ。スイス、イスラエル、アイスランド、デンマーク、ニュージーランド、スウェーデンなどは25%を超えている。いずれも大学院レベルの研究や、社会人の再教育に力を入れている。対する日本は・・・政府の学術・教育への取り組みは、「教育重視」で国力を維持しようとする世界の潮流から大きく遅れている。
なお「学術会議」に関連して日経新聞に極めて興味深い記事がいくつか掲載されていることを注記しておきたい。
一つは10月10日の「上皇ご夫妻 長引く外出自粛」という記事だ。「歴史談議が好きなご夫妻は、在位中は歴史家の半藤一利、保阪正康、加藤陽子の3氏を頻繁に御所に招かれていた」とあった。東大教授の加藤氏は日本近現代史が専門。平成の天皇皇后と親しく懇談する間柄だったというのだ。首相官邸は当然そうした事実を承知しつつ、今回、加藤氏を任命しなかったということになるのではないか。
天皇家は学術と深いつながりがあるということは、BOOKウォッチで『教養としての歴史問題』(東洋経済新報社)を取り上げる中で指摘済みだ。今の天皇は水運史の研究者でもある。皇太子時代の著書『水運史から世界の水へ』(NHK出版、2019年4月刊)の巻末参考資料一覧には、体制寄りとは言えない歴史学者、網野善彦氏の著書『海と列島の中世』も入っている。
11月末の日経新聞にも注目すべき複数の記事が掲載されていた。一つは新型コロナに関する論文数が、日本は世界16位と大きく立ち遅れていること。トップの米国や2位の中国とは絶対数で大差がある。「コロナ禍は日本の科学研究の危機も浮き彫りにした」というわけだ。寄稿者の浜口道成・科学技術振興機構理事長は、この順位について「日本の大学・科学技術政策の帰結」ととらえている。要するに長年の予算削減の結果だというのだ。
もう一つは「研究者の中国流出続く」という記事。中国で研究する日本人は増え続け、2017年10月時点で約8000人。「日本での待遇に問題がある」「国内の大学などでは研究ポストが見つかりにくい」という事情が背景にあり、「人材流出を止めるとすれば、研究環境の改善が急務だ」と指摘されていた。
政府がやるべきことは、学術会議の内部に手を突っ込み、人事に介入することではない、ということが透けて見えてくる。必要なのは、中国以上の強力な科学技術政策を打ち出し、それを予算面で確保することではないか。現状では、無為無策のまま、日本は「小国」への道を転げ落ちていくことになりかねないと感じた。
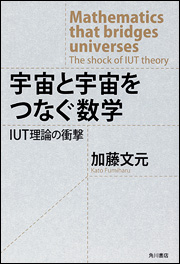
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?