今年も吉野彰・旭化成名誉フェローがノーベル化学賞を受賞した。自然科学部門のノーベル賞受賞者は21世紀に入ってからだけでも18人目。日本の科学研究は絶好調と思いたいところだが、これらは昔の遺産で、現在の日本の研究体制は危機に瀕しているようなのだ。
本書『科学立国の危機』(東洋経済新報社)は、そうした実態を憂え、体制を立て直すにはどうしたらいいのかと探ってきた元三重大学長の豊田長康・鈴鹿医療科学大学長の渾身の書だ。読んで面白い本ではない。むしろ、いらいらし、だんだん恐ろしくなってくるかもしれないが、文科省や政府関係者には、ぜひとも読んでいただきたい本だ。
著者の憂いは、杞憂ではない。たとえば、国の政策を研究することを大学の目的にしている政策研究大学院大学が2019年12月26日に開くシンポジウムのタイトルは、「我が国科学技術の失速の原因と復活の処方箋」――日本の研究力の失速は周知の事実なのだ。
人口100万人当たりの論文数の推移というグラフを見ると、多くの国が1990年以降一貫して右肩上がりなのに、日本は今世紀に入って横ばいかやや下落している。この結果、自然科学部門のノーベル賞受賞者がいまだゼロの韓国にすら、10年くらい前に追い越され、理工系、計算機科学、社会・心理系の分野では、3年前の時点で2倍近くも引き離されている。
論文の数の多寡やノーベル賞などは、われわれ衆生には関係ないと思われる向きもいるかもしれない。しかし、そうではない。特許数は論文数の数に比例するし、人口当たりの論文数は数年後の人口当たりGDP(国内総生産)ときれいな比例関係にあることも分かっているのだ。
日本は、バブル経済崩壊のあと、大学、研究所の予算を絞り、研究者の数、研究費を事実上減らしてきた。さらに、限られた研究費を効率的に使おうと、大部分の大学や研究所の予算をじりじり減らし、浮いた予算を特定の大学や研究所に集中配分している。「選択と集中」政策だ。
著者はそれが誤りだったと指摘している。予算を多く配分したからといって、論文数はそれに比例して増えるわけではない。効率が逓減するからだ。一方、なけなしの人や研究費を減らされた側は、論文どころではなくなる――こうした話は、かなり前から大学や研究者の間で語られてきた嘆きだ。
本書が凄いのは、これらの、いわば常識論を、膨大なデータをもとに分析し、これでもかこれでもかとグラフや表で示して説得力を持たせていることだ。
人口が減り、高齢者が増えている日本。今のままでは、早晩、世界第3位の経済大国の座も明け渡さざるを得ない。それでも、現在のドイツやフランスのように人口に見合った安定した国家に軟着陸できるなら、結構いい国になるかもしれないと、評者などは期待してもいた。
しかし、残念ながら、今のままでは、日本はそういう国になれそうにない。早急に、国の科学技術政策を改めて欲しいのだが、不祥事続きの文科省の体たらくを思い出して、ますます気が重くなるのだ。
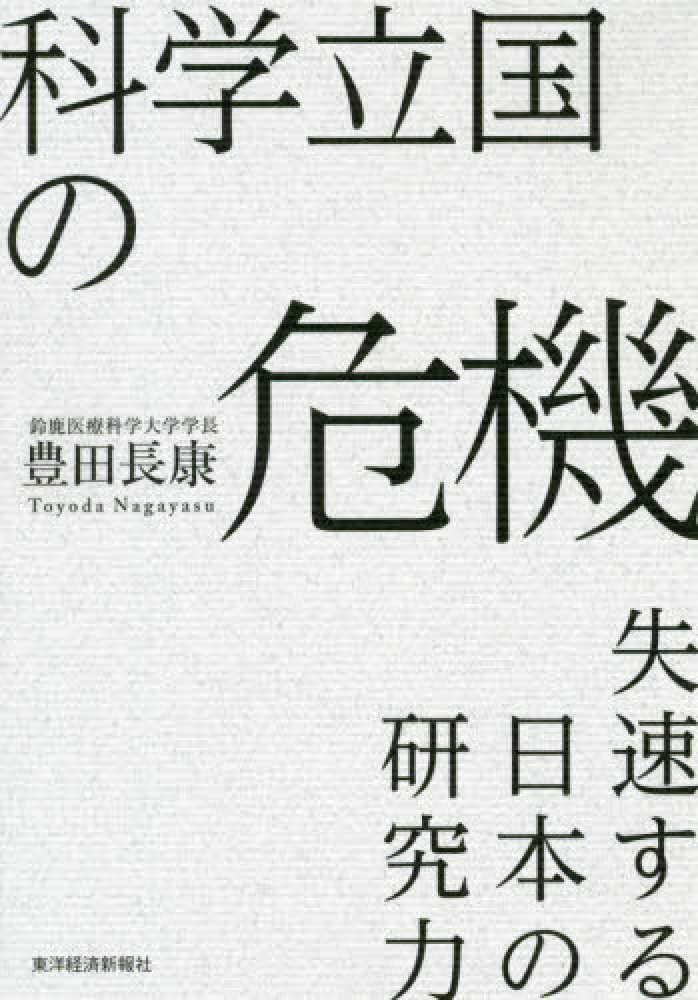
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?