数学の未解決問題「ABC予想」が解かれた。論文の発表者は京都大の望月新一教授(1969年生まれ)。7年半前、2012年8月のことだ。しかし、いまだにその論文を掲載する数学誌は出ていない(文末に追記有り)。謎の証明だと言える状況だ。どうなってしまったのか。そう思っている人もきっといるだろう。
証明には望月教授の創った新しい数学手法が用いられている。「宇宙際タイヒミュラー理論」(Inter-Universal-Teichmuller theory=IUT理論)。本書『宇宙と宇宙をつなぐ数学』(株式会社KADOKAWA)は、IUT理論とそれを使ったABC予想解決の一般向け紹介書だ。
著者は、加藤文元さん(東京工大教授)。加藤さんは望月教授と学んだ大学が異なるが同学年だ。IUT理論完成までの最終6年間にかかわり、両者で月1、2回程度、セミナーを開いた経験を持つ。同理論の一般向け紹介者としては格好の人物だと言っていい。
学会誌掲載が実現しないのは、IUT理論がとても難解だからだ。論文掲載の事前審査が進まないのだそうだ。加えて加藤さんが本書を書いたのは、誤解が数学界に広がっていることへの懸念もあった。
望月教授は「トップクラスの学者でも理解するのに長時間を要する」と見ていて、学界の理解を広げるのにさして熱心ではないとされる。下手をすると確認されないまま忘れ去られる恐れもある状況だと言えるかもしれない。2004年のド・ブランジュによる「リーマン予想解決」のようにほとんど放置されている先例もある。
数学の未解決問題では「ヒルベルトの23の問題」と「ミレニアム懸賞問題」がよく知られている。「連続体仮説」や「ポアンカレ予想」(いずれも解決済み)はその一つだ。解決される度に大きなニュースになった。一方、ABC予想は広く報道されたものの一般にはなじみが薄い。テーマ化したのが1985年と新しいためだ。
ではABC予想とはどんなものなのか。式の意味ならば中学生でも分かるものだ。
自然数aとbが互いに素であるとき、aとbの和をcとする(a+b=c)。これを「ABCトリプル」と呼ぶ。このABCトリプルの積(a・b・c=D)を取ったときのDの根基(こんき=ラディカル)をdとすると、dとcとの大小比較で現れる事態についての予想が、ABC予想だ。
根基は聞き慣れない用語だが、Dの場合、互いに異なる素因数を、2乗、3乗などダブりをすべてなくした上で乗じた積dのことだ。「rad D」と書く。例えば、Dが36の時はrad 36=2^2×3^3→2×3=6("^"はべきを表す)となる。逆に根基が6となる元の数は、6や12、18......など無限個ある。
ここでcとdの大小関係は、c < dとなるのが普通だ。しかしc ≻ d になることも例外的にある。この例外は無限個あるが、「d を累乗して少し大きくすることで有限個にできるだろう」とABC予想は考える。つまり、c ≻ d^(1+ε)(ε=イプシロンは正の小さな実数)だ。
数学の門外漢には、このような予想がどれほど重要なのか、と映るかもしれない。実はこれが解決すると、さまざまな数学の難問が解けてしまう、と言う。A・ワイルズが別の方法で解決した「フェルマーの最終定理」(「Aのn乗+Bのn乗=Cのn乗」を満たす3以上の自然数nはない)をはじめ、「モーデル予想」「トゥエ=ジーゲル=ロスの定理」「エルデシュ=ウッズ予想」など数多い。大変な威力を持つ予想なのだ。
本書で加藤さんは、望月教授の来歴や加藤さんとのかかわり、同予想を取り巻く状況を紹介。その後でIUT理論を概観し、これを適用したABC予想解決への道筋を示す。
加藤さんが最初に指摘するのは、予想(a+b≻ d)の左辺が和の計算であるのに対して右辺( d)がかけ算であることだ。数学は足し算とかけ算が強固に絡まり合っている。積を取ると必ず足し算が付いてくる複素数などは、典型なのかもしれない。だが自然数では2つを切り離して、足し算を固定、かけ算だけ伸び縮みさせてみよう、と言う。この切り離すというのがIUT理論のアイデアだ。
素数の積をめぐっては、こんなことが言えるかもしれない。つまり、自然数の定義だ。1に1を足していって作られたものだとする「ペアノの公理」がよく知られる。足し算による定義だ。一方、かけ算でも定義できる。自然数はすべて素数の積に分解できるので、それをすべて作って小さい順に並べる方法だ(ただし1は素数の0乗)。数をそんなふうに見ると、足し算とかけ算は独立していて分離できるかもしれないと思えてくる。
加藤さんの説明を掻い摘んでIUT理論を紹介するとこうだ。
・異なる数学の舞台(IUT理論ではuniverses、加藤さんの比喩では、足し算、かけ算が切り離されてかけ算だけを伸び縮みさせた世界)を設定。現実世界に計算者がいて、そこにテレビがあって画面の中に同じ計算者がいる。ただし2つの計算者は同じだが掛けられる制約が異なっている――というふうに舞台は現実世界も含めて入れ子式になっている ・計算の群論的対称性(計算方法のレシピ)を、各計算者に計算の対象や計算方法を伝達 ・受信した対称性を基に、それぞれの舞台で元の計算の対象や計算方法を復元。計算を実行する ・対称性の通信や復元で生じる不定性・ひずみ、つまり計算結果のサイズの違いを定量的に評価して不等式を導く
ではABC予想はどうか。予想の主張である「c ≻d^(1+ε)」。これのIUT理論での「deg Θ≦deg q+c」への帰結を目指す。
評者のような文系出身者に「deg 」は無縁だったが、次数(デグ)を表す記号だ。ここではdeg Θ(デグ・テータ)が現実舞台での計算結果、deg qはかけ算を伸縮させた舞台での計算結果となる。右辺に加えられているcは、ABC予想のcとは別物で、ひずみの定量的評価で求められた小さな値だ。IUT理論によるABC予想は、現実舞台での累乗数が、かけ算伸縮舞台での累乗数よりも小さいことに帰結させたい訳だ。
いよいよ本論。加藤さんはここで、これまで「かけ算を伸び縮みさせた舞台」と呼んでいたものを示す。その舞台とは、現実舞台の「q」を伸縮舞台での「qのn乗」に対応させたものだ。これはLogを用いると、「N Log q≒Log q」(両項を結ぶのは近似であることに注意)と表される。Log(けた数)と先に出てきたdegの違いは、ここでの理解の上では考えなくてよいそうだ。同じようなものと考えていい。
数式の流れで表すと、こうなる。
N Log q<Log q+c(N Log q≒Log qだから、正の数値を加えると「<」になる) →deg Θ≦deg q+c →deg qは小さい、つまりc ≻ d^(1+ε)のεは小さい
となって証明は完成する、という。
なんだか、値が確定しないまま議論が進められていくような、キツネにつままれたような印象を持つ流れだ。それも、本書に収められている望月教授本人による寄稿を読めばある程度解消する。
「数学は曖昧さを許さない体系だと思っている人が多いかもしれないが、実はそうではない」として、曖昧さは以前から取り入れられている、と言う。
所望の値の追求をあきらめて極限を取ったり、不等号で追い込んだりするではないか、と。また物理学では、相対性理論によると大域的に見れば時空の幾何が曲がっている。その中にある固定されたユークリッド空間(平面の高次元版)は局所的な近似としての構造だ。また量子力学では、必然的かつ内在的な不確定性を抱えている。
つまりは、ひずみを抱えていても、そのひずみ定量的に評価できれば合理的である、ということだ。「未来からの論文」とも称されるIUT理論のキモは定量的評価だったのだ。
本書は、ぼんやりと読むと1日、2日で読了する。分かりやすく書かれた本だという印象だ。しかし、読み返すうちに、緻密に張られた伏線に気づくだろう。例えば、「遠アーベル幾何学」や「楕円曲線」など数学専攻者でも難解な分野の知識も、IUT理論の理解には必要なのだと思い知らされることになる。ただそれらを体系的に組み上げてIUT理論に臨むことは困難でも、それぞれをトピックとして立ち寄るだけで、十分に面白い。
複数の舞台に情報=対称性を伝達するのに使う群論についての加藤さんの解説は、特に分かりやすかった。群論は「行為の算術」であるという群論の哲学と、その技術論を分けて紹介している。群論では形は伝えられても大きさは伝えられないという特質も透けて見える。群論を学びたい人にもおすすめだ。
文系だが、難解な数学にも挑戦してみたいと思っている読者は少なくないだろう。そんな一人として、多少なりとも参考になればと思って紹介した次第だ。
加藤さんの著書には『ガロア―天才数学者の生涯』(中公新書)、『数学の想像力: 正しさの深層に何があるのか』(筑摩選書)、『物語 数学の歴史―正しさへの挑戦』(中公新書)などがある。また、BOOKウォッチでは数学関連で『完全版 天才ガロアの発想力』(技術評論社)、『クロード・シャノン 情報時代を発明した男』(筑摩書房)、『虚数はなぜ人を惑わせるのか』(朝日新書)などを紹介済み。
2020年4月3日追記 数学の超難問といわれる「ABC予想」を京都大学数理解析研究所の望月新一教授(51)が証明したとされる論文が、ついに国際的な数学誌に掲載されることになった。京都大が2020年4月3日に発表した。
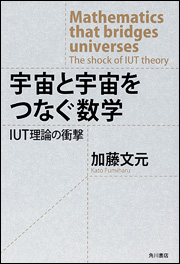
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?