最近でこそやや沈静化したが、何かの機会にしばしば論議になる。南京事件の虐殺は本当にあったのか、あったとしたら犠牲者はいったいどれくらいだったのか。本書『増補 南京事件論争史』(平凡社)は、この事件についての近年の様々な議論を中国現代史の研究者、笠原十九司・都留文科大名誉教授が丹念にトレースしたものだ。2007年に刊行された原著に、最近の10年分を付け加えて、このたび「増補版」が出た。
「一九三七年一二月、南京市を占領した日本軍は、敗残・投降した中国軍兵士と捕虜、一般市民を殺戮・暴行し、おびただしい数の犠牲者を出した。この『南京事件』は当時の資料からもわかる明白な史実であるにもかかわらず、日本では否定派の存在によって『論争』がつづけられてきた。事件発生時から現在までの経過を丹念にたどることで、否定派の論拠の問題点とトリックを衝き、『論争』を生む日本人の歴史認識を問う」
これが「原著」での著者の基本姿勢である。「増補版」ではさらに、「不毛で熾烈な論争が繰り返されてきた」と、いちだんとオクターブが上がっている。このくだりを見ただけで賛成の読者は快哉し、反対の読者はおそらく唾を吐くことになるのだろう。
こうした事柄についてネットで調べると、さまざまな見解が対立し、何が本当なのかわからなくなることがある。それは、専門外の「半可通」が書き込みに参画しているからだ。ウィキペディアなどでも、正体不明の、誰だかわからない筆者が、自分好みの見方を客観的事実かのように書いていて、読みながら気になることが少なくない。
似た傾向は、専門外の有名人が歴史を語るときも付きまとうようだ。最近、作家の百田尚樹氏による『日本国紀』(幻冬舎)がベストセラーになっているが、『応仁の乱』を書いた歴史学者の呉座勇一氏が朝日新聞のコラムで、「学界の通説と作家の思いつきを同列に並べるのはやめてほしい」と苦言を呈して話題になった。
本書は、専門の学者によるものなので、立場の問題はさておき、論争のもとになっている史料や、関係者の証言などについては、アカデミズムの中で承認される手法で扱われていると推認できる。著者は「まえがき」で南京事件論争をめぐる混迷をおおむね次のように分析している。
・通常の学問論争や歴史論争とは性格も様相も異なった、きわめて特殊な論争である。 ・事件が史実であることは学問的には決着しているが、世間一般では「論争は継続中」と受け取られている。 ・それは南京事件が、日中戦争を否定的にとらえるか、肯定的に見るかという日本人の戦争認識のカギを握る象徴的な事件になっているからである。 ・一方、中国では日本の中国侵略を象徴する虐殺事件と見なされ、学問的な問題を超えた政治問題、外交問題にもなっている。 ・さらに日本国内では、南京事件を否定する右翼政治勢力が言論報道抑圧行動をとることにより、自由な学問論争が阻害されている。学校教育でも、南京事件を教えることがタブー視される傾向が助長されている。
つまり、本来は「学問」レベルで処理されねばならない論争が、「政治」になっているということだ。複雑化の背景には、日中双方の「政治」が絡んでいるということになる。
本書は、第一章「『論争』前史」、第二章「東京裁判」、第三章「一九七〇年代」、第四章「一九八〇年代」、第五章「一九九〇年代前半」、第六章「一九九〇年代後半」、第七章「二〇〇七年」、第八章「二〇一〇年代前半」、第九章「二〇一〇年代後半」と年代を追って論争史をフォローし、「おわりに」で、「日本の首相が南京を訪れることを望む」と締めくくる。そして近く出版する『決定版 南京事件の検証』が論争の終止符になると予告している。
本書は戦前の言論統制の話から始まる。南京事件に対する徹底した報道規制、出版弾圧、証拠の隠滅・・・。こうした戦前の統制の厳しさについては本欄でも、『空気の検閲 大日本帝国の表現規制』(光文社新書)、『大本営発表 改竄・隠蔽・捏造の太平洋戦争』(幻冬舎新書)、『たたかう映画』(岩波新書)、『幻の雑誌が語る戦争』(青土社)などで紹介済みなので、おおむね推測が付く。
戦後も長く、余り報じられなかった南京事件。評者自身はかつて偶然、「事件を見た」という元日本軍兵士からリアルな体験談を聞いたことがある。したがって、事件はあったという立場であることを告げておきたい。その証言者は政治的にはまったく無色の人であった。内容はあまりにも具体的かつ凄惨なのでここで書くのは避けたい。この元兵士は「『見た』と言っているが、本当は『やった』のでは」とも思ったが、私的な会話の中で出た回顧談であり、それ以上は聞けなかった。
ちなみに先の百田氏の『日本国紀』でも南京事件は取り上げられている。「三十万人の大虐殺」が起きたという話があるが、これはフィクションであるとし、「日本と日本人の名誉に関わることであるから、やや紙幅を割いて書いておく」と前置きして論及し、<客観的に見れば、「『南京大虐殺』はなかった」と考えるのがきわめて自然である>と結論づけている。
しかしながら、南京事件があったという証言は多い。野中広務・元官房長官は、「虐殺者30万人」には同意していないが、著書『差別と日本人』(株式会社KADOKAWA)の中で、まだ日中国交正常化の前に最初の訪中をしたときのことを書いている。同行した後援者の1人が南京の雑踏で倒れて起き上がれなくなった。聞けば彼は、南京事変に参加していたという。「上官の命令に逆らえず、何の罪もない女性や子ども百数十人を殺した。その忌まわしい記憶が現地で甦り、倒れてしまったのだ」と書いている。
亡くなった三笠宮さまも『古代オリエント史と私』(学生社)の中で、支那派遣軍参謀として南京総司令部に赴任当時、「日本軍の残虐行為を知らされました」と書き残している。
日本軍が中国で行った「重大な汚点」(第二遣支艦隊参謀の証言)については、研究者による『三竈島事件―― 日中戦争下の虐殺と沖縄移民』(現代書館)にも詳しい。こちらは南京ではなく、香港の近くの「三竈島」の話だ。小澤征爾氏の兄で、中国で育った筑波大学名誉教授の俊夫さんも、『日本を見つめる』(小澤昔ばなし研究所)の中で現地の日本軍兵士が自慢げに語っていた残虐行為について触れている。
外務省のホームページでは南京事件についてこう記されている。
「日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています」
異常な状況下では平時と異なることが起きることは1923年、関東大震災での朝鮮人虐殺の前例がある。本欄でも『証言集 関東大震災の直後 朝鮮人と日本人』 (ちくま文庫)や『九月、東京の路上で――1923年関東大震災ジェノサイドの残響』(ころから)、吉村昭氏の労作『関東大震災』(文春文庫)などを紹介した。当時の日本人の朝鮮(人)や中国(人)に対する微妙な心理状態も含めて、なぜ事件がおきたか、克明に報告されているので参考になる。関東大震災から南京事件までは14年しかたっていない。
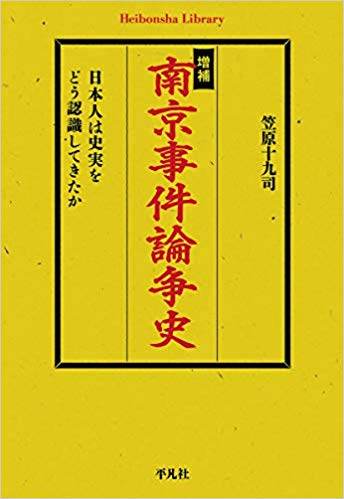
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?