映画監督には、自分自身も数奇なドラマの主人公のような人が少なくない。その代表例が、イタリアの映画監督、ピエル・パオロ・パゾリーニ(1922~75)だ。「アポロンの地獄(67年)、「テオレマ (68年)」、「豚小屋(69年)」などの問題作で世界的にセンセーションを巻き起こしたが、75年、「ソドムの市」の撮影終了直後に、惨殺死体で発見された。
本書『パゾリーニの生と<死>』(ミッドナイトプレス)はパゾリーニの全映像作品を丹念に読み解き、彼の思想と生涯に迫ったものだ。著者の兼子利光さんは1954年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。ヴィスコンティからダリオ・アルジェントまでのイタリア映画と、ホラー、B級映画の研究者。雑誌「アエラ」の校閲者を長く務めた。
「わたしにとってパゾリーニの映画作品は長い間、カフカの『変身』の主人公がある朝、目覚めたとき感じた『気がかりな夢』のようなものだった。その『気がかりな夢』に少しでもかたちを与えようと試みたのが、このパゾリーニについての考察である」
兼子さんはパゾリーニにとりつかれた理由をそう語る。「惨殺死という衝撃的な死で閉じた生涯を、その際立つ個性の、外からは窺い知れない心の底のほうから特徴づけるものは何か」という視点で分析する。
パゾリーニは、回り道をして映画監督になった人だ。軍人でファシストの父には反発し、学校教師で慈愛に満ちた母を敬愛して育った。7歳から詩を書いていた。やがてドイツ軍は北イタリアで攻勢を強め、対抗するパルチザン闘争も激しさを増す。3歳年下の弟はそのパルチザンに加わったが、内部抗争で殺される。19歳だった。
戦後のパゾリーニは学校教師をしながら文学活動。そして共産党に入党し、地域の農民闘争にも関わる。ところが、「未成年者への淫行」の疑いで告発され、党から除名。やがて創作活動に比重を移し、詩人、作家として名を成す。映画の脚本も手掛けて、自ら監督もするようになる。
61年に処女作「アッカトーネ」を発表。ローマ郊外の下層プロレタリアートの日常をテーマにしたものだった。その前年に公開されたフェリーニの「甘い生活」は、50年代後半のローマの豪奢で退廃的な上流階級の生態を描いたが、「アッカトーネ」は、「もう一つのイタリア」を赤裸々に映像化した。いわば当時のイタリアの「光と陰」だ。公開時にはネオ・ファシストによる妨害を受けている。
本書は「第一章 下層プロレタリアートと<郊外>」、「第二章 キリストとマルクス主義」、「第三章 消費資本主義の<定理>」、「第四章 マリア・カラスと生の三部作」、「第五章 消費社会のなかの『死』」という構成。
パゾリーニが映画の世界に足を踏み入れた50年代後半から、イタリアは「ネオ・カピタリズモ」(新資本主義)によって経済発展を続けていた。南部の農業地帯から、北部の工業地帯に農業労働者が職を求めて押し寄せる。「経済の奇跡」が都市部に大量のプチ・ブル層を生み出し、イタリアを消費社会に変えていた。パゾリーニは、この消費社会を画一的で抑圧的なものの到来ととらえていた。
「ファシズムが完全には達成できなかったあの文化の強制、あの同一化を今日の権力、つまり消費文明の権力は、多様で個別的な現実を破壊しながら、完全に達成しつつある」(カルロ・ルカレッリ『イタリアの新しい謎』より)
兼子さんは、消費社会の<現在>に対する思想的な拒否の意思表明が「テオレマ」「豚小屋」といった作品で表現されていったと解釈する。それらは<現在>に対峙するパゾリーニの思想的な映画、だというわけだ。
パゾリーニは、「罪を贖われたブルジョアはその持っている権利のすべてを放棄すべきだ。そして、これを最後に権力の観念を魂から追放すべきである」と宣言する。兼子さんによれば、60年代後半に高揚した学生運動の思想と行動にも抜きがたくあったプチ・ブル的な<権力の観念>をパゾリーニが鋭敏に感じ取り、それを的確に批判したものだという。「これは人間の存在の根源に向けて問いかけられた倫理的な言葉ではないかと、わたしは考える」と記している。
パゾリーニが無残な姿で見つかったのは75年11月2日。犯人として17歳の少年、ピーノ・ペロージが捕まったが、事件は謎に満ちていた。遺体は激しい暴行を受けていた。はたして、ひ弱に見える少年が一人でやれるものなのか。しかも少年はほとんどケガをしていなかった。パゾリーニは血だらけだったが、少年の服や身体には一滴の血も付いていなかった。
少年はパゾリーニとは旧知であり、カネのために売春をしている同性愛者だった。事件は世界的な映画監督に絡む大スキャンダルとなり、パゾリーニは被害者にも関わらず、社会的に指弾される。
当時のイタリアは、ネオ・ファシストのテロが頻発していた。一方では「赤い旅団」によるアルファ・ロメオ社長や検事誘拐なども起きていた。パゾリーニが殺された75年というのは、そうした極右、極左の過激な活動がピークに達していたときだった。
犯人とされた少年は刑期を終え、事件から30年が過ぎたころから、新たな証言を始める。「俺を脅していた男たち、家族を脅していた男たちは年老いたか、死んでしまった」ということがきっかけだ。新証言によると、パゾリーニの車に乗った少年の前に複数の男が現れ「コミュニストの、ホモ野郎」と口走りながらパゾリーニに襲い掛かったのだという。08年の証言では、男は5人。うち2人は知っている男。ネオ・ファシストの活動家ですでに死亡しているという。他の3人は知らない男だった。「いまでは、すべての責任を自分が負ったことに後悔している」。
パゾリーニは死の数時間前にジャーナリストのインタビューを受けて、身に迫る危機を予言していた。「我々がここで話している間にも、誰かが地下室で我々を片付ける計画を立てているとしたら、すごいことじゃないか」と。
兼子さんは「パゾリーニの死じたいはパゾリーニには属さない・・・パゾリーニの死は、<社会>に属するものだ」と結論づけている。
本書では、パゾリーニの残した詩も、兼子さんの手で翻訳されている。著者にとりついたパゾリーニへの、渾身のオマージュともいうべき一冊だ。

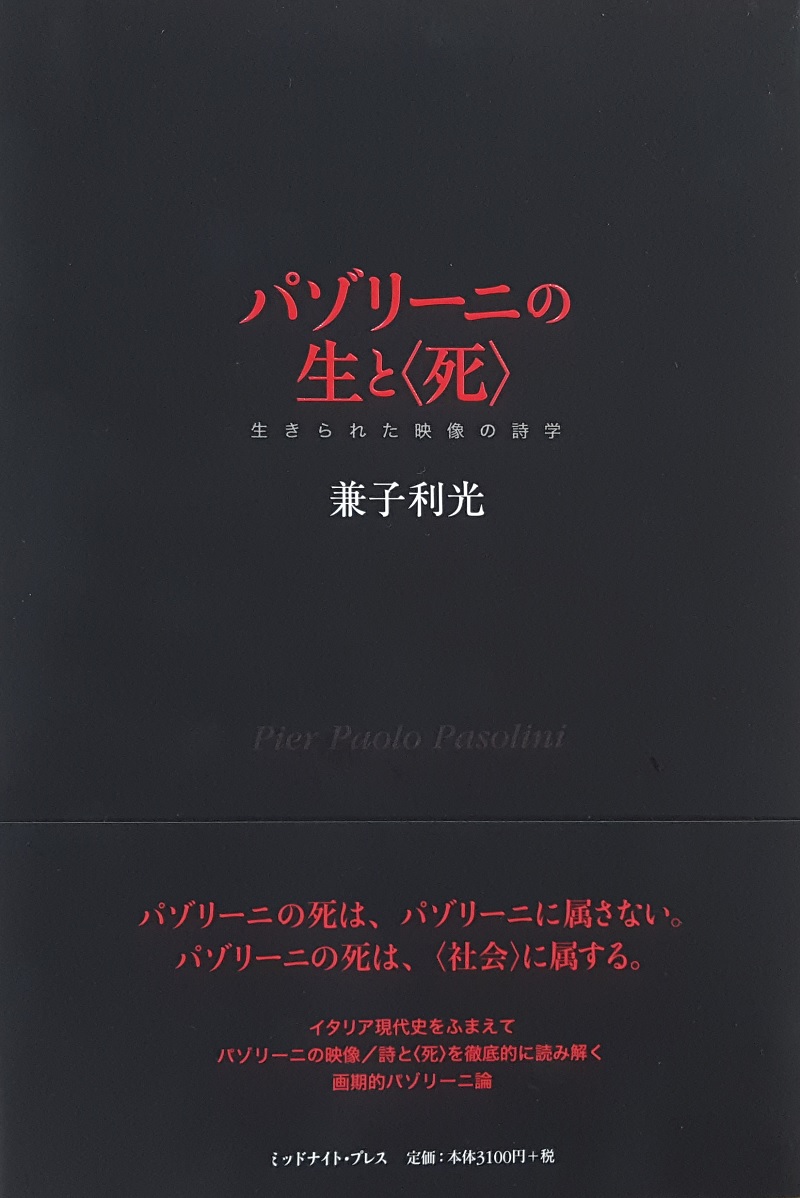
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?