世界最高峰のオーケストラとされる、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団は、創設から一貫して経営母体を持たず、演奏家たち自身が運営している。本書『ウィーン・フィルの哲学』(NHK出版新書)は、彼らが後ろ盾なしに伝統を守ってきた秘密に迫っている。クラシックファンにお勧めしたい本である。
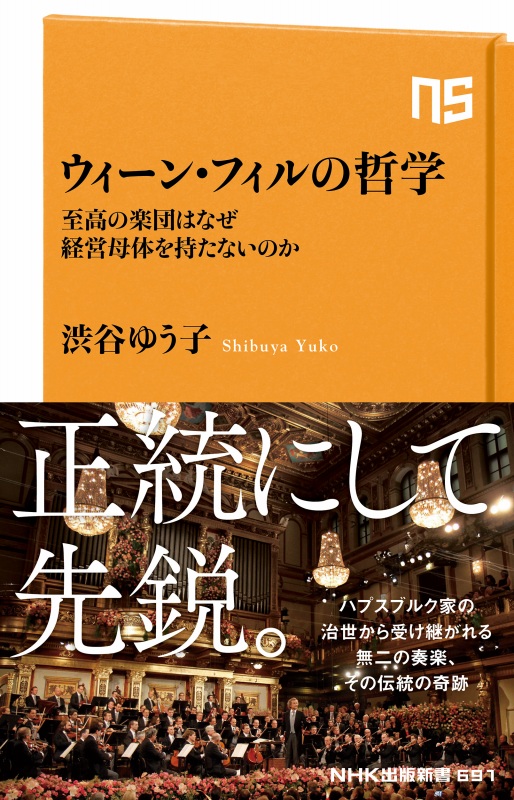
著者の渋谷ゆう子さんは、音楽プロデューサー、文筆家。株式会社ノモス代表取締役として、海外オーケストラをはじめとするクラシック音楽の音源制作やコンサート企画運営を行っている。同時にウィーン・フィルなどに密着し、取材を続けている。
ウィーン・フィルは、1842年にオーストリア帝国で生まれた、ウィーン宮廷歌劇場管弦楽団(現ウィーン国立歌劇場管弦楽団)の奏者で構成されたオーケストラである。その運営と経営を演奏家たち自身が行っていることはあまり知られていない。
彼らはそれぞれが個人事業主としてオーケストラを組織する自主運営団体である。その歴史を振り返りながら、独自の運営手法について詳しく説明している。
本書の構成は以下の通り。
第1章 音楽界のファーストペンギン 第2章 ウィーン・フィルとは何者か? 第3章 ウィーン音楽文化と自主運営の歴史 第4章 戦争が落とした影 第5章 王たちの民主主義 第6章 アート・マネジメントの先駆として
コロナ禍の下、ウィーン・フィルがどう動いたかを冒頭、取り上げている。2020年3月、ヨーロッパ各国で感染が急速に拡大。欧州ツアーを中止して帰国した。オーストリアは厳しいロックダウンに入り、全ての楽団員が自宅待機を余儀なくされた。
ウィーン・フィルは独自に飛沫拡散実験(エアロゾル実験)を行い、政府高官と直接交渉し、観客の人数など制限はあるにせよ、これまでどおり公演する許可を得た。2020年6月5日、100人の観客数を上限に屋内コンサートを行った。11月には「バブル方式」で来日公演を実施した。そこには「自分たちの音楽を届けたい」という純粋な思いだけではなく、圧倒的な交渉力と実行力があった、と渋谷さんは感嘆している。
ウィーン・フィルの奏者は全員「ウィーン国立歌劇場管弦楽団員」である。日々開催されるオペラ演奏で生活のための収入は確保しながら、ウィーン・フィルで演奏することで音楽的欲求を満たし、さらに高いギャラを稼ぐことができる仕組みである。
日本では通説として、「国立歌劇場奏者である公務員が休暇を申請して、その休日を使ってウィーン・フィルで演奏している」と言われることもあるが、誤りだとしている。
国立歌劇場は国の管理化で民営化された組織であり、楽団員は公務員ではなく、民営化された歌劇場に雇用されたオーケストラの一員だという。
ウィーン・フィルそのものは、非営利団体の協会で、現在147人の正会員(奏者)全員が運営に参加し、収益が配分されている。1933年以降、常任指揮者を立てず、オーケストラがコンサートごとに指揮者を選ぶ方式を採用しており、音楽的観点からもオーケストラ自身で全責任を負っている。
日常の実務を担うのは12人の運営委員で楽団長がトップで、事務局長が補佐する。指揮者とのコンタクト、コンサートやツアー日程の調整や、プログラムの組み立てなどの実務のほか、指揮者の送迎などマネージャーのような仕事もしているという。
ウィーン・フィルの奏者になるには、まずウィーン国立歌劇場管弦楽団員のオーディションを受け、国立歌劇場管弦楽団員にならなければならない。国立歌劇場管弦楽団員になっても欠員が出なければウィーン・フィル奏者になるオーディションもないので、その機会は非常に限られている。
奏者は1997年まで正会員は全員男性で、ウィーンで音楽を学んだオーストリア人がほとんどを占める、同質性の高い集団だった。ウィンナーワルツに代表されるオーストリア独特の音楽感覚が求められたのもその一因だという。また、女性奏者を採用すれば、出産育児休暇で何年も席を空けるメンバーを抱えることもあり、女性を登用する機運がなかったようだ。
その後、女性コンサートマスターも誕生、女性奏者は試用期間やエキストラ採用も含め23人(正会員は19人)となったが、変革はまだ始まったばかり、と渋谷さんは見ている。
本書の読みどころは、ワーグナーやマーラーら、ウィーン・フィルと関わりの深い作曲家のエピソードだ。ワーグナーは「トリスタンとイゾルデ」の公演のため、77回もリハーサルをしたが、上演が中止になった。20年後に初演を迎えたが、ワーグナーは指揮棒を譜面台に置き、奏者に自由に演奏させて、音楽に聴き入っていたという。
政治や戦争との関わりにふれた第4章も興味深い。ウクライナ侵攻が始まった直後、ニューヨークのカーネギーホールでの公演があった。指揮者ヴァレリー・ゲルギエフとピアニスト、デニス・マツーエフという2人のロシア人をコンサート前日に交代させた。パンデミック時の対応もそうだが、今回の戦争でも、ウィーン・フィルが他の楽団に対して前例を作る形となった。
「現在のクラシック音楽界では、ウィーン・フィルが何をしたかがまるで『判例』であるかのように取り上げられることが多い」
ゲルギエフらを排除したウィーン・フィルだが、必ずしもロシアに縁のある音楽を否定しているわけではないという。ロシア出身のラフマニノフやチャイコフスキーの曲を、アメリカツアーでも演奏したそうだ。
渋谷さんは、有事での対応力を見ていると、「できるビジネスマン」としての側面を持つ彼らが、演奏会で楽器を弾いていることを忘れそうになる、と書いている。
テレビ放送されるニューイヤーコンサートも、こうしたことを念頭に置いて見れば、より感興が増すのではないだろうか。
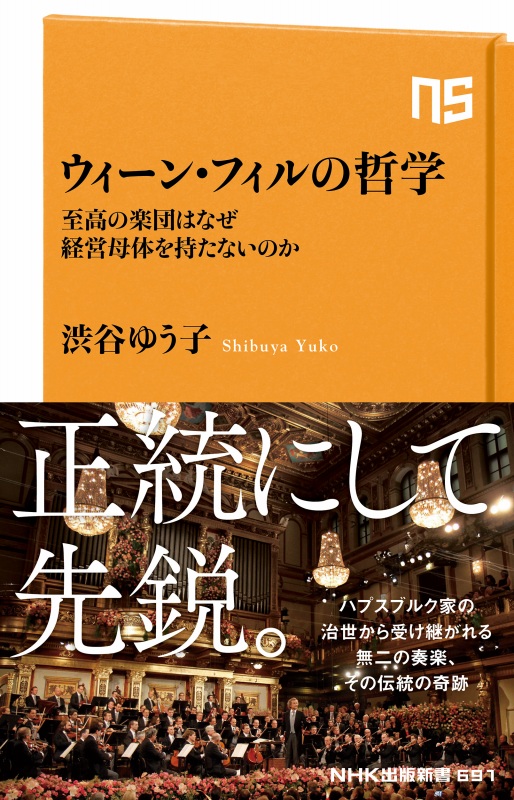
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?