デビュー作『火山のふもとで』(新潮社)以来ファンになった松家仁之(まさし)さんの新作にして、最初で最後の青春小説という触れ込みの本書『泡』(集英社)を、この夏に読むことができたのは僥倖だった。まさにひと夏の物語だったからだ。
『火山のふもとで』は、浅間山のふもと北軽井沢の別荘地を舞台にした、若き建築家のひそやかな恋を描いたものだった。本書の舞台は南紀・白浜を思わせる、「温泉と海水浴の町」砂里浜(さりはま)だ。高校2年の薫は学校に行けなくなり、夏休みを利用して大叔父の佐内兼定のもとに転がり込む。教師である薫の父は、兼定が教育的ではないところに、かえって薫の回復のきっかけを期待したのだ。
東京生まれの兼定だが、遠く離れた砂里浜でジャズ喫茶「オーブフ」を営んでいた。薫は正式なアルバイトというわけではなく、たんなる手伝いで、店はたった一人の従業員、岡田が切り盛りしていた。
5年前、ふらりと岡田がやってきて、そのまま住み着いた来歴が語られる。ダッフルバッグをひきずりながら、髭も髪も伸び放題の男が店に入ってきた。
「歩いてすぐのところに銭湯がある。気持ちいいよ。温泉だし海も見える。荷物はここにおいて、さっぱりしてくればいい」。岡田にそう声をかけたときには、店で働いてもらおうと思っている兼定だった。「岡田の目に暗がりはある。あるけれど、岡田は人を殺してはいない」。
モダンジャズのレコードをかける場面が出てくる。いつの時代の話だよ、と思って読み進むと、想像以上に昔のことであることがおいおい分かる。
兼定はシベリア抑留帰りの復員兵だった。「シベリアで長年教育されて、工作員として日本に送りこまれてくると聞いた。お前もアカなら、この家にいる場所はないからな」。心のよりどころにしていた生家で、そう長兄に告げられた。親元に戻っていた妻とは1年後に離婚した。
砂里浜は死んだ仲間の帰ることのなかった故郷だった。小さな遺品を渡そうと訪れたが、家には誰も住んでいなかった。海の見える町、坂のある町に住んでみたいと思っていた兼定は安いアパートを見つけ、保険会社の営業所に履歴書を出すと採用された。如才ない人柄ですぐにトップの営業成績をあげるようになった。
保険会社を退職し、貯めた資金で「オーブフ」を開き、常連客もつくようになった。だが、今は岡田目当ての女性客が多いことがさりげなく書かれている。
そうした兼定の事情とともに、砂里浜での薫の生活が描かれる。午前中は浜にいても、11時まではアパートに戻り、シャワーを浴びて身支度して店に出る。忙しいのはランチタイムの1時間だけだ。その後は昼寝をして、夜の営業を待つ。
ある夜、岡田の恋人マサコが友人のカオルを連れて店に来た。店が終わった後、4人で花火をした。二人きりになったとき、カオルが「おいてけぼり同士キスでもする?」と投げやりに言った。ごくりと息を呑む薫だった。
兼定の抑留時代のことが断片的に描かれる。小樽高商でロシア語を学び、ロシア語が出来ることを隠していた。悟られないようにしたが露見し、さらに帰国するまで年月が必要だった。小樽時代が、兼定の青春の終わりだったことが伝わってくる。
岡田から教えられ、薫の料理の腕は日増しに上達していった。ポテトサラダとホットドッグ用のキャベツ炒めは、薫がつくって店に出せるようになった。接客もうまくなった。砂里浜での2カ月を終え、薫は東京に帰っていく。
たいしたエピソードがある訳でもなく、淡々と夏は過ぎていく。その中でも元気を取り戻していく薫。兼定の「失われた青春」との対比で、これからの無限の可能性が示唆されている。
岡田が東京出身であることは明かされたが、最後まで何者かは分からないままだ。しかし、決して岡田との距離を縮めないようにしている兼定の心づかいが気持ちいい。
過去を背負った人たちがいて、彼らに支えられて若者は成長していく。そうした好日的な物語として読めばいいのではないだろうか。とは言え、学校嫌いの高校生に勧めても理解してくれるかどうか不安である。何せ時代は数十年前のこと。著者の青春物語と理解するしかないかもしれない。
恋の花も実もある青春物語を期待する人には、やはり『火山のふもとで』を推したい。
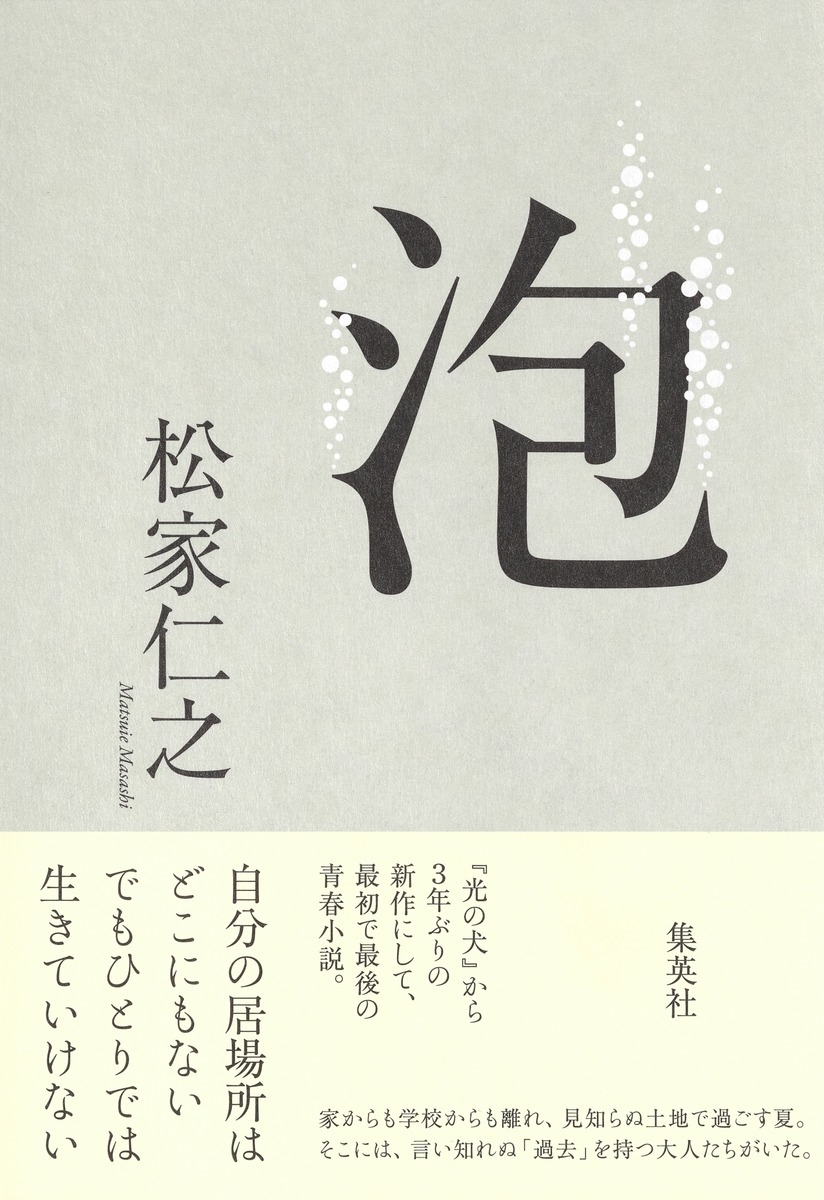
著者の松家仁之さんは、1958年生まれ。新潮社で編集者として活躍、季刊総合誌「考える人」の創刊編集長、「芸術新潮」編集長を兼務して2010年に退職。『火山のふもとで』で2013年、読売文学賞を受賞2018年『光の犬』で芸術選奨文部科学大臣賞、河合隼雄物語賞を受賞。
BOOKウォッチでは、『火山のふもとで』(新潮社)を紹介済みだ。
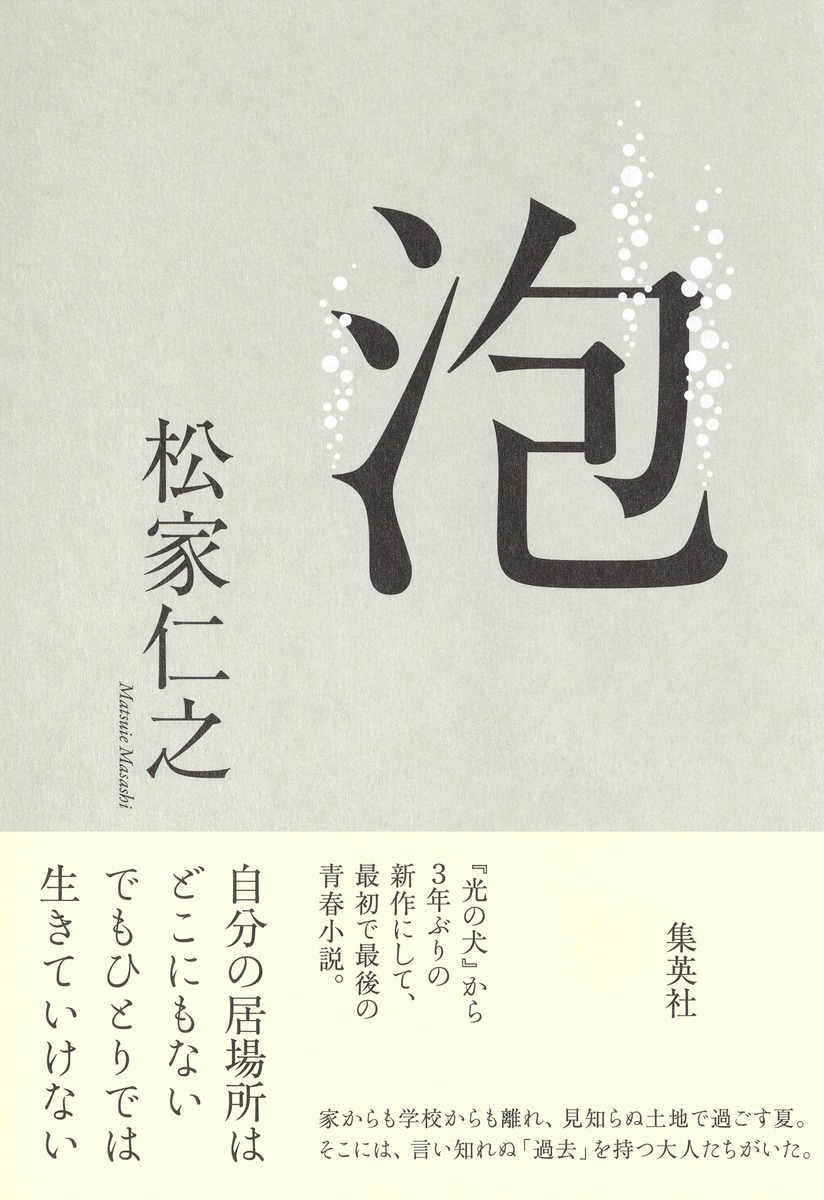
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?