毎年夏休みの季節になると、読み返したくなる本がある。本書『火山のふもとで』(新潮社)は、2012年発行の松家仁之(まついえ・まさし)さんのデビュー作。浅間山のふもと、北軽井沢の別荘地を舞台にした若き建築家のひそやかな恋と青春の物語である。
「『夏の家』では、先生がいちばんの早起きだった」で物語は始まる。主人公の「ぼく」は、村井設計事務所に入ったばかりの新人。東京・北青山にある事務所は、毎年、7月の終わりから9月半ばまで「北浅間の古い別荘地、通称青栗村にある『夏の家』へ、事務所機能が移転する」のだった。
この設定は実に上手い。軽井沢に関しては、別荘族や小説家を主人公にした作品が多い。だが本書は期間限定とは言え建築設計事務所が舞台なので、徹底したリアリズムが作品の基調となる。
事務所の目下の課題は「国立現代図書館」の設計コンペだ。所長の村井俊輔は、フランク・ロイド・ライトの弟子で「日本的モダニズム」で評価された建築家。しかし、住宅建築を主に手掛けているため、こじんまりした事務所の雰囲気は家庭的だ。
いまは設計にはCADなどのソフトが必須でパソコンが欠かせない。だが本書は1982年の設定なので、製図用鉛筆のステッドラー・ルモグラフ、ユニの消しゴム、トレーシングペーパーが必需品だ。鉛筆を削る音で一日が始まる。「午前と午後で最大十本の鉛筆を使うぐらいが仕事の正確さを守ることになる」という目安に沿って、所員は淡々と仕事をし、静謐な時間が流れる。
先生の姪の麻里子が夏の家の期間だけのアルバイトとして登場、物語は動き出す。週3回、下の旧軽井沢まで一緒に買い出しに出かけるようになるが、先輩から「所内恋愛は禁止」と注意される。だが、旧軽井沢にある麻里子の別荘に立ち寄るうちに次第に親密になる。
小説の舞台になっている「青栗村」にはモデルがある。北軽井沢の大学村だ。昭和3年(1928年)に法政大学の学長、松室致が法政大学の先生方に分譲したのが始まりで、その後、岩波書店の岩波茂雄、哲学者の田辺元、谷川徹三らが家を建て始めた。大学関係者、文化人ら入居者の自治で運営され、一種のサロンのようなコミュニティーを形成していた。
作家の野上弥生子は開村以来の住民で、作中にも野宮春枝として登場する。「開村当時からここにいて、大雪の日にヒマラヤスギの大木が自分の家を押しつぶしても、平然としていた小説家。あんなに小柄な人だったとは」。
軽井沢周辺の自然の描写が美しい。その一方で、コンペには大きな公共建築をつぎつぎに落札してきた船山圭一の事務所も参加していることが明らかになり、緊張が走る。
そして夏が終わり、ふたたび事務所は東京へ戻る。コンペの締切まであと1か月というある日、「ぼく」は先生と二人で軽井沢に向かう。仕上げの仕事をする先生の運転手として同行したのだ。そして物語は駆け足で終末を迎える。
発表当時の新聞書評に「読み終えるのが惜しいほど甘美な作品だ」とあったように、ひと夏の時間がゆっくりと流れてゆく。また「先生」をはじめ、建築家が語る世界は理性に満ちて、明晰だ。それらが混然一体となり、至福の境地に読者を誘う。
著者の松家さんは、1958年生まれ。新潮社で編集者として活躍、季刊総合誌「考える人」の創刊編集長、「芸術新潮」編集長を兼務して2010年に退職。デビュー作の本書で2013年、読売文学賞を受賞という老成ぶりを示した。
本欄では4作目の『光の犬』(新潮社、2017年)を紹介している。
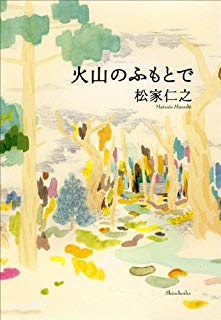
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?