邪馬台国の女王・卑弥呼はあまりにも有名だ。ところで、彼女はどんな時代に生きていたのだろうか。本書『卑弥呼の時代』(吉川弘文館)は紀元三世紀ごろの古代社会の姿を、多方面からのアプローチで探る。同社の「読みなおす日本史」シリーズの一冊。現在では入手が難しくなっている日本史研究の名著、良書を復刊しているシリーズだ。本書の原本は1995年に新日本出版社から刊行されている。
著者の吉田晶さんは、1925年生まれ。京都大学文学部史学科卒業。大阪電気通信大学教授、岡山大学教授などを歴任。2013年に亡くなっている。『日本古代国家成立史論』(東京大学出版会)、『日本古代村落史序説』(塙書房)、『古代日本の国家形成』(新日本出版社)などの著書がある。
本書は以下の構成。
序章 「卑弥呼の時代」へのいざない 第1章 「魏志倭人伝」と邪馬台国の位置論 第2章 倭人の習俗と社会 第3章 「国」の構成と景観 第4章 「王」の出現と「倭国乱」 第5章 卑弥呼の王権について 終章 「卑弥呼の時代」の歴史的位置
多くの古代史ファンの最大の関心事は、「邪馬台国はどこにあったのか」。本書は当然ながら、それにも言及しているが、主語を「卑弥呼」にして、以下の四つの幅広い視点から総合的に分析しているのが特徴だ。
第一に『魏志倭人伝』の史料的価値について。第二に考古学研究の成果を積極的に吸収する。第三に東アジアの国際関係のなかで卑弥呼の時代を位置づける。第四に『倭人伝』に記されている倭人社会の習俗や社会に関する記述を、同じく『魏書』におさめられている烏丸伝・鮮卑伝・東夷伝という東アジアの諸種族の習俗や歴史についての記述と比較し検討する。
邪馬台国の所在地について、著者は基本的に「畿内以外の地に邪馬台国の位置を求めることは困難」という立場だ。理由は、『倭人伝』の記述によるものではない。畿内起源の庄内式土器が北部九州をはじめ関東にまで分布していること、奈良盆地の東南部に前方後円墳が出現し、それが全国に分布するなどの事実によっている。
著者によれば、『倭人伝』の方角や行程記事をそのまま読むと、邪馬台国は東シナ海東方の群島になってしまう。そのため、畿内説では方角に「南」とあるのを「東」の誤りとし、九州説では行程距離の日数や里程を短く考えようとする。いわば『倭人伝』の記述の恣意的な読み替えだ。著者はそのような読み替えはするべきではないという。
むしろ三世紀代の中国人が、倭国および邪馬台国の位置について、どのように考えていたかを正確に理解することが第一の前提だとしている。
そして魏による倭国の地理的認識は、魏の南にあって魏と対立していた呉の存在との関係から生まれている、と見る。『倭人伝』に記されている倭国や邪馬台国の位置に関する行程記事は、魏にとっての東アジア地理像を基礎に書かれたものであり、それは日本列島の現実の地形とは合致しない、したがって邪馬台国の位置論争は、『倭人伝』の記述そのものによっては、ただちに解決しえない問題だと説いている。
魏は卑弥呼による遣使をきわめて厚遇していた。卑弥呼に対し「親魏倭王」という当時としては破格の待遇を与えている。著者がはっきり書いているわけではないが、東アジア周辺国との緊張が続く中で、魏は東シナ海にある倭と特別な関係にある、ということを示そうとしたのではないか、それが『倭人伝』記述の背景になっているのではないか、ということが本書から読み取れる。
本書は、実際のところ、魏使や『倭人伝』の筆者である陳寿は、倭国を東シナ海に南北に連なる群島からなるものと認識していた、と見ている。そうだとするなら、いくら『倭人伝』を読み込んでみても、邪馬台国の場所は特定できないわけだ。
第2章の「倭人の習俗と社会」も興味深い。多くの日本人を悩ませてきたのが「文身(いれずみ)」に関する記述だ。倭人の男子はみな文身をしており、潜水して魚や貝を取っているというのだ。現在の日本人からすると、どこかよその国の話のように感じるが、著者は他の文献史料なども参照し、おおむね事実とする。
なるほどと思ったのは、こうした事実を裏打ちする考古史料があることだ。一つは、「線刻人面土器」。弥生後期のもので、九州中部から関東地方まで分布している。土器の表面に線刻で表現された人面絵画が描かれている。顔に彫られた文身に見える。
もう一つは、人物埴輪に描かれた文身。これも九州から関東にかけて発掘されているという。古代社会では、「戦士」としての威厳づけにもなっていたようだ。
さらには『古事記』『日本書紀』にも、文身に関する記述があるという。年代が下った『隋書』の中の「倭国伝」にも、「男女の多くが文身し、水に入って魚を捕る」という記述があるそうだ。これは608年の隋使一行の見聞によるものなので、その時期まで文身が行われていたことがわかるという。
しかしながら正倉院に伝わる「計帳」には、個人の身体的特徴が黒子(ほくろ)に至るまで記されているが、そこには文身は出てこない。8世紀には文身の風習は消えていたと見られる。
中国では、文身はとっくに刑罰の一つになっていた。中国文明の影響を受けて日本が律令国家となる過程で、文身の習俗は消えたと見られている。同じようなことは南太平洋の民族の文身にも言えるそうだ。15世紀以降、近代文明と触れる中で消えたという。文身の風習は、他の高度な文明との接触や、その受容で消えるものらしい。
こうした文化人類学的な考察を知ると、近年のタトゥーブームは、先祖返りということになるのかもしれない。一種の退行現象だ。
本書ではこのほか、「『倭人伝』の『国』について」「『国』の構成と景観」「『倭国乱』の記事について」「鉄の生産と流通」「王権の宗教的性格について」「卑弥呼の外交」などに論及されている。
最後のところでは、卑弥呼の墓について触れている。結論的なことは書いていないが、『倭人伝』によれば150メートルもの径を持つ巨大なもので100余人もの奴婢が殉葬されたという。これは、大型古墳時代の到来と関係しているのかどうか。
『倭人伝』によれば、239年から247年にかけて魏との通交がひんぱんだった。邪馬台国の使節は歴代中国王朝の都・洛陽を訪れている。圧倒的なスケールの都市に、腰を抜かさんばかりだったことだろう。そういえば、BOOKウォッチで紹介した『日本の古墳はなぜ巨大なのか』(吉川弘文館)には、壮大な規模の始皇帝陵についての情報を、こうした交流を通じて卑弥呼の側が入手していた可能性が示唆されていた。
本書は25年前の刊行なので、読者にとっては最近の新しい研究成果が知りたいところかもしれない。今回の再刊に際して巻末に掲載されている小笠原好彦・滋賀大名誉教授の一文によると、「これを超える邪馬台国・卑弥呼に言及した著作は、今日でも、見当たらないといってよいであろう」とのこと。邪馬台国については、一般向けにさまざまな本が出ているが、アカデミズムの見方を知っておくには適した一冊と言えそうだ。
BOOKウォッチでは関連で、『鏡の古代史』 (角川選書)、『ヤマト王権誕生の礎となったムラ 唐古・鍵遺跡』(新泉社)、『新版 古代天皇の誕生』(角川ソフィア文庫)なども紹介している。
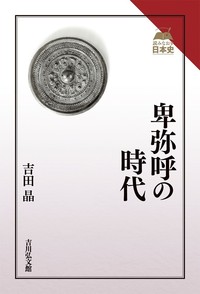
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?