仕事や恋愛、友人関係などあらゆる人間関係において、「共感」できることは、とても大切な能力だ。しかし、過度に共感が求められる場面に、息苦しさを感じた経験がある人もいるのではないだろうか。

テロ・紛争解決スペシャリストの永井陽右(ようすけ)さんの著書『共感という病』(かんき出版)は、共感の「負の側面」を明らかにし、向き合い方を考察していく。
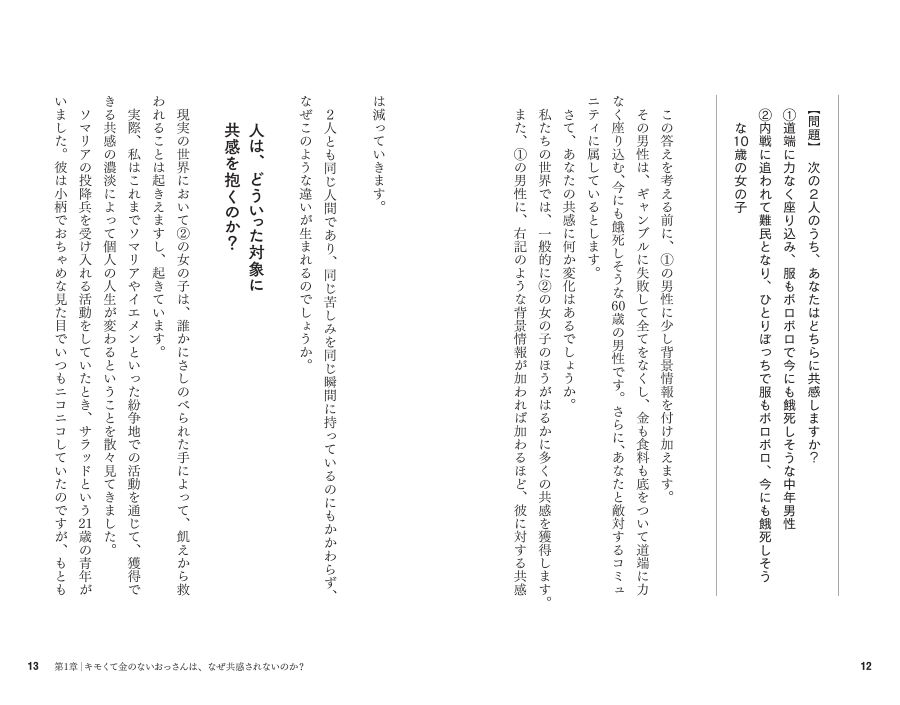
例えば、道端に力なく座り込み、服もボロボロで今にも餓死しそうな人物がいるとしよう。それが、中年男性か、10歳の女の子の場合、あなたはどちらに共感するだろうか。
中年男性のほうは、ギャンブルに失敗してすべてを失い、金も食料も底をついた60代で、あなたとは敵対するコミュニティに属している。一方、女の子の方は、内戦に追われて難民となり、ひとりぼっちの身の上。となると、多くの共感を集めるのは、やはり10歳の女の子の方ではないだろうか。
2人は同じ苦しみを同じ瞬間に味わっている。にもかかわらず、なぜこのような違いが生まれるのか。
「私たちは、結局のところ、どこまでも個々人が持つバイアスに振り回されている」と永井さんは指摘する。結果として「共感」は、全員ではなく「特定の誰か」しか照らさない「スポットライト的性質」と、自分にとって照らすべきだと思えた相手しか照らさない「指向性」を持つことになるという。
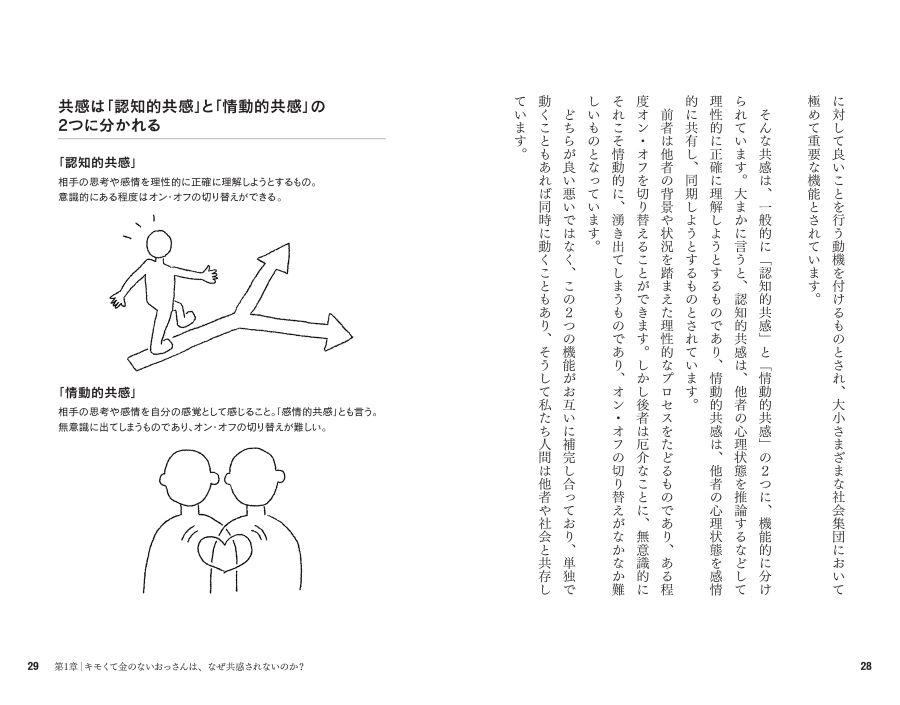
過剰な共感は対立や分断を生む。特に近年の日本社会では「共感」がいきすぎ、同調圧力が強くなりすぎている面もあるという。「味方ではない」と認識した人に厳しく、ネットでの炎上などは、その典型例ともいえる。
「はじめに」で、永井さんは、「共感」というものに「胡散臭さ」も感じてきた、という。
東日本大震災に対する「絆」に始まり、ラグビーワールドカップでの「ワンチーム」、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた「団結」など、それ自体は素晴らしいアイデアではありますが、どこかそうした美しい概念が本来の目的を超えた何かに対して恣意的に使われてきた節もありました。
たしかに「絆」や「ワンチーム」「団結」の内部は、最高に気持ちが良くて恍惚すらできるものですが、よく見てみると、その中にいない人がたくさん存在していることに気が付きます。むしろ外側にいる人に対して排他的であることも珍しくありません。「共感し合おう」「繋がっていこう」と言うと、なんとなく無条件に良いものである気がしますが、繋がっていくからこそ分断していくとも言えるわけです。
確かに、理念に共感する人が増えるほど、同じ考えを持たない(持てない)人たちへの風当たりは強くなる。
私は共感が全て悪いとは思っていませんし、そんなことを言うつもりも毛頭ありません。むしろ社会と世界を良くするために間違いなく重要な要素だと思うからこそ、共感が持つ負の面を理解し、自覚し、うまく付き合っていく必要があると思うのです。
本書の目次は以下の通り。哲学者の内田樹さん、#KuToo運動で女性差別反対運動を行っている石川優実さんとのロング対談も収録されている。
【目次】
第1章 キモくて金のないおっさんは、なぜ共感されないのか?
第2章 共感中毒がもたらす負の連鎖
第3章 紛争地域から見る共感との付き合い方
特別対談 石川優実
第4章 戦略的対話 わかりあえない相手とのコミュニケーション
第5章 基本的に人はわかりあえない
第6章 共感にあらがえ
特別対談 内田樹
「周りに合わせなきゃ」と時に息苦しく感じることがあるが、そう感じているのは自分だけではない。現代の「共感中毒」時代をうまく切り抜ける方法を考えていきたい。

当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?