ややこしい物事は、角度を変えて見ると、すっきりすることがある。登場人物が入り組んで様々な戦いが続いた戦国時代。それを経済、財政、経営という近代の視点から見直したのが本書『戦国大名の経済学』(講談社現代新書)だ。大名たちのサバイバル合戦の背景がすんなり理解できる。これまでほとんど類書がなかったそうだ。
甲冑など兵士1人の装備は一式で約70万円、鉄砲1挺50万円、戦いに備えた兵糧米代1000万円・・・「銭がなくては戦はできぬ」とキャッチにあるように、本書は戦国時代を「カネ」の面から掘り下げる。
著者の川戸貴史さんは1974年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位修得退学。博士(経済学)。現在、千葉経済大学経済学部准教授。専門は、貨幣経済史。著書に『戦国期の貨幣と経済』(吉川弘文館)、『中近世日本の貨幣流通秩序』(勉誠出版)がある。
戦国の世は戦いの時代。大量の兵を動員して装備を近代化、城を頑強に作り替え、権謀術数の限りを尽くして、絶え間ない権力闘争に勝利する。そのために先立つものは軍資金だ。平時においても、支配している領地を円滑に運営するには資金が必要だ。河川改修や道路の整備など、今でいう公共事業もやらなければならない。
大名たちはどのようにして「カネ」を調達したか。本書はそのような問題意識のもとに、戦国時代とその前史を振り返る。すると、あの戦国時代が、一段とリアリティを帯びて現代によみがえってくる。
本書はまず、戦国時代の前史に当たる15世紀の状況から説き始める。将軍が全国に睨みを利かしていたころ、守護大名は幕府の庇護を期待し、幕府に毎年定額を出資(守護出銭)していた。これが幕府財政の基盤だった。ところが経済が疲弊し、幕府のパワーが弱まってくると、カネを出し渋る大名が増えてくる。
このころの主要産業は農業だった。米作りがもたらす年貢がすべての基盤となっていた。ところが、15世紀は寒冷期。天候不順で凶作が続いた。あちこちで一揆や徳政令を求める動きが目立つようになる。1461(寛正2)年の大飢饉では京都だけで数万人の餓死者が出たという。これは当時の京都の人口の約半分に当たるという。
日本全体の富の蓄積が停滞、もしくは下落傾向に陥ると、各地の守護大名同士も生き残りに必死になる。もはや幕府による庇護は期待できない。政治的にも経済的にも自立の動きが加速する。応仁の乱は、守護大名自身が経済的自立を確立して、自らの意志で戦乱への参加を決定しうるようになったことを示す象徴的な戦争だった、と著者は見る。
本書は以下の構成。
序章 戦国時代の経済と戦国大名の経営 第一章 戦争の収支 第二章 戦国大名の収入 第三章 戦国大名の平時の支出 第四章 戦国大名の鉱山開発 第五章 地方都市の時代――戦国大名と城下町 第六章 大航海時代と戦国大名の貿易利潤 第七章 混乱する銭の経済――織田信長上洛以前の貨幣 第八章 銭から米へ――金・銀・米の「貨幣化」と税制改革 終章 戦国大名の経営と日本経済
農業生産・米作り=年貢に依存していた財政状況をいかにして多角化するか。それが室町時代後期から戦国時代にかけての大きな流れだったようだ。各章の目次からも読み取れる。
多角化の一つは、鉱山開発。15世紀後半には今川氏が駿河国安倍山で金鉱開発に成功していた。採れた金をあちこちに政治工作用の「贈答品」として配っていたことがわかっている。
甲斐国でも武田信玄が活躍した時代に、金が採れていたという。武田氏が内陸部のそれほど肥沃でもない土地にありながら、突出した軍事力を維持できた要素の一つに金の生産があった、と著者は推測する。
いちばんの注目は石見の銀山だ。開発したのは、中国地方に一大勢力を誇っていた大内氏。品質の良さが国際的にも評判になる。天下統一を果たす中で豊臣秀吉は石見銀山を直轄領とし、そのまま江戸幕府に引き継がれた。石見銀山は後世の政権にとっても重要な資金源だった。
もう一つの資金源が貿易だ。戦国時代は、国境管理が緩やかであり、海外の商人たちが大勢やってきた。国際貿易によって富を築くことが可能になった時代でもあった。
先の石見銀山は、その意味でも重要だった。なぜなら銀は当時の国際通貨だったからである。南蛮貿易でも銀が貨幣になった。とりわけ九州の大名は貿易を競い合い、利権をめぐって衝突することもあった。キリシタン大名なども一皮むけば貿易とセットになっていたといえそうだ。のちに秀吉が御朱印船貿易のタガをはめ、徳川政権が「鎖国」に乗り出すのも、国際貿易の独り占めを狙ったものだったと見ることができる。
信長などの楽市楽座は、地域の市場経済を活性化させる仕組みだ。儲かった商人たちからの献金で大名のフトコロも潤った。これも年貢以外の収入源の一つといえる。
以上のように見ると、戦国時代とは、経済的な苦境から抜け出すために、領地を広げ、財力を増大させるために様々な方策で大名たちが覇を競い合った時代だったということがわかる。一種のミニ帝国主義だ。負けた側は単に領地を取られるにとどまらない。戦場では略奪など「乱取り」が横行した。モノだけでなく人も奪う。捕虜は戦利品として売買され、中には海外に売り飛ばされるケースもあった。
これまでも、個々の大名がいかにしてのし上がったかについてはいろいろと分析した本が出ているが、本書は総体としての守護大名、戦国大名を見渡している点でわかりやすい。当時の大名財政については、史料が乏しく、著者は苦労して数字を探し出したようだ。
BOOKウォッチでは関連書をいくつか紹介済みだ。『飢餓と戦争の戦国を行く』(吉川弘文館)は、「華やかな戦国大名の合戦物語とはまるで違う、悲惨な戦争の実情」を余すところなく描く。「乱取り」などにについて詳しい。『移民と日本人』(無明舎出版)は、すでに16世紀末に奴隷として南米にまで売り飛ばされていた日本人の話が紹介されている。ローマに派遣され帰国した少年使節団が、道中の世界各地で日本人奴隷を目撃して驚愕していた話も出てくる。
和辻哲郎文化賞を受賞した『戦国日本と大航海時代――秀吉・家康・政宗の外交戦略』(中公新書)も内容が濃い。伊達政宗は1613年に支倉常長をトップにした慶長遣欧使節を送ったが、これは、太平洋・メキシコルートでスペインとの独自貿易の道を模索したものだった。政宗はキリスト教を受容して貿易を振興するつもりだったが、徳川の天下になり断念する。
『信長の経済戦略 国盗りも天下統一もカネ次第』(秀和システム)は、信長にスポットを当てて独自の経済戦略を解剖している。
『耳鼻削ぎの日本史』(文春学藝ライブラリー)には信長軍が伊勢国長島で一向一揆を討伐したときに、百姓の男女2000人の耳鼻を削いでいたという話が出てくる。ほかにも大規模な合戦で耳鼻削ぎが常態化していた。戦国時代は戦死者数が莫大になり、勝った側が「手柄」を簡便な方法で持ち帰ろうとした結果だ。「戦果」が「報償」につながる。秀吉の朝鮮出兵では女子供も含めて何万もの「鼻」が持ち帰られた。その怨念は今も韓国に渦巻く。
『本能寺前夜――西国をめぐる攻防』 (角川選書)は、戦国時代についてのクールな解説が光る。戦国大名が「戦争の大義」をいろいろと掲げていても、結局のところ、「領国を維持するためには、周囲の勢力を殲滅、あるいは服従させて、拡大していくしかない。その結果、戦争自体が目的化してしまったのである」と結論付けている。
戦前の日本が、戦争に突入していく過程でいかにして「軍資金」を調達したかについては『軍事機密費』(岩波書店)に詳しい。一体あの戦争の収支はどうなっていたのか。『兵器を買わされる日本』 (文春新書)は、安倍政権になって米国からの兵器購入が急膨張したことを伝え、「安倍・トランプ」親密さの背景を解き明かしている。
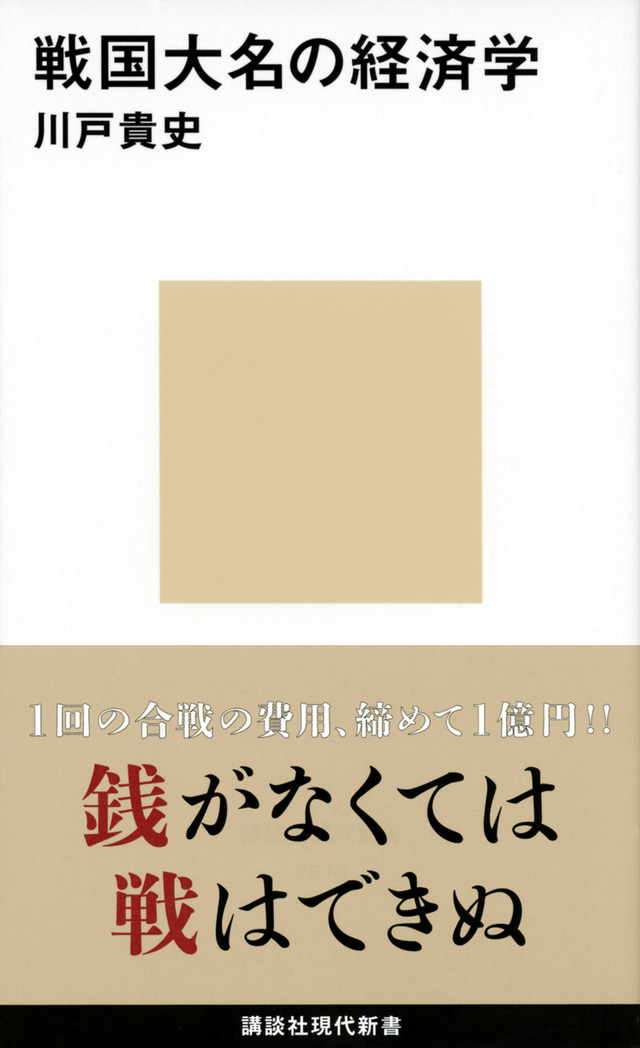
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?