トラクターに世界史的な意味などあるのか? 単なる農業機械でしょ、とつっこみながら読み始めたら驚いた。レーニン、スターリン、毛沢東と現代史の巨人の名前が出てくるではないか。革命政権にとって農業政策とはトラクターをどう利用するかということに尽きたのである。
「牛馬のように飼料を必要とせず、燃料を補給することで物を牽くことができる。人や馬のように疲れることなく、しかも人や馬の何倍もの力をいつまでも安定して出すことができる」と著者の藤原辰史さんは、トラクターの特長をわかりやすく説明する。この結果、人間は大地の束縛から解放されるとともに、多くの問題も生まれたのである。
たとえば土地の荒廃。トラクターの濫用によって1930年代のアメリカ中西部の平原では、ダストボウル(砂塵の器)という現象が発生した。化学肥料の大量使用とトラクターの土壌圧縮によって、土がさらさらの砂塵になり、空を覆ったのだ。ジョン・スタインベックが『怒りのぶどう』(1939年)に描いた農民の流浪という皮肉な事態が生じた。
またキャタピラーによって推進するトラクターは、戦車とは双子のような存在である。実際、大戦時には各国でトラクター生産のための工場で戦車がつくられた。
そうした負の側面もありながら、週刊文春(11月9日号)でライター兼百姓兼猟師という肩書で本書を評した近藤康太郎氏(朝日新聞日田支局長)は、「日本企業得意の安価な小型トラクター(歩行型トラクター)」に光明を見出す。全国に余っている小型トラクターを使い、余っている農地を耕したらいいと提唱する。
また、朝日新聞書評(11月5日付)でも佐倉統さん(東京大学教授・科学技術社会論)は「著者は、こういったマイナスを、国家権力や独占資本がもたらしたといった紋切り型ではとらえない。そうではなく、農民や技術者たちの夢や希望やさまざまな思いが、網の目のように絡まって、トラクターを生み出し、受け入れ、育てていったのである」と述べている。
歩行型トラクターというと肩肘はったイメージがある。日本でなじんだ言い方では、耕運機。トラクターもまた日本では独特の「進化」を遂げたことを知り、「トラクターの日本史」とでもいうべき著者の目配りのよさに感心するのである。
著者の藤原辰史さんは、京都大学人文科学研究所准教授の農業史の研究者。「人文研」の伝統を感じさせる本である。
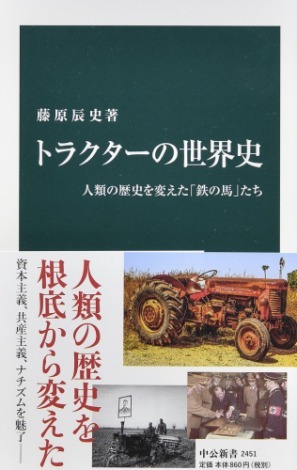
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?