2020年東京オリンピックの開会式などが行われる新しい国立競技場を設計した建築家の隈研吾さんの新著が、本書『ひとの住処』(新潮新書)である。副題の「1964-2020」にあるように、1964年と2020年の二つのオリンピックを補助線に、日本の戦後の建築と自らの歩みを振り返っている。
世界20カ国で建築を設計してきた隈さんの「自分史」のような本でもある。1954年に生まれた隈さんの家は横浜の大倉山にあった。祖父が土いじりのため農家から小さな畑を借りて小屋を建てた。戦後、両親が住居にした。土壁が崩れ、ガムテープで補修する「小さくてボロい家」だった。
田舎も畑も嫌いな母により、隈さんは幼稚園、小学校と電車で東京・田園調布に通学した。そのせいで、友達の家を観察するのに特別の関心があったという。当時、東京は木造の家からコンクリートのビルとマンションに変化する時代。
「友達の家に遊びに行くのは、不思議なワープの旅であった。それは様々な家に出会う旅であったし、様々な人生、様々な街、様々な都市計画、様々な経済に出会える旅であった」
この頃から建築に関心を持っていた隈少年に衝撃をもたらしたのが、1964年の東京オリンピックだった。丹下健三設計の国立代々木競技場の外観に圧倒され、吊り構造の内部は、「神殿」のように思えた。
「いつの日か建築によって人々を感動させたいと、僕はその日に心を決めたのである」
しかし、1970年の大阪万博、高校1年の隈さんは、ヒーローだった丹下健三や黒川紀章が設計したパビリオンを見て落胆する。特に黒川に憧れていたため、鉄でできたカプセル建築のパビリオンに失望した。
東大では工学部建築学科に進み、集落調査で知られた原広司の研究室に入った。しかし、「原は何も教えてくれなかったし、授業やゼミを、原はやるつもりがなかった」。面白いエピソードを披露している。
ある日、学生たちは工事現場に招集された。原先生が設計していた、千葉の山の中の小さな住宅現場で、あまりの工事の難しさと予算の無さのために、工務店が逃げ出したのだ。原は率先して働き、学生らと住宅を完成させた。超現実的な途方もない夢の実現のため働くことに彼らは喜びを見出していた。
その後、隈さんらは原さんを口説き落とし、サハラ砂漠の住居の調査を実現する。行く先々で、ボールペンを子供たちに配り、大人の警戒心を失くしたところで、家を見せてもらう。2カ月の旅で100戸ほどの集落を調査し、図面化することができた。
卒業して飛び込んだ80年代の建築業界は、コンクリートの精度を追求する武士道的な息苦しい世界だった。安藤忠雄氏を「武士道のチャンピオン」と書いている。そんな空気が嫌でニューヨークに渡り、昔のアール・デコ建築を訪ね歩いた。
86年に東京に戻り、自分の事務所を開いた頃に『10宅論』という本を書く。当時、「〇金、〇ビ」という言葉が流行語になり、日本人を分類するのがブームになった。隈さんは、住宅によって、面白おかしく分類した。ワンルームマンション派、清里ペンション派、カフェバー派、ハビタ派、アーキテクト派、住宅展示場派、建売住宅派、クラブ派、料亭派、歴史的家屋派の10派である。
タイトルの「ひとの住処」には、住宅に人の生き方が現れるという隈さんの哲学があるのかもしれない。
後半は地方の各地、高知県の梼原町、宮城県の登米町(現登米市)の現場で出会った木やローコストの建築について紹介している。「戦後システムとは全く別のやり方で、建築を作ることができそうに思えてきた」。
最終章「第4章 2020――東京オリンピック」では、新国立競技場について書いている。第1回の国際コンペで1位に選ばれたのは、イラク出身のザハ・ハディッドだった。隈さんはザハに国際コンペで何度も苦杯を喫している。そもそも隈さんはコンペの厳しい応募要項を読み、「およびじゃない」と思い、エントリーしなかった。
その後、ザハ案への批判や高額な建設費が引き金になり、キャンセルされた。2回目のコンペが行われ、隈さんらのチームが選ばれた。
「2020年なんだから、今さらコンクリートと鉄でもないだろう。この時代を象徴する素材を捜すとしたら、木しかないだろうと思った」
地方の小さな製材所でも加工できる、細い材木を庇などに使った意図を説明している。
さて、新型コロナウイルスの感染の広まりで、東京オリンピックの延期や中止が取り沙汰されるようになってきた。その議論は別として、新国立競技場は、2020年東京オリンピックのシンボルとして長く人々の記憶に残るだろう。この本は設計者からのメッセージでもある。
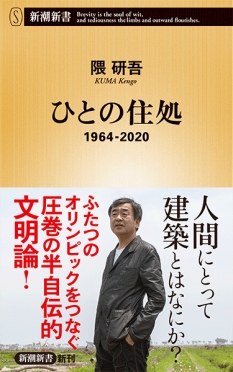
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?