立場が明確な本だ。本書『イスラエルに関する十の神話』(法政大学出版局)は、パレスチナ問題についてのイスラエル側の主張を徹底的に批判している。
これが、パレスチナ人による著作ならば、さほど違和感はない。ところが、著者のイラン・パペ氏はイスラエル・ハイファ生まれのユダヤ系イスラエル人。イギリスのエクセター大学の教授、同大学のパレスチナ研究所の所長でもある。
著者はパレスチナ紛争について、「歴史、それも誰もが知っている直近の歴史までも故意に歪めて、途方もなく大きな危害を引き起こしている」とみる。すなわち「意図的な歴史の曲解が抑圧を強化し、植民・占領政策を擁護」しており、「偽情報を流して事実を捻じ曲げる政策が昔から現在まで続いているために紛争が永続化」していると分析する。
したがって本書の性格について、「いわゆる中立的記述を装う本」ではないと言い切る。そして「イスラエル・パレスチナの地で被植民地人化され、占領と抑圧の犠牲になっている人々に加勢する」と自身のスタンスを明言する。
ここまで旗幟鮮明だとイスラエルとの関係が難しいだろうと心配になる。そのあたりは著者も自覚しているようだ。「もしシオニズムの提唱者あるいはイスラエルに忠実な人が本書で展開した議論に関わる気になってくれれば、何よりの幸せ」と語り、次のように付け加えている。
「私はイスラエル人で、パレスチナ社会と同じようにイスラエル社会のことを心配している」
「この国の不正を支える神話の間違いを明らかにすることは、この国に住む人々、この国に住もうと思う人々にとって、有益であるはずである」
タイトルにある「十の神話」のいくつかは、日本に住む私たちにもなじみがある。「パレスチナは無人の地であった」「ユダヤ人は土地なき民族であった」「シオニズムはユダヤ教である」「シオニズムは植民地主義ではない」「一九四八年にパレスチナ人は自ら居住地を捨てた」「一九六七年六月戦争は『やむを得ない』戦争であった」「イスラエルは中東で唯一の民主主義国家である」・・・。
著者はこれらを「神話」とみなし、ことごとく否定していく。パレスチナは民なき土地ではなかったし、ユダヤ人は土地なき民ではなかった。パレスチナは植民地化されたのであって、ユダヤ人がイスラエルを回復したのではない・・・。
いくつか興味深い記述があった。たとえば高名なユダヤ人哲学者、マルティン・ブーバーとマハトマ・ガンジーとの「対話」。ガンジーは1938年、ブーバーにシオニズムの事業を支援してほしいと頼まれたが、「同情によって正義を曇らせることはできない」と拒否する。
「ユダヤ人の民族郷土を求める声は私の心に訴えるものがない。彼らは聖書と、執拗なパレスチナ帰還という民族的願望により、他者の土地での民族郷土設立を正当化する。しかし、自分が生まれ暮らしている国を自分の郷土とする民族はいくらでもいる。なぜ彼らも同じようにしないのか?」
背景には、インドを植民地化していた英国政府がシオニズム(ユダヤ人の民族国家をパレスチナに樹立することを目指した運動)を支援しているという事情もあった。つまり、シオニズムは、別の側面から見ると、英国政府が中東に足場を築くための方策の一つであり、そのことが「ガンジーの心をいっそうシオニズムから遠ざけた」と著者は指摘する。
シオニズムは19世紀の欧州で台頭したが、当初、ユダヤ教超正統派は反対し、信者が活動家として関わることを禁じていたという指摘も興味深かった。超正統派のラビたちは、シオニズムを、メシアの到来によってイスラエル再建がなされるまでユダヤ人を異郷生活に留めるという神の御意志を人為的に行おうとする冒涜行為だと非難したという。
また、英仏などに住むユダヤ人の経済的有力者たちも困惑したそうだ。なぜならシオニズムは今住んでいる国に対する忠誠心に疑問を投げかけるような思想だったからだ。それゆえ第一次大戦末に英国が「バルフォア宣言」でシオニズムに全面協力するまで、強い運動にはならなかったと指摘する。つまりシオニズムは元来ユダヤ人の中でも少数派の思想だったというのが著者の見解だ。
訳者の脇浜義明さんの「あとがき」によると、イスラエルは2018年7月、「イスラエルはユダヤ人のための民族郷土国家で、ユダヤ人だけが民族自決権を持ち、ヘブライ語を国語とする」という「ユダヤ民族国家法-基本法」を成立させた。このことについて脇浜さんは、「アパルトヘイト国家であることを法的に決定した」とみなし、「イスラエルは民主主義国」という神話を自ら捨てたと認定する。
脇浜さんは最近の米国の潮流の変化についても触れている。米国はイスラエルの最大の支援国であり、民主党リベラルも「親イスラエル」だったはずだが、最近、イスラエル離れが加速しているのだという。世論調査でも親イスラエルと、親パレスチナの比率が逆転している。焦った親イスラエルロビーは、教科書におけるイスラエルの歴史などに関する記述の「改善」を求めて圧力をかけているそうだ。
本書は、欧米では常識とされている中東の諸問題について、専門的な学者が書いた本なので、事情に疎い日本人読者にはやや難しすぎる部分があるかも知れない。しかし、パレスチナ問題にとどまらず、紛争の歴史は何が正しいのか、巷間流布している「通説」や「神話」にはフェイクが潜んでいるのではないか、という観点から手に取ると、なかなか刺激的だ。著者自身、「現代のアカデミズムを蝕んでいる病気――実践的参加や献身的関与は学問研究の卓越性を破壊するという発想や束縛から解放されることを願う学生や研究者には、ぜひ本書を読んでもらいたい」とアジっている。
本欄では関連で、『謎解き 聖書物語』(ちくまプリマー新書)、『知立国家 イスラエル』(文春新書)、『限界の現代史』(集英社新書)、『否定と肯定』(ハーパーコリンズ・ ジャパン)なども紹介している。
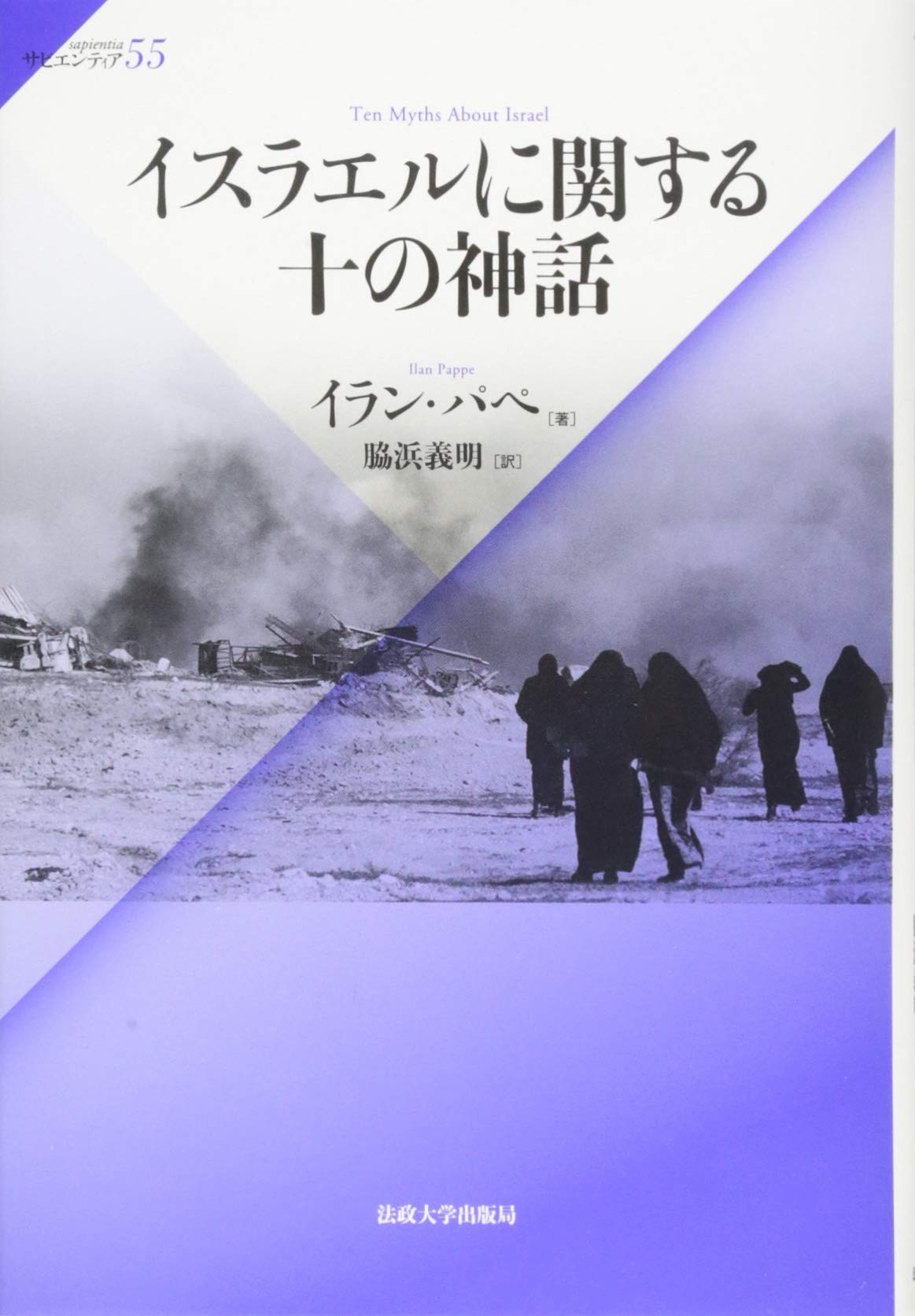
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?