タイトルの「動物になって生きてみた」は比喩ではなく、文字通りそのまま。アナグマと同じように巣穴を掘って生活し、アナグマと同じくミミズを生で食し、森を四つん這いで歩きネズミを追う......。そうやって動物と同じように生きたら動物の視点で世界が見られるのではないか――。それも1日や2日ではない。来る日も来る日も動物と同じ暮らしを続けた体験から、自然の中で動物として生きるとはどういうことかを考察し、2016年のイグ・ノーベル賞生物学賞を受賞したのが本書の著者で英国人ナチュラリストのチャールズ・フォスターである。
驚嘆するのは、著者は本書でアナグマだけはなく、カワウソ、キツネ、アカシカ、アマツバメとも同じ条件で生活してみようと試みていることだ。例えば、カワウソになりきるためには毛皮の代わりにウエットスーツを着て川に潜り、魚やザリガニを食べて生き、縄張りを示すためにあちこちで糞をする。厳冬の季節も含め、この生活を1年間続けたのだ。こうして、それぞれの視点で見えた動物から見た世界を"人間の言葉で"書き表したのが本書だ。
実際のところ、著者のようなやり方で「動物になってみる」のはかなり尋常ではない"実験"と言っていい。都会のキツネになりきろうと試みた際には、ゴミ箱をあさり残り物を口にしたり、ハタネズミを捕らえようとしたりして警察官に不審尋問を受ける羽目になった。自分をアナグマ化させる実験の時には息子をミミズ食に巻き込み、スパゲティのように生きたミミズをすすらせる。この部分の描写には正直怖気が差した。アカシカの身になるため、あえて猟犬に追われる体験もしている。
これらの体験を文章化する方法にも、おそらく相当の工夫がなされている。アナグマの章で触れているが、人間のように目で見た景色を書くのは人間の感じ方で、アナグマになりきるならば景色を鼻で、嗅覚で描かなければならないと考えた。結果として、著者の意を読み取るのが難しい部分があるが、よく読むと実に含蓄のある表現になっている。本書の最大の読みどころだ。翻訳者はさぞかし苦労したことだろう。
また、動物になりきるための知識として、動物たちの生理学的な最新の知見が随所に散りばめられているが、これも大きな本書の読みどころだ。まるで自分もその動物に近づいた気持ちになる。
そうやって最後まで読み続けてわかるのは、人間と動物の圧倒的な違いである。どんなに努力しても、人間はアナグマやカワウソにはなれないという当たり前の事実を改めて理解することで、動物や自然に対して敬意を抱く自分を発見できる。そうした意味でも実に奥深い一冊だ。(BOOKウォッチ編集部 スズ)
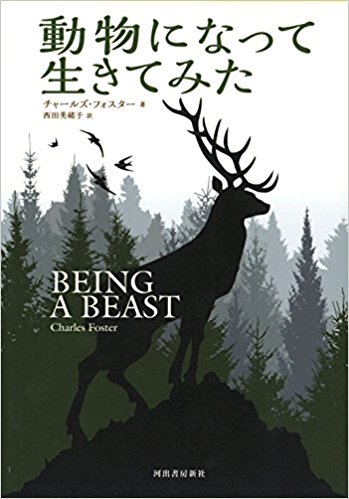
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?