今年(2017年)ノーベル文学書を受賞したカズオ・イシグロの第3作で代表作の一つとされる。第1作『遠い山なみの光』と第2作は『浮世の画家』は、それぞれ日本を舞台としていたが、本作は英国が舞台である。しかも「執事」という英国らしい伝統的な職業にプライドを持つ主人公が登場する。英国最大の文学賞、ブッカー賞を受賞、本作でカズオ・イシグロは、ノーベル賞へのステップを上りはじめたと言ってもいいだろう。
親子2代で執事をしてきたスティーブンスは、邸宅の新しい主となったアメリカ人ファラディに短い旅に出ることを勧められる。人手が足りず邸宅のマネージメントに困っていたスティーブンスは、かつて女中頭だったミス・ケントンの復帰を期待し、職業的な動機で彼女の住む西部地方に向かう。その6日間の出来事とかつての主人、ダーリントン卿に仕えたころの回想が巧みに交差する。
第一次大戦後、ドイツではナチスが台頭しつつあった。ドイツへの過酷な賠償請求をゆるめることがヨーロッパの平和に寄与すると考えたダーリントン卿は邸宅で、非公式な国際会議を開く。欧米からの要人をアテンドする責任がスティーブンスにのしかかる。執事の仕事は国際的なホテルのマネージャーのようなことも併せ持つのだ。その最中に副執事の父の死、ミス・ケントンとのいさかいが起きる。それがいかに重大なことだったかをスティーブンスは、のちに知る。
カズオ・イシグロは、自ら自分の作品の重要な要素は「記憶」だと、ノーベル賞受賞のインタビューで語っている。旅をしながらスティーブンスは、過去の栄光を振り返り、現在を思う。第二次大戦後、ダーリントン卿はナチスへの協力者として非難され没落する。そのダーリントン卿に尽くすことが、自分のすべてだったのだ。
旅の最後の1日について書くのは控えよう。ただ、つねに「品格」を重んじ、自己啓発を怠らない主人公から少しばかりの勇気をもらった、としておこう。
解説の丸谷才一が「土屋政雄の翻訳は見事なもの」と書いているとおり、上質な日本語をたっぷり味わうことができる。
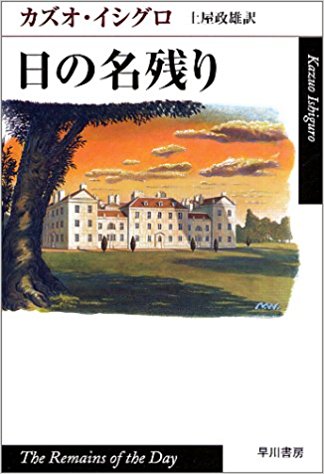
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?