少子高齢化が進む社会の潮流の一つとして「終活」がほぼ定着し、生前整理やエンディングノートなどをめぐってはビジネスも盛んで、愁嘆場のようなイメージはほとんどない。本書は著者の蔵書処分編としての「終活」をつづったものなのだが、世間のカラリとした断捨離とは対照的に、それはもう、自身にとってはまさにこの世の終わり的なことだった。
著者は1935年生まれ。10歳の頃からほぼ70年かけて集めた蔵書は約3万冊。それを2年ほど前、数百冊を残して処分することに。蔵書を積んだトラックを見送ったあと「その瞬間、私は足下が何か柔らかな、マシュマロのような頼りのないものに変貌したような錯覚を覚え、気がついた時には、アスファルトの路上に俯せに倒れ込んでいた」という。
著者は自身のウェブサイトで「蔵書のほとんどすべてを、万やむなく処分したことで、体調に著しい変化をきたし、これを機に蔵書とは何かということを考えるようになった」と本書出版にいたった思いを吐露。「近年、蔵書処分をめぐって悩む人が多いとやら、一つの世代的な現象なのかもしれない。実際、蔵書処分は大変なことで、人生の終末期に、こんな段階があるとは思ってもみなかった」と嘆く。
生前整理や断捨離への関心が高まりはじめたころには、その方法の一つとして、蔵書の図書館への寄付が紹介されたことがあり、著者もそれは検討したようだ。本書では、日本の出版文化をたどったうえで、蔵書維持の困難性に言及している。
評者の平山周吉さん(雑文家)は「最初に涙し、最後も涙でにじむ」と著者の気持ちを思いやる。そして、本書を著すことが、著者にとっての慰みであるとともに「『書物へのリスペクト』を喪失した現代日本への静かな告発にもなっている」と指摘した。
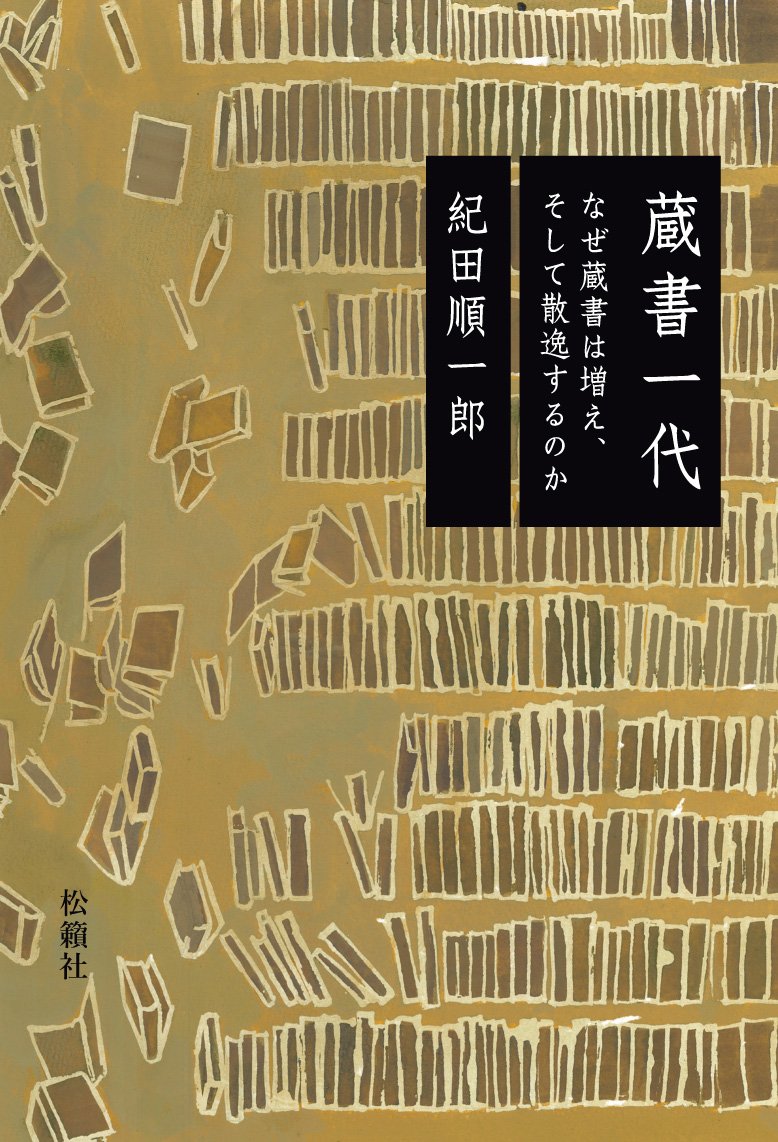
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?