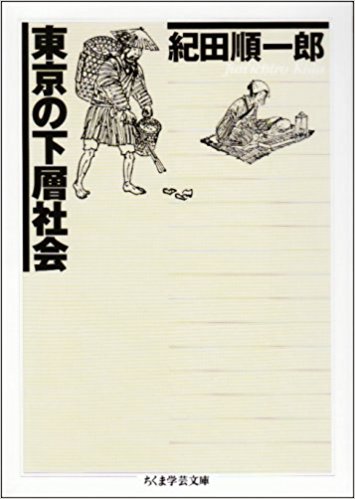東京を変える、再生させる――都知事選や都議選のたびに、そんなスローガンを聞くが、過去の東京はどうだったのか。
紀田順一郎さんの『東京の下層社会』読むと、明治、大正、戦前の東京の凄まじい姿がわかる。「忘れられた東京」「知らなかった東京」だらけ。目からうろこになること請け合いだ。
棟割長屋は異臭ふんぷん
驚くのは、昔の東京に貧乏人が多かったことだ。昭和4年発行の『新版大東京案内』によると、救護法の対象とされていた極貧者が約12万人。低所得者層は約30万人。当時の東京市の人口の約1割5分にのぼったという。
明治までさかのぼると、状況はもっとひどい。東京のあちこちに貧民街があった。
「近親相姦や強姦も日常茶飯事」「棟割長屋は異臭ふんぷん」「結核菌が蔓延」
1891(明治24)年、ロシアの皇太子が来日したときは、政府が東京市に命じてすべての乞食を元加賀藩の施設に収容し、外出させないようにしたという。昭和初期、ある極貧地域の小学校では、児童398人のうち104人が残飯を主食にしていたそうだ。「帝都」と胸を張っていた時代だが、いったいどこの国の首都の話かと仰天してしまう。
筆者の紀田さんは作家、評論家。SF研究からスタート、読書論、出版情報論など膨大な知識量で知られる。神奈川近代文学館の館長なども務めた。本書は過去の様々な「東京本」を渉猟してまとめたものだ。桜田文吾『貧天地饑寒窟探検記』、草間八十雄『近代下層民衆生活誌』など、今では知る人が少ない当時の出版物から生々しい話が引用されている。巻末にはそれらの一覧が記されている。
「もう泣くまい。悲しむまい・・・」
とくに興味深いのは「娼婦」についての記述だ。大正末期から昭和初期、全国で売春業に関わる女性は約15万人。15歳から35歳までの女性の76人に1人が関係していたという。
1924(大正13)年、群馬県から東京の新吉原に売られた森光子と言う19歳の女性がいた。「もう泣くまい。悲しむまい・・・自分の仕事をなし得るのは自分を殺す所より生まれる」。そう日記に書いた光子は決死の脱出に成功して、体験記を残した。実家の借金返済のために身を売ったが、いくら稼いでも楼主からの前借りは絶対に返せないシステムを詳述している。当時、娼婦になった女性の88%は「家の困窮を救うため」だったという。
紀田さんは、そうしたデータを参照しながら、永井荷風が東京の赤線街などを舞台に描いた娼婦像に疑問をはさむ。「背後に実生活の匂いや家の重圧と言ったものがほとんど感じられない」「現実の女性たちの苦悩は捨象されている。あえて言えば見て見ぬふりをしているのである」。
スラムや娼婦の話は遠い昔の話なのか、それとも今の時代にも地続きなのか。各紙の報道によれば、小池百合子知事は、関東大震災の朝鮮人犠牲者を慰霊する式典への追悼文送付を取りやめたという。確かに東京は1923年の大震災、45年の大空襲、64年の東京五輪で脱皮を繰り返し、様々な過去を埋葬、世界に冠たる近代都市に生まれ変わった。だが、為政者であるからには、地層の奥深くに刻まれている「負の歴史」「声なき声」を忘れずに、東京再生に取り組んでもらいたいものだ。本書を読んでそんな感想を持った。