数学の本というと敬遠してしまう向きが圧倒的に多いことだろう。本書『小数と対数の発見』(日本評論社)は一般向きの本とはちょっといいにくい。ただ団塊の世代には懐かしい著者の名前を見て手に取る人もいるかもしれない。
著者は1960年代後半から70年代初めにかけて全国を吹き荒れた学園闘争の指導者で、東大全共闘代表を務めた。当時は東大理学部物理学科の大学院博士課程に在学中だったが、大学院を中退し、その後は長く駿台予備学校の講師を務めている。予備校で教えるかたわら地道な科学史研究を続け、近世物理学の幕開けを叙述した『磁力と重力の発見』(2003年、全3巻、みすず書房)は毎日出版文化賞、大佛次郎賞などを受賞、海外でも翻訳された。その後、『十六世紀文化革命』(全2巻)『世界の見方の転換』(全3巻)と続く科学史3部作は2014年に完結した。本書はその副産物として生まれたものだという。
小数というと、きょうの最高気温は33.1度、最低気温は23.5度など、われわれの日常生活にも当たり前のように登場する。だが、10進小数が登場したのはそれほど古いことではない。数を数えたり物を測る技術は文明の誕生とともに始まったと考えられているが、最初は60進小数が用いられていた。下の桁が10になると桁上がりする10進ではなく、下の桁が60になると桁上がりする仕組みだ。これは円周を360度とすることと関係があったようだ。
だが、実際に60進小数を使うのは面倒だ。12世紀になると0を含む10進位取り表記がイスラム世界から西洋に伝わってきた。しかし、0から9のインド・アラビア数字がすぐ使われるようになったわけではなく、16世紀前半の天文学者コペルニクスの著作にもⅠ、Ⅱといったローマ数字が使われていたという。著者はこれを西欧世界では貨幣体系や度量衡にも10進法ではない数え方が生き残っていることに注目する。イギリスでは比較的最近まで貨幣単位としては1ポンド=20シリングだった。度量衡でも1ヤード=3フィート。重さでは1ポンド=16オンスといった数え方が欧米では日常的に使われている。古代中国や日本のように数が大きくなると十、百、千、万、小さい方を分、厘、毛、糸と10進で数えたのは例外的だったようだ。小数点を使った10進小数の表記が実現するのが16世紀後半から17世紀初めというのにはちょっと驚かされる。
対数が発見されるのはそれとほぼ同時期のことだった。対数は高校数学で登場するが、忘れてしまった人も多いだろう。対数の記述法について初めて提案されたのは1614年、スコットランドのネイピアという科学者によってだった。対数はごく大きな数や小さな数を扱う科学技術計算で威力を発揮する。
対数の発見当時、目を見張るような進展が起きていた天文学で、対数の導入が進んだのは当然のことだった。天文学者のケプラーはすぐに対数の有用性に着目した。彼は天体観測家ティコ・ブラーエの助手として師の膨大な観測結果をまとめ、「ケプラーの法則」という惑星運動の法則を発見したことで知られる。ネイピアが提唱した対数が天文学の世界で、きわめて有用であることを見抜き、独自の対数表を作ったという。対数の導入で計算が大幅に楽になり、俗に天文学者の寿命が10年延びたといわれるほど効果が大きかったという。
今日、科学技術計算の世界に欠かせない常用対数が考案されたのはその直後のことだ。常用対数は建物の構造計算など工学の計算でよく使われる便利な道具だが、その概念が生み出されたのは比較的最近のことだったわけだ。
筆者は近世物理学の進展を側面から支えた実用数学を極力、ラテン語などの原著にあたり丁寧に読み解いていく。数字や数式が多いので、決して読みやすいとはいえないが、筆者が丹念に集めた原著や当時の文献から転載した科学者の肖像画や当時の文献の表紙、そこに収録されている数表など図表が多数収められていて、数式を飛ばしてしまえばそれほど読みにくくない。当たり前のように思っている小数や対数がどういった歴史を経て実用化されたのか。日常生活の深みにはまっている凡人を啓発し、刺激してくれる労作だ。
本書出版元の日本評論社は「数学セミナー」などの刊行で知られる数学に強い出版社。創業100年になる。著者の山本氏は今年、『近代日本一五〇年――科学技術総力戦体制の破綻』(岩波新書)も出しているほか、『フォトドキュメント東大全共闘1968‐1969』(角川ソフィア文庫)にも長文の寄稿をしている。76歳だというが意気軒昂のようだ。
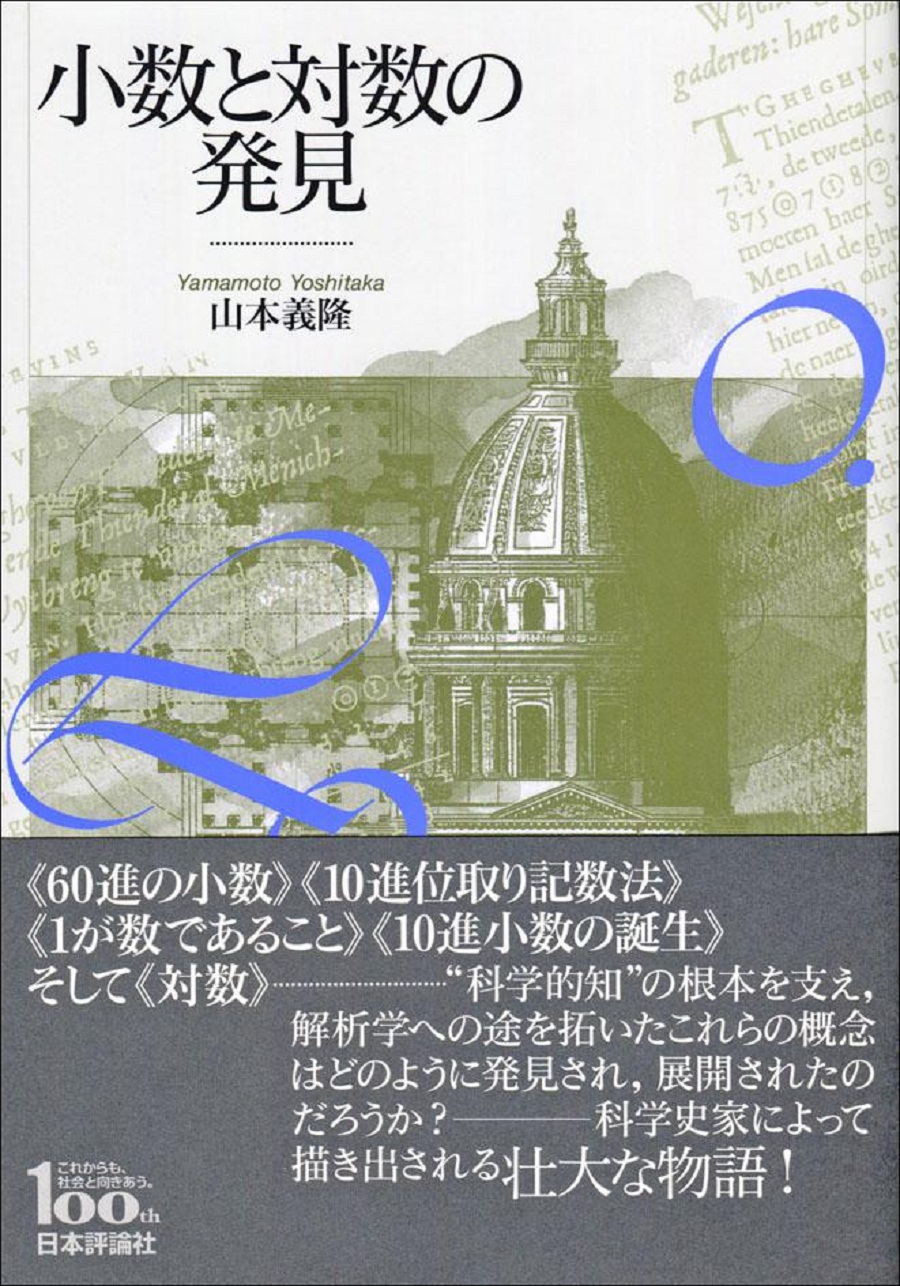
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?