何とも物騒なタイトルだ。『「オウム」は再び現れる』(中公新書ラクレ)。著者の島田裕巳さんは宗教学者。一連の事件が起きる前からオウム真理教に関心を持って接触し、事件後は、マスコミにもしばしば登場してきた事情通だ。その島田さんが「再び現れる」というのだから穏やかではない。
昨年(2018年)7月、オウム真理教の麻原彰晃ら幹部13人の死刑が執行された。これでオウムの問題に決着がついたのかといえば、「必ずしもそうとは言えない」と筆者。一つには麻原教祖の遺骨のことがある。歴史的に宗教指導者の遺骨は崇拝の対象になることがある。というわけで、誰が引き取るか、その行方に関心が集まる。
もちろん現状では、オウムがかつてと同じような形で復活する兆しはない。後継の団体の動きも活発とは言えない。公安当局による信者数の公表人数も横ばい。しかも彼らが何か危険なことをしでかしそうな兆候もないようだ。
ではなぜ、島田さんは「再び現れる」というのだろうか。
島田さんはオウムの組織の在り方と、犯罪を実行するに至った信者たちの関係に注目する。尊師を頂点に、階段状に正報師、正大師など20ほどに細分化された「ステージ」。下位の者は上位の指示に従わざるを得ない「タテ社会」だ。この構造はかつて政治学者の丸山真男が『超国家主義の論理と心理』で分析した戦前の日本社会と同じだと島田さんは指摘する。しかもその構造は、昨今マスコミで話題になる様々な問題でも明らかなように、今の日本社会にも根強く残っている。
「オウムの信者が数々の犯罪行為に加担したのは、個々人が強固な信念を持っていたからではない。グルである麻原との距離を推し量り、その上で、より上位の者の指示に従って行動しただけなのである」
島田さんは、俘虜に対する暴虐行為で裁判にかけられた日本人戦犯の例を引き合いに出しながら論じる。オウムの犯罪者たちが属していた社会とは、「一般社会とは異なり、個別の行動に対して責任を持つ必要のない社会だった」。つまり、オウムは、宗教としては異色だったが、その組織構造は極めて日本的であり、日本が無謀な戦争に突っ走っていった時代と現在とを比べた場合、日本人の行動原理、組織原理は変化していない、ゆえにオウムのような組織が再び現れる可能性は十分あり、それが宗教という形を取るとも限らない、と強調する。
そして、私たちがオウムの事件から学ぶことがあるとすれば、それは、自分の属している組織がおかしな方向に向かっていると感じられたとき、そこでどのように振る舞えばいいのかという問題である、と語る。組織的捏造や隠蔽、改ざん。あるいは危険タックル。この何年か日本で起きた諸問題を思い起こして、暗い気分になる人もいるのではないだろうか。
本書は全体として、オウムの歴史を駆け足でフィードバックした作りとなっている。その中では、すでに知られていることかもしれないが、「土谷正実」に関する部分が興味深かった。土谷は筑波大の大学院の博士課程で学んでいた科学者。サリンだけではなく、毒ガスとしてはVXやソマン、タブン、シクロサリン、マスタードガス、ホスゲン、シアンガスなどを製造した。このほか、TNTを始めとする爆薬やLSDなどの幻覚剤、覚醒剤のメタンフェタミン、麻酔剤のチオペンタールなども。「土谷個人が、何でも製造できる化学工場のようなものだった」と島田さん。
オウムの他の科学者たちが、ことごとく失敗した「開発」を土谷だけが、たった一人で「成功」させたという。特別の「研究室」が与えられ、そこでおもうぞんぶん、好きな実験に取り組んでいた。サリン製造には葛藤があったらしいが、義務だと思ってやったという。
歴史に「もしも」ということがしばしば言われるが、オウムでも「もし土谷が入信していなかったら」どうなっていただろうか。島田さんは「松本サリン事件や地下鉄サリン事件は起こっていなかった・・・その点で、土谷の存在は極めて大きい」。
本欄では関連で、『サリン事件死刑囚 中川智正との対話』(株式会社KADOKAWA)、『オウム真理教事件とは何だったのか?』(PHP新書)、『逆さに吊るされた男』(河出書房新社)、『カルマ真仙教事件』(講談社文庫)、『宿命 警察庁長官狙撃事件』(講談社)を紹介している。
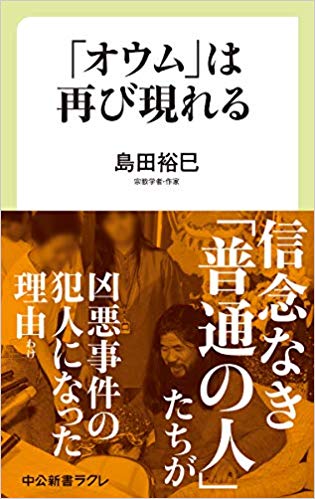
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?