いわゆる「裏世界」では、時折、とんでもない人物が現れて伝説を作るが、『ストリップの帝王』(八木澤高明著、角川書店)で描かれる瀧口義弘の「伝説」は超ド級だ。何しろ、妻子ある地銀マンという堅実な人生を捨てストリップ界入りして、「帝王」と呼ばれるほどの存在になったという異色の人物。それだけで驚いている場合ではない。というのも、次々と明かされる瀧口の半生は「武勇伝」だらけなのだ。
刃物を持ったヤクザと大立ち回りして相手を病院送りにした。全国300人の踊り子のキャスティングを一手に握り、劇場に手配していた。最高月収は1億8000万円を越えていた。しかもその金を湯水のようにギャンブルに投じていく。イジメ同然の取締りに腹を立て、ダイナマイトを腹に巻いて警察署に乗り込んだ。不法滞在の踊り子を使ったかどで職業安定法違反となり全国指名手配されたが、時効になるまで逃げ切った......。数え上げればきりがない、伝説だらけの人生は、ヘタな脚本家だってそんなストーリーにはしないだろうと思ってしまうほど破天荒。まさに事実は小説より奇なりを地で行くような一代記なのだ。
戦後のストリップは1947年、東京・新宿の帝都座で産声を上げた。額縁ショー、金髪ショーとどんどん過激になり、70年代後半にはステージ上で踊り子と客が"本番プレイ"をする「まな板ショー」があちこちの劇場で行われるようになった。瀧口が銀行員を辞めてストリップの世界に入った頃は、このステージ上での売春行為が人気を博し始めていた。やがて、舞台上だけでは客を捌けなくなり、ステージ脇に個室を作って踊り子とセックスする"ピンクサービス"が現れ、ストリップは隆盛を極めていく。
この売春同然のサービスを担うのが、フィリピンや南米から来た不法就労の外国人女性たちだった。そんな彼女たちの"芸能プロダクション"でもあった瀧口の元には大金が転がり込んできた。また、傾きかけた地方のストリップ劇場の再生を任されると、瀧口はピンクサービスや大規模宣伝作戦で次々と再建していき、「帝王」の地位を固めていく。
しかし、時代は変わっていく。バブル崩壊後の長引く不景気によって温泉街の衰退が始まる。風営法の改正によって性的サービスへの規制は強まる。ネットの発達によって女性の裸が簡単に目に入るようになると、ストリップ劇場への客は遠のいていく。温泉街の劇場から始まったストリップ劇場の衰退は街場に伝播していったが、帝王は自らの理想のストリップのあり方を守り続けた結果、業界は時代の変化に取り残されてしまった。
ストリップ業界という望まぬ世界に引き込まれ、己の才覚と哲学でトップに上りつめた男の栄光と挫折......。単純に評伝として読んでも面白いのはもちろんだが、バブル期以降の社会風俗史としても学ぶべきところが多かった。
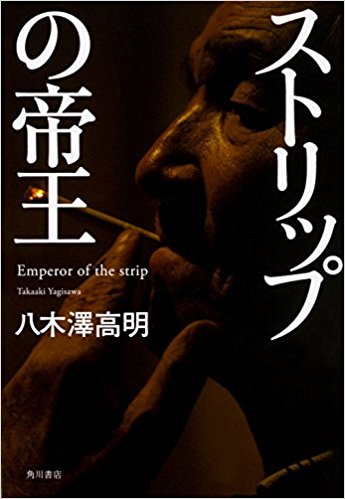
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?