村上春樹、五木寛之、川端康成、松本清張、石川啄木ら、生まれ育った町を離れ、東京をめざした作家、またそんな若者を描いた作品を「上京者」という視点で読み解いたのが、本書『上京する文學』(ちくま文庫)だ。
「赤旗」に連載、2012年に新日本出版社から刊行され、当時さまざまな書評で話題になった。「上京者」の一人である評者も読もうと思ううちに入手できなくなり、今回、加筆・修正の上、書下ろし原稿を加えて文庫化されたのを機会に読んだ。著者の岡崎武志さんは30歳を過ぎて上京した書評家。
19人(解説の重松清さんの特別寄稿を含めると20人)のうち一番面白かったのが、毎年この季節になると、ノーベル文学賞候補として名前が挙がる村上春樹の項だった。
『ノルウェイの森』や『象工場のハッピーエンド』、『村上朝日堂』など、村上春樹の小説やエッセイをもとに、彼の上京以来の軌跡を追っている。
東京生まれの東京育ち、就職後も東京に住む人への違和感を岡崎さんは、こう書いている。
「お金がかからない、という点ではうらやましいような、大人になっても両親の庇護のもとに暮らすのは、どこか歪なようなと、複雑な感想を彼らに持つ。繰り返すが、他府県から『上京』して、東京で一人暮らしすることは上京者の特権なのだ」
神戸から上京し、早稲田大学に入学した村上春樹も「生まれてこの方、一人で暮らしたのははじめてだったから、毎日の生活はとても楽しかった」(『村上朝日堂』)と孤独感よりも解放感を味わったようだ。
目白の学生寮、練馬、三鷹のアパート、妻の実家が営む文京区千石の寝具店、国分寺、千駄ヶ谷のジャズバー。その足跡は東京の西側に偏っている、と岡崎さんは指摘する。そして、「関西から上京して来た者は、東京の西側に住みたがるようだ」と感想をもらしている。
1981年、作家一本でやっていく決意を固め、店を人に譲って千葉県船橋市に移り住む。「村上春樹の『上京』は、このとき終わりを告げたのかもしれない」と結論づける。
その後、村上は海外にも居住しながら創作活動を続けてきた。その原点は大学入学時の上京にあり、最初の夜に、がらんとした部屋で読んだのがジョン・アップダイクのペーパーバックだったというのは象徴的だ。
夏目漱石の項では、漱石自身は東京出身だが、『三四郎』の主人公が上京者なので、作品に沿って解説している。九州から上京した三四郎は、市電と人の多さ、東京の広さに驚いた、と書いている。
「尤も驚いたのは、どこまで行っても東京がなくならないという事であった」
明治の後期ですでにこういう状況であった。東京の都市圏はその後も拡大を続ける。神奈川、埼玉、千葉へと外延部がひろがり、いまや東京都市圏の全貌を見通すことは困難になっている。現代の上京者が東京を描く文学もまた変わらざるを得ないのでは、と思った。
若者だけが東京を目指したのではない。松本清張は朝日新聞西部本社に在勤中の44歳のときに芥川賞を受賞。東京本社への転勤に伴い、上京した「遅れて来た中年」だった。そのことがよかったのでは、と岡崎さんは考える。
「上京者の清張は、作品の舞台として東京を多く描きながら、同時に東京を起点に地方への目を向けた」 「清張の作品群は、地方をよく知る者の目が、東京という巨大な都市を見た時にどう映るかという実験でもあった」
福岡郊外の香椎が犯行現場となった『点と線』、金沢が舞台の『ゼロの焦点』......。主人公、犯人、刑事ら登場人物が地方と東京を往還する中で、ストーリーが推進する。
本書では評論家、川本三郎氏の「東京を地方によって相対化する。東京人には見えない、東京の負の部分が見えてくる」(「東京人」2006年5月号所収「地方から東京を見た、清張の東京論」)という分析を紹介している。
今も清張作品が繰り返し、ドラマ化、映画化されて人をひきつけて止まないのは、東京に来た上京者と上京せずに地方に残った者、双方に「東京」の光と影を照射し続けているからだろう。
東京への憧れで上京した太宰治、石川啄木。生涯で9回上京した宮沢賢治にとって「銀河鉄道」とは上京する夜行列車を指していたのではないかなど興味深い指摘がある。人それぞれの上京があり、東京を舞台にした文学がある。
今、地方を舞台にした文学作品が増え、芥川賞などを受賞する機会も多い。翻って、現在、「上京文学」はあるのだろうか、そんなことを考えた。
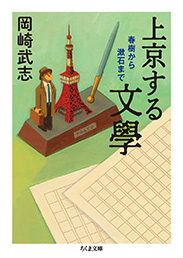
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?