ホタルが光ることは誰もが知っている。しかし、卵のときから死ぬまで光り続けていることを知る人は、きっと稀だろう。昆虫はかつて身近な生き物だったが、あまり馴染みがなくなって久しい。光続けるホタルのような昆虫の驚異ともいうべき生態を紹介するのが本書『日本昆虫記』(株式会社KADOKAWA)だ。
本書は復刊本だ。朝日新聞に連載された記事を基に同社が刊行したものが初版。太平洋戦争が始まった1941年のことだ。 53年の朝日文化手帖版、59年角川文庫版、82年講談社学術文庫版を経て本書に至っている。初版はブックカバーの中央に穿たれた丸い窓からカミキリムシのイラストがのぞいていた。
古い本なので、著者の大町文衛さんを知る人はほとんどいないはずだ。明治から大正期に活躍したの文筆家大町桂月の次男として1898年に生まれた。東京帝国大で細胞遺伝学を学んだ昆虫学者で、のちに「コオロギ博士」として親しまれた。旧制中学などの教員を経て、三重高等農林(現・三重大)教授を務めた。73年に亡くなっている。
新聞への連載は、おそらく正月に始まったのだろう。「目出度い虫」から始まる
「わが可憐なる昆虫諸君は、一口に虫けらといって卑しめられたり、子供の玩弄物となったりする運命しかもっていないように見える。私は何かその面目を保てるようなものはないかと考えた末、思い当たったのが、タマムシであった」
とした上で、虫の形態的特徴や文化とのかかわりに触れる。法隆寺金堂の玉虫厨子には1282匹が使われているそうだ。
続けて、大きい虫、小さい虫、虫の母、虫の父ときて光る虫となる。「ホタルは世界に1200種くらい知られており、日本にも40種くらい産しているが......光るのは3種」。このうち、ヘイケボタルは「間接に充血吸虫を駆除してくれる」という。
光るメカニズムについては「発光物質が酵素の作用で酸化されるとき発光することぐらいしかわかっていないが」としながらも、発光を増幅する器官を説明。発光層の外側にレンズ層、奥に反射層が備わっていて「構造の微妙なことは驚くばかり」だとしている。
このあと後半は昆虫食や害虫駆除の紹介が中心になる。農学部で昆虫を学んだ経緯によるためだろう。害虫被害というと、庭木を食うケムシ程度を想像しがちだ。しかし、歴代の飢饉には干ばつ、大水、冷夏などといった異常気象によるものだけでなく、害虫の食害によるものも大規模にあったと指摘している。
当時としては、最新の知見が集められた内容だったが、本書にそれを求める今の読者はいないだろう。例えばホタルの発光については、発光反応の基質(ルシフェリン)が酵素(ルシフェラーゼ)の作用によって中間体を生成。それが酸素と反応して発光体(オキシルシフェリン)が生成されることが分かっている。
ではなぜ、今回再版されたのだろうか。それは随筆としての味わいの深さだろう、と推測する。読んでまず感じたのは、ゆったりした語り口とユーモアだった。ネットや政治など最近、世間は早口で余裕がない。評者は、本書にどこかほっとしたのと同様に、初版が発行された昭和16年、息苦しい時代の読者もやはりほっとしたのではないだろうか、と思った。
ちなみに同名の映画『にっぽん昆虫記』(1963年)は、はかなくもたくましい女性の生きざまを描いた今村昌平監督の代表作だ。関連があるに違いない。
大町さんの著書は本書のほかはすべて絶版になっているが、『虫・人・自然』(甲鳥書林)、『虫と人と自然と 随筆集』(東和社)、『大町博士書簡集』(小川正彦編 私家版)などがある。
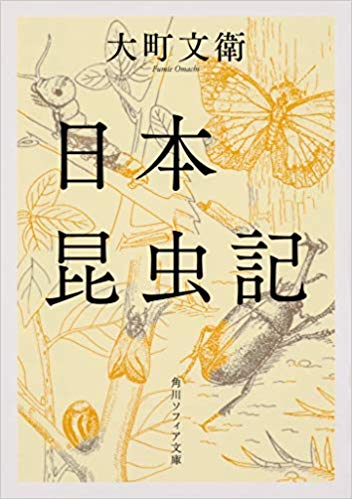
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?