日本は戦前に回帰しつつあるのではないか。また戦争ができる国になっているのではないか。そんな指摘を聞くようになった。
いや、それは杞憂だ、ありえない、タメにする議論だという反論や楽観論もある。どっちが正しいのか。
本書『よみがえる戦時体制――治安体制の歴史と現在』(集英社新書)は前者の立場に立って警鐘を鳴らす。日本は今「あたらしい戦前」にあるというのだ。
著者の荻野富士夫さんは1953年生まれ。小樽商科大の名誉教授で専攻は日本近現代史。『特高警察』『思想検事』(岩波新書)、『小林多喜二の手紙』(岩波文庫)、『「戦意」の推移』(校倉書房)、『日本憲兵史(小樽商科大学研究叢書)』(日本経済評論社)など多数の著書がある。新聞などマスコミに登場する機会も多い。
本書は5章に分かれている。前半の第1章「戦時体制の形成と確立――どのように日本は戦時体制を作っていったのか」、第2章「戦時体制の展開と崩壊――どのように治安体制はアジア太平洋戦争を可能としたのか」では戦前の戦争態勢づくりについて述べる。この辺りはさすがに専門だけあって詳しい。
続く第3章は「戦後治安体制の確立と低調化――速やかな復活にもかかわらず『戦前の再来』とならなかったこと」。戦後の保守が逆コースを志向しつつも、戦後の民主主義、平和主義、経済重視で中途半端に終わったことを記す。
著者が懸念を表明するのは本書の後半だ。第4章「長い『戦後』から新たな『戦前』へ――どのように現代日本は新たな戦時体制を形成してきたのか」、第5章「『積極的平和主義』下の治安法制厳重化――新たな戦時体制形成の最終段階へ」。80年代以降、「新たな戦前」への転換が徐々に進み、積極的平和主義という名の自衛隊の海外派遣が繰り返され、このところの解釈改憲や特定秘密保護法・共謀罪法で一段と加速したとみる。
このあたりの大きな見取り図は、立場によって評価の違いはあれ、個々の事例としてはその通りだろう。安倍政権が「戦後レジームからの脱却」に執心してきたのは周知のとおりだ。著者は戦前の治安体制研究の専門家として、「テロ防止」「治安維持」を口実に、反対する者を監視、抑圧する「戦争ができる警察国家」ともいうべき体制がよみがえっていると見る。治安維持法と特定秘密保護法・共謀罪法とは内容が異なるが、当局の恣意的な運用が可能という点では共通しているというわけだ。また、北朝鮮の核・ミサイル開発で、「国益」を守るために武力行使もやむをえないという機運が出始め、国民が呑み込まれようとしていることに警戒感を高める。
荻野さんのシビアな見方には、教鞭をとってきた「小樽」が影を落としている。小樽は戦前、治安維持法のもとで拷問死したプロレタリア作家、小林多喜二(1903~33)が育った地なのだ。多喜二は小樽商業学校から小樽高等商業学校を出て北海道拓殖銀行(拓銀)小樽支店に勤務していた。
著者は多喜二が32年の『沼尻村』という小説で、労使協調路線の組合幹部にこう語らせていることを紹介する。「満州は我々日本の生命線だ。あそこを取れば、自然我々のこの苦しい状態も楽になる...」。別の登場人物は「満州に無産者の王国を」と意気込む。今から考えると、首を傾げるが、当時はそういう気分があったということなのだろう。
戦争というものは、権力者の側だけが用意するものではない、国民の側からも「戦争協力」の動きが出る。そこに多喜二は早々と注目していたことを著者は強調している。大事な指摘だといえる。
大正デモクラシーの時代は、メディアも国民も軍縮の側に立ち、軍部には批判的だったとされる。ところが昭和に入り、山東出兵などを契機に戦争態勢が強まる。31年の満州事変では「満蒙は我が国の生命線」と叫ばれ、日露戦争で20万の死傷者を出して獲得した満州の権益を守れという声がメディアや国民の間で高まった。戦争準備が進む中で、33年には治安維持法で1万4000人以上が検挙されるなど、言論統制や弾圧が一気に強まり、反戦の動きは封じられた。
朝鮮半島情勢はこのところ急激に様変わりし、戦争が遠のいたように見える。鳴り物入りで成立した共謀罪はの施行後、この一年間で立件ゼロ。日本の内外はやや落ち着きを取り戻したようだ。本書の警告は、今のところ杞憂に終わっている。とはいえ、メディアも国民もちょっとしたきっかけで暴走しかねない「あやうさ」を内包しているという指摘は忘れないようにしておきたい。
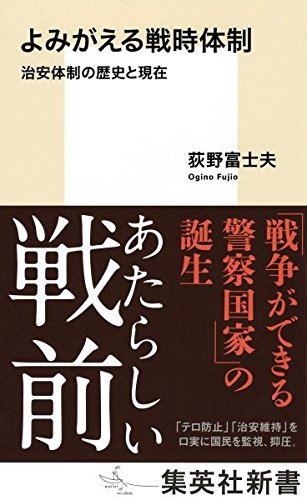
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?