文豪夏目漱石はむろん、小説家として名高いが、さまざまな顔をもった文学者だった。 作家になる前は、日本でトップクラスの英文学者だった。なにしろ本場イギリスに文部省から派遣されたエリート留学生だ。親友正岡子規に習った俳句も素人の域をこえ、俳人といっていい。多くの門下生に慕われた教育者の面もあった。
朝日新聞社に小説記者として入社し、新聞記者(ジャーナリスト)でもあった。朝日では編集者(エディター)の仕事も任される。本書『編集者 漱石』(新潮社)は、若くして小沢書店を設立、長年、文芸編集者として腕を振るった長谷川郁夫さんが、漱石を編集者の面から描いた力作評伝だ。
著者は編集者のしごとを、(1)集める、並べる、分類する(2)見つけて、育てる、と整理する。つまり、メリハリをつけて一覧し、新人を発掘、育てることだ。漱石はこの両面を十分、備えていた。
『吾輩は猫である』や『坊っちゃん』で文名が上がった漱石は、教授就任直前の東京帝大講師の職を捨てて、朝日新聞社に入社した。安定した官立の大学教員から、ベンチャー企業といってもいい在野の新聞社へ、40歳の転身である。義務は長編小説を適宜、執筆、掲載することだった。漱石はそれから9年、命を削るようにして小説を書き続けた。一方で、朝日は日露戦争後の大衆社会の出現にむけ、文化、文芸面の充実をはかるため、朝日文芸欄を設けた。小説や随筆、批評、展覧会評などを、紙面のひとところに集めた面で、現在の文化面、文芸面の前身である。漱石は、事実上、文芸欄の編集長を任された。
文芸欄には、メインになる批評や小説のほか、海外文化の短信なども添えられ、バラエティーにとむ工夫がなされた。筆者には漱石の門下生のほか、漱石グループとは肌合いの違う自然主義系の作家や、武者小路実篤ら白樺派の若者にも声をかけた。著者はこうした漱石の編集力について「漱石の柔軟な公正さが表われているとも感じられるが、同時に戦略のしたたかさを思うのである」と評している。
編集という仕事は他人を相手にする以上、ときにトラブルが生じる。ある若い批評家が文芸欄用に書いた原稿について、抗議がきた。筆名が認められない、タイトルを変えられた、文章に手が加えられた、などだ。文芸欄の実務を担当する門下生の森田草平の不手際が原因だったが、漱石は「そう正面からお切込みなっては叩頭、謝罪するほかないが、そう厳粛に権利問題としないでこちらの意見もそう怒らずに聞いてほしい」(大意)などと手紙を書き、妥協点を探っている。こうしたいきさつを詳しく紹介するあたり、著者も編集者として同様の問題で相当苦労したんだな、と思わせる。
漱石にはもう一つ、重大な編集者の仕事があった。自分が書いていない時の連載小説の選定、依頼である。日本近代文学史に残る『土』(長塚節)、『銀の匙』(中勘助)を発掘、掲載させたのも漱石だった。
『こころ』の連載のあとは、若手作家十余人に短編小説を書いてもらう予定だった。漱石は辞を低くして若い作家に原稿依頼の手紙を出したが、なかなか原稿がそろわず、やきもきした。この時期は『こころ』の最終章、「先生」が「明治の精神」に殉じて自殺にむかうクライマックスのころだ。自分の小説の結末をつけながら、気苦労の多い編集作業も続ける漱石の力技に、感嘆せざるを得ない。
著者は本の編集者らしく、モノとしての本にも注目、本の装丁や挿画に漱石がいかに関心を持ち、気を配ったかを力説する。装丁家として橋口五葉を発掘、アールヌーボー風の曲線をあしらった表紙が、漱石の単行本の価値を高めた。漱石は若い画家岡本一平の時事漫画も高く評価し、新聞に掲載された岡本の漫画を、本にまとめるように強くすすめ、世に押し出した。
中央公論の編集者、滝田樗陰が漱石の晩年、漱石山房にしばしば訪れ、漱石に大量の書画を書かせたことは、よく知られる。樗陰はいつも上等の筆、墨、紙を用意し、漱石が書斎に現れるやすぐに書けるように調えた。書かせた書画は次週までに立派に表装され、持ってこられた。漱石は悪い気がしないはずはない。「原稿」を「作品」に昇華する。これは編集者の基本だ。著者は、漱石の編集者としての感覚が樗陰の要望、期待と呼応したとみている。
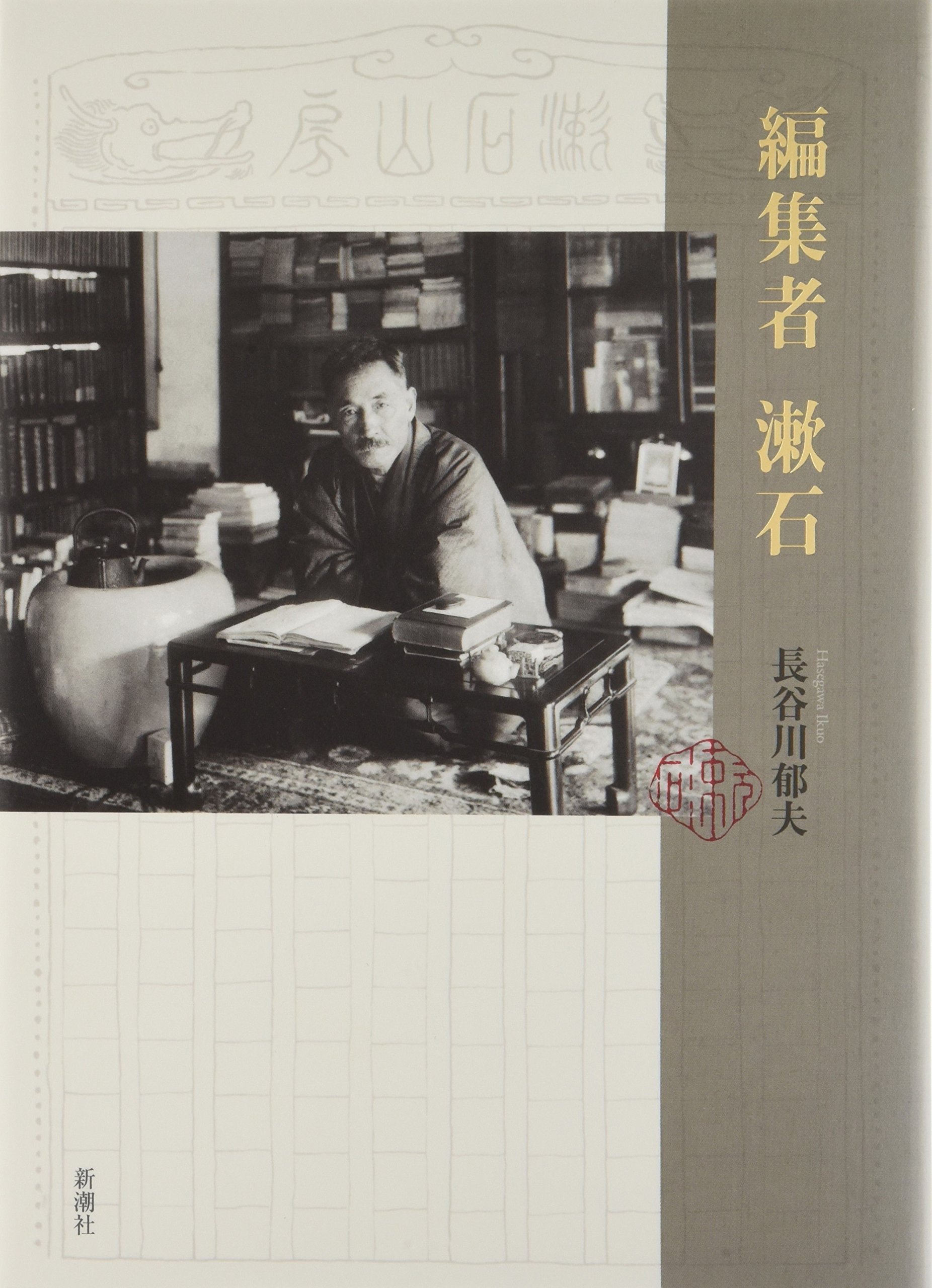
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?