新聞のコラムや連載を長く書き続けることは容易ではない。長く続くコラムでも筆者は数年ほどで代わるのが常だ。また新聞は「紙面改革」と称して、毎年紙面を更新する。その際やり玉に挙がるのが、コラムや連載だ。だから、読売新聞で美術を担当する編集委員の芥川喜好さん(1948年生まれ)が、1981年から通算37年、6シリーズ千数百回の連載を書いてきたというのは、飽きっぽい新聞業界にあって全くの異例。恐らく日本の新聞の中で最も長く連載を続けている記者だろう。
うち、日曜版で11年続いた「日本の四季」は、近世から現代の作家の美術作品を大きなカラー写真とともに紹介。43歳の若さで1992年度日本記者クラブ賞を受賞、美術ジャーナリズムに新風を吹き込んだ、と高く評価された。
その芥川さんがいま連載しているコラムが「時の余白に」ということになる。2006年4月から毎月第4土曜日、朝刊解説面に掲載している。11年9月までの分は同名タイトルで、みすず書房(12年)から刊行された。本書『時の余白に 続』は、その続篇にあたり、11年10月から17年12月までの72回分を改稿したものだ。
前著について哲学者の鷲田清一さんは、「紙面の番外地とでもいうべき場所で、のほほんとした語り口で、じつに骨太の主張をしている。いまの新聞がややもすれば見失いがちな「冷静」と「歯止め」を、この一身でつないでおこうという使命感が、です・ます調の謙虚な語り口に滲みでている」とライバルの朝日新聞書評(12年7月1日付)で賛辞を送っている。
大きな賞賛に恵まれなかった画家や人々により多く目を向けるという姿勢は変わらない。「今(こん)和次郎 採集講義」展(パナソニック汐留ミュージアム)を訪ねては、考現学の始祖とされる今に、「ああ、全く視線の方向の違う男がここにいる」という感想を抱く。中央に集まった上昇志向の強い男たちの中で、「民家、バラック、街頭、身の回り、と常に低きを這い続けました」と、今の「低い視線」に共感を寄せる。
また、新潟県新発田市で開かれていた洋画家、佐藤哲三の油彩風景展を晩秋訪れ、東京に出ることなく、一生北方の厳しい風土を描いた佐藤の作品『みぞれ』に、「近代が生んだ風景画の最高峰です」と最大の賛辞を送る。「空を覆うほの暗い赤と灰褐色の雲が田の面に映りこんで鈍く輝く、ものすさまじくも美しい画面」と形容する絵を見て外に出れば、雨が降ったかと思うと「黒い雲の間から光が差して海の方から明るんできます」という劇的な展開、「佐藤さんの絵のようですね」という地元の人のことばに「土地に生きてきた方が佐藤哲三を『発見』した瞬間です」と記す。
中央画壇を長く取材し、「壇」というものを知り尽くした人だが、取材の足はしばしば地方に向いている。長崎県諫早市の諫早図書館で開かれた「吉永裕・里帰り展」は、画家を志し18歳で上京してから半世紀「模索と漂流」を重ね、「和紙にパステル」という独自の表現を切り拓いた画家を、高校の同級生たちが迎えて開いたものだった。「故郷は遠かった。自分の作品が受け入れられるとも思えなかった」「抽象表現への抵抗もなく、みな素直に見てくれた。東京の個展ではなかったことです」という談話を紹介している。
コラムの題材は美術ばかりではない。「売れようが売れまいが」、たった一人で50年間450点を刊行してきた深夜叢書社の発行人、齋藤愼爾さんは俳人で文芸評論家でもある。作家の瀬戸内寂聴さんが呼びかけた50周年と励ます会を取材し、「寂聴さんの言う『昔と全く変わらない』『その道の親分になろうとしない』青年の魂と、抵抗の意志ゆえに、半世紀続いたことが分かる気がしました」と報告する。
解説面という紙面に、芥川さんのコラムを置いているのも、読売新聞のひとつの見識だろう。せちがらい有象無象の現象をそれらしく解説する記事の中で、まさに「余白」のような精神的なゆとり、豊かさをもたらす文章である。読んでいると、心が落ち着いてくる。
同社のホームページでは、「編集手帳」(朝刊1面)、「よみうり寸評」(夕刊1面)など新聞の顔とも言えるコラムと並んで「時の余白に」を紹介している。
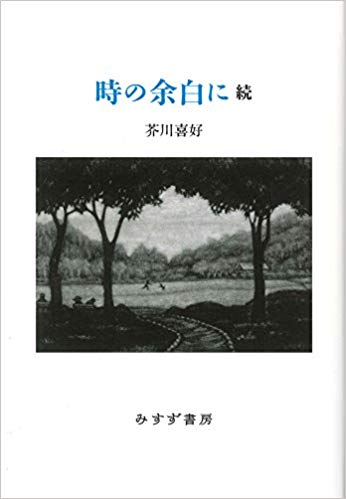
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?