平成が終わろうとしている。30年ほど前にも同じようなことがあった。昭和が終わろうとしていた。そのころ刊行されたのが本書『私の昭和史』(岩波新書)。表紙には著名な評論家の加藤周一さんの名前が大きく出ているが、加藤さんは編者。実際には一般人の原稿を集めたものだ。
庶民にとって、昭和とはどのような時代だったのか。そんな問いかけで、岩波新書の編集部が読者に投稿を呼びかけ、入選作15編が掲載されている。類書はいろいろあるのだろうが、「岩波新書」の読者層による投稿ということで、文章も内容も緊張感があり、レベルの高さがうかがえる。いま読んでも全く色あせない。
一つの元号で「戦前」と「戦後」という「二生」を経た昭和。どうしても戦争の影が付きまとう。
「八路軍と共に八年」という一文を書いている本間雅子さんという女性を紹介しよう。大正の末に、瀬戸内の山間の農村で生まれた。小学校6年の時、満蒙開拓団に誘う講演会があり、胸を躍らせた。お上のすることに間違いがあろうとは思いもよらなかった。
太平洋戦争が勃発した翌年、村の郵便局に勤め始めた。当直の夜、仮眠中に電話のベルで起こされる。手にした受話器から届いたのは、兄の戦死を知らせる電報だった。震える手でようやく書き取った。
1945(昭和20)年5月、戦況が緊迫する中で満州の憲兵隊に所属する男性と結婚した。新郎は帰国できない。写真を相手に結婚式を挙げ、満州に渡る。
そこで本間さんの人生は急変する。日本が負けたのだ。中国の民衆が襲い掛かり、家財は一夜にして残らず消えた。夫とはぐれ、中国共産党の「八路軍」に召し上げられる。野戦病院で中国人傷病兵の看護をさせられることになった。脱走しても捕まる。野戦病院だから戦況に応じて移動する。極寒の北朝鮮まで退却を強いられたこともあれば、万里の長城を越え、黄河や揚子江を渡り、ベトナム国境近くまで迫ったことも。二本の足で、兵士たちと「行軍」を続けたのだ。
1949年に新中国が成立して国情が落ち着く。戦後8年たってようやく帰国できた。夫はすでに別の女性と結婚していた。
不本意な形で召し上げられた八路軍だったが、いっしょに働いた中国の人たちとの別れには胸が詰まったという。のちに周恩来首相は「中国政府は一部の日本人に感謝している。彼らは医師、技術者、看護婦としてわれらの解放戦争に参加してくれた...」と謝意を述べた。
本間さんはこう振り返る。「私たちの力は一握りの砂に等しいものだったが、わずかでも役立てたと思えることが私自身の心の灯になっている」。
その後、帰国仲間と再婚、夫の郷里の小樽に落ち着く。夫婦生活は平穏に27年間がすぎた。夫は定年後まもなく亡くなり、子供のいなかった本間さんは故郷で静かに余生を送っている...。
戦後世代の体験記では1962年生まれの金子千寿子さんの「一畳半の女たち」が心にしみる。投稿当時は新宿のゴールデン街でアルバイトをしていた。かつての"青線"だ。スナックやバーなどがひしめく木造店舗の三階は長く売春部屋だった。
マスターに「三階は当時のままになっているよ」と言われ、のぞいてみる。二階の天井板を外し、垂直に近い階段をよじ登ると、広さ一畳半ほどの部屋が4つあった。売春防止法が施行されて相当の時間がたっているのに、布団が敷きっぱなし。その後もしばらく利用されていたということか。ミカン箱の上には小さな電気釜。横にピンクのスーツケース。日焼けしたカーテンを開けると、一抱えもある仏壇が現れた。ここに生きていた娼婦たちはその後どうなったのか。炎天の路地に迷い出てきた黒揚羽を見つけ、もしや彼女たちの魂が、この世に舞い戻ってきたのではないかと想像する。
最近、レトロ風俗の写真集は少なくないが、ここまでぞっとする生々しい描写は珍しいのではないか。短歌を詠む金子さんはこんな一首をはさんでいる。
この街で一番古いトメさんはただ一升の米で売られた
金子さん自身も、戦後の繁栄とは無縁の半生を送ってきた。母は、金子さんが高校生のころ、三人の子どもを置いて家を出た。外に男をつくったのだ。ところがある日、金子さんが暮らす東京のアパートに転がり込んできた。目の前で倒れ、生活費を娘に頼ろうとする。その後、関係を断った。「今日まで、思い出したい何ほどの思い出も残ってはいない」。そんな金子さんの生き埋めにしてきた辛い青春と、娼婦たちの物語が混然と溶け合っている。
編集部の公募には649編が集まった。それぞれ力作であり、「多様性」を軸に加藤さんが選び抜いたのが掲載された15編だという。筆者は20代から80代まで幅広い。男女はほぼ半々。
昭和初期の窮乏で、熊野灘沿岸の漁村では、生まれた子の半分が母の手で扼殺されていたとか、終戦を知った朝鮮人の元従軍慰安婦が、大変な剣幕で現地の将校宿舎に怒鳴り込んできて、大隊副官の指示で茶碗酒を飲ませてなだめたとか、いろいろと驚くような話が出てくる。最近人気の「自分史本」として、どれも十分に成立しそうなものばかりだ。
加藤さんは、歴史を知るには、遠望して天下の形勢を察すると同時に、近接して個別的な状況を見る必要があるという。「この小さな本は、昭和史において近接の視点を提供する。私はそこで新たに学び、改めて多くを考えた」。
まもなく終わる平成はどうだろうか。阪神淡路大震災、オウム事件、東日本大震災などの災厄や事件に見舞われたが、総じて昭和ほどの起伏や断層はない。なんとなくのっぺらぼう。岩波新書編集部も、読者の平成体験記を募集しづらいのではないか。
本書を読んで、改めて思う。「八路軍」の本間さんや、「一畳半の女たち」の金子さんはお元気だろうか、その後どうなされただろうか。昭和に生まれ育って、波乱万丈だった時代の一端を知る評者には少々気になるところだ。本書は絶版のようだが、復刊を期待したい。
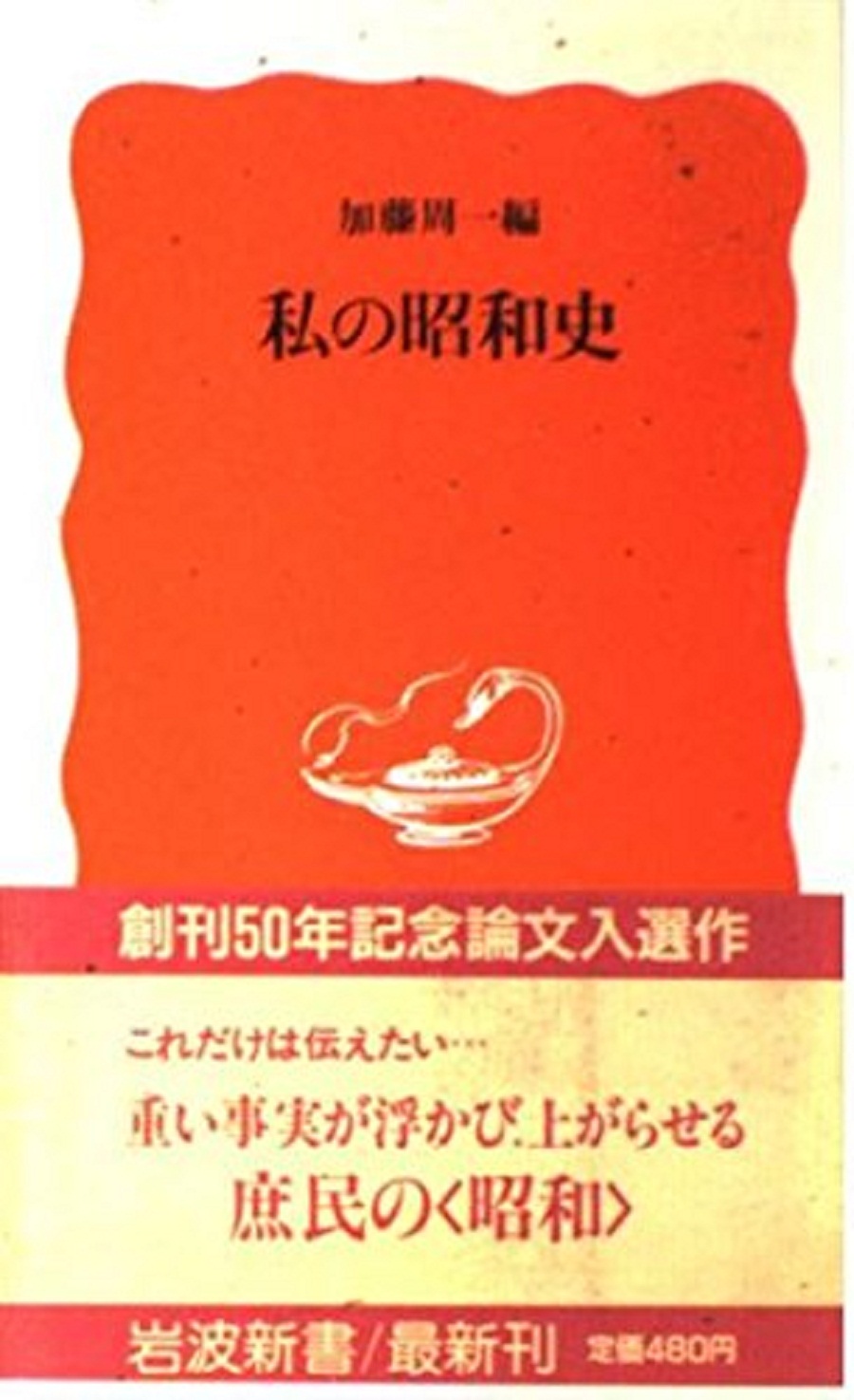
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?