有名な人だが、実像については詳しく知らなかった。『兎の眼』『太陽の子』などで多くの読者を獲得した児童文学者、灰谷健次郎さん(1934~2006)。
小学校教師を途中でやめて作家になり、子どもを主人公にした作品で不動の地位を築いたことぐらいは知っていたが・・・。
本書『いのちの旅人』は、意外にも灰谷さんについての初めての評伝だという。作品同様、壮絶だった灰谷さんの半生や、血気あふれる強烈な個性が浮かび上がる。あれほどの凄味がある作品を残した作家は、さすがに並の人間とはパワーが違う、本人自身がドラマの主人公になってもおかしくない、ということを改めて認識できる一冊だ。
著者の新海均さんは、光文社の元編集者。「月刊宝石」で灰谷さんに対談企画をお願いしたのが最初の出会いだ。それから灰谷さんが亡くなるまでの20年余り、仕事以外も含めて身近なところでずっと付き合ってきた。
本書は大別して、二部に分かれている。前半は、灰谷さんの少年時代から、作家として有名になるまで。後半は、有名になってから、新海さんが直に見聞した話が中心だ。
前半部では極貧だった幼少期の話が強烈だ。小学生のころ、家に食べ物がなくなり、次兄と二人で夜明け前の小学校に忍び込んだ。校庭に植わっていたトウモロコシを盗もうとしたのだ。宿直の先生に見つかり、泣きながら事情を話すと、先生は「そうか、辛かったな」。自分の家に連れて行って、白飯を腹いっぱい食べさせてくれた。
中学では強制的に「就職組」に振り分けられた。家が貧しかったからだ。高校に行きたかったが、ハナから問題外。学校ではよくケンカした。ポケットにはいつもチェーンを忍ばせていた。凶暴な問題児として教師を困らせた。
ゴム工場、港湾労働者、菓子職人見習い、溶接工・・・仕事を転々としながら、何とか定時制高校に通うようになり、そこで同じような境遇の仲間と出会う。昭和20年代の半ば、朝鮮戦争の特需で日本が立ち直ろうとしていたころだ。
級友の多くは年上だった。一緒に酒を飲み、語り合い、紅灯にも出入りする。まじめな政治活動にも参加した。友人の自殺や失恋などもあった。人生経験を積み、文学への関心も深めた。友人の一人から、「オレの代わりに勉強してくれ」と入学金などを工面してもらい、二年制の大阪学芸大学(現在の国立大阪教育大)に進学する。卒業後、神戸で小学校の教師になった。
体当たりの熱血教師。原点は「トウモロコシの先生」だろう。学校に泊まり込むことが多かった。子供たちの学芸会の脚本は一晩で書き上げ、上演を見た親たちが大粒の涙を流した。同人誌にも属して小説を発表、61年、『梁の手』が読売短編文学賞を受賞する。選考委員の武田泰淳は、「このうまさに用心深く注意すれば、作家として伸びる可能性が多い」と評した。その後、紆余曲折を経て74年の『兎の眼』がミリオンセラーに。トイレも炊事場も共同という、かつては遊郭だったわびしい四畳のアパートで書き上げた。続く『太陽の子』も大ヒット、硬派の児童文学者として無二の存在になる。
一方で、二度の結婚は破たん。妻はいずれも自殺未遂。人気絶頂時は講演に引っ張りだこで謝礼は一回50万円。ヨットやクルーザーが趣味で、家づくりには贅沢をした、などと聞くと、真摯な作品群との距離感がうまくつかめず、ちょっと引いてしまいそうになる。しかし、謝礼は全額相手側に寄付したり、受け取らなかったときもあった、知り合いに貸して返ってこなかったお金が合計すると5千万円ぐらいある、服は3、4着だけ、有名になっても、貧乏だったころと何も変わらなかった、などと聞くと、なるほどと思ったりもする。
様々な社会活動にも積極的にかかわった。1997年、神戸で「酒鬼薔薇事件」が起きた時は、新潮社の写真週刊誌に、被疑者の少年の顔写真が掲載されたことへの抗議として、同社から自分の全作品を引き上げた。新潮文庫などで25作品、計800万部の売り上げがあったというからスタンドプレーではない。双方に痛手だったことだろう。その顛末も、本書で詳しく紹介されている。
著者の新海さんはこう記す。
「灰谷は単に書斎にこもる孤独な作家ではなかった。行動する作家であり続けた。行動しながら、世の中のゆがみにノンを言い続けることをやめなかった」
灰谷さんの著作は近年アジアを中心に30冊以上が翻訳されているそうだ。とくに韓国では静かなブーム。『兎の眼』の子ども版がすでに17万部も売れているという。「落ちこぼれを許さない」「どんな子にも、素晴らしいところがある」という灰谷さんの、自らの人生経験を踏まえた痛切なメッセージは、国境を越えて響いているに違いない。
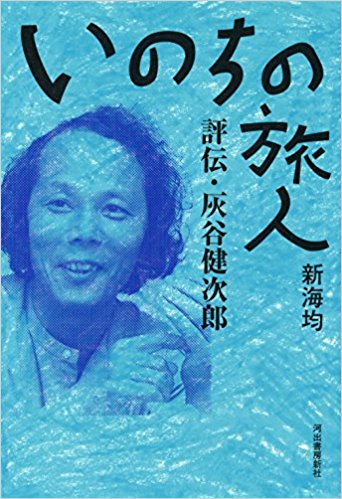
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?