読んでいると、だんだん怒りが込み上げてくる。どうしてあのような「無茶」がまかり通ったのか。立案遂行者の責任はどうなっているのか。
旧日本軍の特別攻撃隊、いわゆる「特攻」のことである。その怒りを著者の劇作家、鴻上尚史さんも抑えきれなかったのではないか。いや、その怒りがあったからこそ、本書をノンフィクションとして書いたということだろう。
まず驚かされること。それは特攻という戦法が、あまりにも無謀で効果が薄いということを、実戦経験が豊富なパイロットから何度も指摘されていたのに強行したということだ。今風に言えば「現場の意見」を「本部が無視した」。
戦艦を撃沈させるにはどうすればいいか。本書によれば、艦船の内部で爆弾を爆発させるのが最も効果的だと分かっている。そのためには、高所から爆弾を落とし、高速で甲板を貫く必要がある。貫く速度は高度に比例するので、高度3000メートルから徹甲爆弾(甲板を貫く威力を持つ爆弾)を落とすというのが最低条件とされていた。
ところが、特攻攻撃の武器となる飛行機の降下速度は爆弾の落下速度の半分程度。軽金属でつくられているから、運よく戦艦に体当たりできても、「卵をコンクリートにたたきつけるようなもの」。
優秀な爆撃機パイロットを抱える現場の鉾田飛行師団は、特攻作戦に反発した。陸軍の航空本部や第三陸軍航空技術研究所に、「体当たり攻撃がいかに無意味で効果がないか」という理論的反論をした公文書を三度も出したそうだ。しかし、却下。「崇高な精神力は、科学を超越する」というのだ。
戦況は悪化する一方。もはや高空から爆弾を目標に上手に落とせるパイロットを養成する時間がない。1944(昭和19)年秋、特攻用の飛行機に爆弾を縛り付け、自爆する神がかり戦術が始まった。
本書の主人公、佐々木友次伍長は陸軍の特攻作戦の第一陣、「万朶(ばんだ)隊」の一員だ。当時21歳。鉾田飛行師団に所属し、最終的に9回出撃して9回還ってきた。まさに「不死身の人」である。
なぜ佐々木伍長は何度も「生還」できたのか。「万朶隊」の隊長に指名された鉾田飛行師団の岩本益臣大尉(当時28歳)の存在が大きい。岩本大尉は操縦と爆撃の名手と知られていた。したがって、操縦者の生命と機体を犠牲にする特攻作戦に強く反発する一人でもあった。自分たちは血の出るような訓練で、爆撃飛行技術を磨いてきたのに、「体当たり」はそのすべてを否定することになる。
最終的に岩本大尉は、特攻隊長としての出撃命令には従いつつも一計を講じる。飛行機に縛り付けられた爆弾を手動で落とせるように独断で改造させたのだ。命令違反だが、航空機の修理を担当する航空廠の分廠長は黙認した。特攻攻撃を「馬鹿げた戦術」と考える人が少なからずいたのだ。
フィリピンで最初の特攻出撃。大本営発表によると、佐々木伍長は「戦艦に向かって矢の如く体当たりを敢行して撃沈」。しかし、実際には佐々木伍長は生きて還ってきた。
軍上層部は慌てた。そしてただちに、「死んだ男」に再度の出撃を命じる。特攻隊員は死ぬことになっている。すでに死んだ、と発表し、「軍神」になっている。死んでもらわないと困るのだ。そうして何度も出撃命令が繰り返され、そのたびに佐々木伍長は還ってくる。
「万朶隊」の要員に指名されたのは、それまでに多数の戦果を挙げていた腕利きのパイロットが多かった。初回を成功させる必要があったし、軍上層部には、彼らでさえ、この特攻作戦の先頭に立っているということを強くアピールすることで、戦意高揚を図る狙いもあったとされる。
ところが皮肉にも、佐々木伍長はあまりにも腕がよかったようだ。冷静な判断力に加え、運も味方した。「生還」を繰り返す佐々木伍長に対し、軍上層部から「銃殺命令」も出ていたそうだが、フィリピンのジャングルで生き延びて46(昭和21)年1月、日本に戻った。
著者の鴻上さんは2009年、元特攻隊員とNHKディレクターによる共著『特攻隊振武寮 証言・帰還兵は地獄を見た』(講談社、09年刊)を読んで佐々木伍長のことを知った。15年春、自身が司会をしているBS朝日の「熱中時代」のプロデューサーに話したところ、少したって興奮気味の報告があった。「佐々木さん、生きてますよ」。
鴻上さんは、札幌の病院に入院中の佐々木さんに会いに行く。糖尿病が悪化して失明していたが、記憶はしっかりしていた。戦後は北海道の実家で農業を継いでいたという。4回にわたるインタビューの内容が本書に採録されている。その後、佐々木さんは次第に体力が弱り、16年2月9日、亡くなった。92歳だった。
本書の最終章「特攻の実像」で鴻上さんは、これまでに様々な立場の人が書いた特攻隊についての本の内容を整理し、まとめている。特徴は、「特攻を命じた側」と「命じられた側」に違いがあるということだろう。「命じた側」は、特攻隊員たちの多くは志願したと書く。だが「命じられた側」は、志願せざるを得なかったと本音を記す。また、「命じた側」には反省もなく戦後を生き延びた人がいる、など特攻をめぐる立場の違い、「格差」を強調している。
本書では海軍の特攻隊の第一陣、「敷島隊」を率いた関行男大尉の出撃直前の発言も引用されている。「日本もお終いだよ。ぼくのような優秀なパイロットを殺すなんて。ぼくなら体当たりせずとも敵母艦の飛行甲板に50番(500キロ爆弾)を命中させる自信がある」と内々に語っていたというのだ。
20代で新しい演劇の旗手の一人として登場した鴻上さんも今年60歳、還暦だ。あと2か月遅かったら佐々木さんにはインタビューできなかったし、10年前の自分なら書けなかったと振り返る。本文はテンポの良い巧みな文章とミステリー仕立ての劇的な構成で一気に読ませる。そのまま映画化、テレビドラマ化もできそうな内容だが、難しいのだろうか。
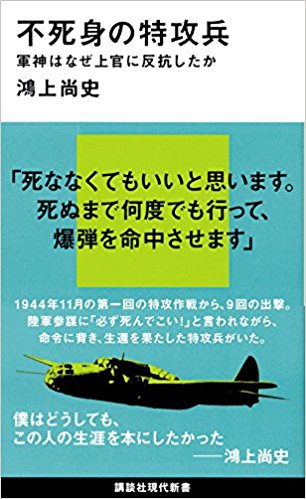
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?