人生100年時代だという。政治家の中でそれを実現しているのが中曽根康弘元首相だ。2018年5月に100歳になる。このところ以前ほど頻繁にはメディアに登場しないが、昨年5月には99歳で白寿の会のパーティが催され元気なところを見せた。
中曽根氏は歴代総理や有力政治家の中でもずば抜けて著書が多い。読書家としても知られ、膨大な蔵書の一部は故郷の記念館で「ライブラリー」になっている。引退後に週刊誌「サンデー毎日」で各界の有名人と対談を続けたこともあり、人物としての幅も広い。
本書『自省録―歴史法廷の被告として』(新潮社)は2004年に単行本として刊行され、昨年、文庫化された。ストレートに政治家人生を振り返り、内外の政治家との交友などをつづっている。著書の中でもわかりやすく、本音のエピソードに満ちている。
冒頭でいきなり「怨念」が語られる。小泉純一郎首相(当時)への不満だ。2003年、はるか後輩の小泉首相から、議員引退を迫られたのだ。中曽根氏は当時85歳。しかし1996年、自民党から「終身比例代表1位」と認定され、ご本人は文字通り「終身現役議員」を続けるつもりだった。
小泉氏は世代交代を加速させたかった。引導を渡すため、自ら中曽根氏のもとに出向く。なかなか難しい局面だ。小泉氏ははっきりしたことを言わない。というか、言えない。中曽根氏の顔を見ようとはせず、うつむいている。中曽根氏の怒りが次第に高まっていく。そして、こんな言葉を吐く。
「おい、敬老精神が、ないじゃないか」
たぶんこの時は相当の迫力だったに違いない。返す刀で、本書では小泉氏を思い切りクサす。総理総裁の言動は慎重にも慎重を要するものだが、小泉氏はそうではないと。「瞬間芸」の人だと。巧みなパフォーマンスで支持率を上げている「ショーウインドー内閣」にすぎないと。「思想、哲学、歴史観」がないと。
このほか本書では興味深い話が満載だが、わかりやいところでは、過去の大物政治家の人物月旦がある。中曽根氏の長い政治歴を反映して吉田茂氏から大平正芳氏まで12人が並んでいる。それぞれ的を射ているが、自身の「政党人のあり方」は河野一郎氏や松村謙三氏から、「宰相学」は佐藤栄作氏から教わったと書いている。
永遠の競争相手は、47年の総選挙で一緒に初当選した田中角栄氏。年齢も同じだった、ということはもし田中氏が生きていたら、今年100歳ということになる。
群馬3区で覇を競い、「福中戦争」「上州戦争」と言われた福田赳夫氏については記述が避けられている。得票数では、福田氏に負けることが多かっただけに、なかなか複雑な思いが沈澱しているのだろう。
海外の政治家との交遊は特に面白い。中でもサミットの休憩時間に、各国のトップが「英語組」と「フランス語組」に分かれて雑談したという話が目をひく。中曽根氏は大学時代にフランス語を勉強していたので、意外にもミッテランを主役とするフランス語組。サッチャー、レーガン、ドイツのコール首相らはほとんどフランス語を話せず、英語組だったという。
ミッテランとは仏教とか禅の話もした、何度も会ったが、「お前のフランス語は会うたびに上達している」とお世辞を言われたそうだ。このあたり、中曽根氏の得意満面、うれしそうな顔が目の前に浮かぶ。
「歴史法廷の被告」というサブタイトルを反映して、過去の報道などについての「反論」もある。有名な「不沈空母発言」にも触れられている。83年の訪米時、ワシントン・ポスト紙の社主との朝食会で「日本は不沈空母」「日米は運命共同体」と発言したということが報じられ、内外で反響を呼んだ。本書で中曽根氏は「万一有事の際は、日本列島を敵性外国航空機の侵入を許さないよう高い壁を持った船のようなものにする」とは言ったが、「不沈空母」とは言っておらず、意訳された結果だという。
ただし、中曽根氏は、誰が通訳しても結果はそう違わなかったとし、ワシントン・ポスト側から訂正の申し入れもあったが、その必要はないと答えたことも明かしている。
この問題には後日談がある。2017年1月に外務省が公開した外交文書の関連記録のなかに、日本語で「日本列島を不沈空母のように強力に防衛」との文字があったのだ。日本側の外務省の記録だ。各社が中曽根氏に問い合わせたところ、事務所から「今回、一定の期間を経て外交関係の資料が公になる。政治はそうした点を十分に認識し、後の時代の評価にも十分に耐えうる政治を行わなければならない」というコメントが出された。核心はぼやけた回答だった。
日経新聞には「私の履歴書」という人気連載があり、中曽根氏は92年に登場している。中曽根氏も含め、有力政治家については『保守政権の担い手』として文庫化されている。その解説部分で、政治学者の御厨貴氏は、中曽根氏の「私の履歴書」の内容について「ハデな言動や君子豹変をくりかえした中曽根は、今まさに自らの行動を他者に、あるいは後世の読者に説得しようと、一生懸命なのだ」と記す。そして中曽根氏のそうした「饒舌」がこの「私の履歴書」で終わることなく、「さらに前人未到の回顧と提言をつづけていくのであろう」と予言している。本書はまさに御厨氏の予言通り、「履歴書」の続編となっている。
「歴史法廷の被告」という意味深長なたとえは、すでに「履歴書」の最終盤で使われている。それまでに連載で書いた政治家歴の内容を振り返る中でこう記している。「歴史の法廷の被告にしては自己主張が強過ぎたとの忸怩たる思いを禁じ得ない」。
「法廷の被告」というのは「起訴」されているということ。レトリックとしてはキツいが、それだけ政治とは厳しいものだという自覚を持った宰相だった。もちろん「勝訴」の確信は揺るがなかったはずだ。
本書の「自省録」という書名はおそらく、ローマ皇帝で五賢帝の一人、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの哲学書の借用だろう。「思想、哲学、歴史観」がない近年の首相たちとは自分違うのだという自負が凝縮されている。
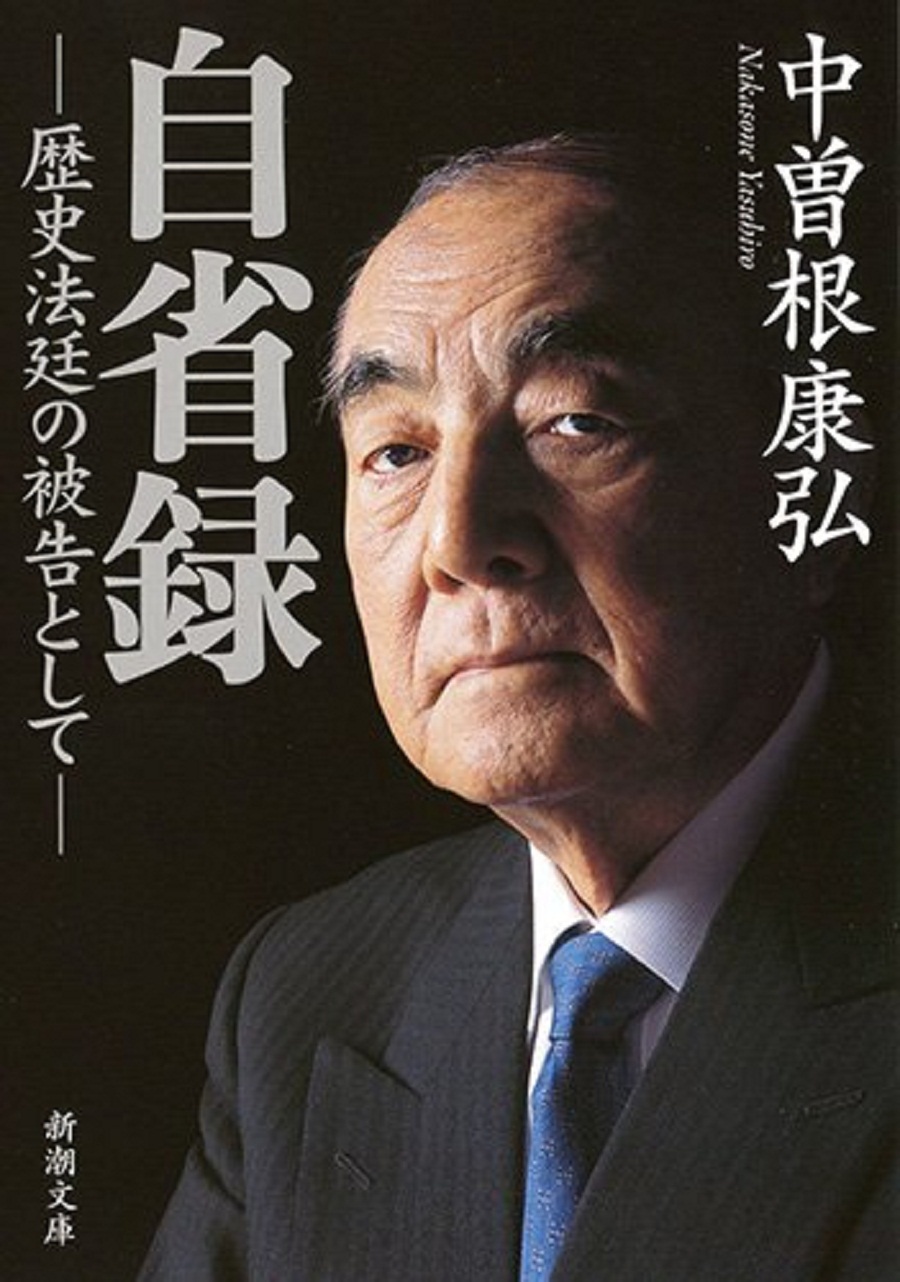
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?